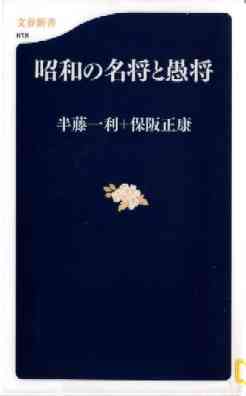帝国海軍 vs 米国海軍 文芸春秋平成19年11月号

文芸春秋8月号で「昭和の海軍」が大きく取り上げられた。この記事は管理職のビジネスマンに大反響があったという。柳の下の2匹目のどじょうを狙って、再び帝国海軍が誌面を飾った。帝国海軍にはまだまだ市場価値があるのか。それはともかく、負けた海軍と勝った海軍を比較するのだから、負けた側のわれわれから見るとちっとも面白くない。しかし、斯界の権威者が薀蓄を傾けて、秘話を披露するのでなかなか読みごたえがある。始めて目にするエピソードもあり勉強になった。座談会参加者は次の方々である。
半藤一利 昭和史研究家
福田和也 文芸評論家・慶大教授
秦 郁彦 日大講師
戸高一成 海軍史研究家・大和ミュージアム館長
江端謙介 軍事評論家
鎌田伸一 防大教授
以下に、その中のいくつかを摘記しよう。
学徒動員
日本で学徒動員が行われたのは昭和18年10月であった。一方、米国では開戦と同時に動員が行われた。米軍の撃墜王リストの上位20番までは学生上がりである。日本は学徒動員の遅れで負けたのではないかと秦郁彦氏はいう。緒戦の勝ちに目がくらみ、わが国はあらゆる部門で緊張感が欠けていたのであった。以下は私が昔読んだ別の本からの情報である。昭和17年の1日、第4艦隊長官、井上成美中将は、麾下の艦長をトラック島在泊の旗艦鹿島の後甲板に集めて、昼食会を催した。
食事の間中、軍楽隊がクラシックや民謡などを演奏した。長官は艦長たちに、希望する音楽を言えと促したという。ひとりの艦長が戦後書いた本によれば、こんなことをしていていいのかとその艦長は思った。米国太平洋艦隊では、開戦後すぐに軍楽隊は解散、隊員は別の戦闘配置に配属されたという。
一系問題
海軍草創期に、兵科将校の中心は、薩摩など官軍の出身であった。ところが軍艦を動かすエンジニアリングでは、幕府出身者が多数を占めた。幕末に多数の幕臣の若者が、海外に留学して、技術を学んだのである。旧幕府系の奴らに追い越されないように、機関学校を別にして差別したと、半藤一利氏は言う。米国のアナポリス海軍兵学校では1899年に兵科と機関科は一体化した。帝国海軍では、敗戦前年の昭和19年10月に、漸く一体化が実現した。私の経験では、兵学校出身の兵科将校の世界には、機関学校出身者と胸襟を開いて語るという、雰囲気が乏しかったような気がする。一方、機関科士官には、兵科に対する劣等感が存在した。戦後出版されたいくつかの機関科士官の本や、クラス会誌から、そういうことがわかるのである。
アウトレンジ戦法
アウトレンジ戦法というのがある。艦隊決戦において、敵の主砲の弾着距離の外側から、わが主砲を撃てば、わが方に被害のないうちに、敵を撃沈できる。理屈はそうであっても、実際にはそうはいかない。砲弾の飛行時間80秒の間に、被弾回避運動ができる。レイテ沖海戦で戦艦大和は、46糎主砲弾100発を撃ちながら、一発も命中しなかった、と秦氏はいう。私見では、大和が100発撃って当たらなかったのは、大和主砲の射撃能力が特に悪かったわけではない。遠距離からの射撃で、弾が当たらないのは普通の現象である。日本海海戦の聯合艦隊の秋山参謀が、米駐在武官時代、米西戦争の海戦を実地調査したレポートによれば、海戦における、戦艦主砲の命中率は、1%か2%の低率であるという。肉薄して戦う、いわゆる肉を斬らして骨を断つという気持ちがなければ、闘いにおいて勝つことはできない。大東亜戦争中の海戦の中で、昭和17年3月1日のバタビア沖海戦,昭和18年3月27日のアッツ島沖海戦に、アウトレンジ戦法の欠陥が如実に現れている。
ファラガット
福田和也氏は、江田島の海軍兵学校にはネルソン、東郷と並んで、ファラガットの肖像画が掲げられていたという。ファラガットというのは南北戦争における北軍海軍の英雄である。敵に向かって遮二無二突撃する敢闘精神の持ち主で、爾来米国海軍の偶像となっている。そんな肖像画があったかな。私は思い出せない。
暗号解読
昭和17年8月、アメリカ軍がマキン島に突然上陸してきてすぐに撤退した。ドイツ駐在武官が「暗号書が奪われた危険性がある。すぐに暗号を変えるべきだと」と助言してきた。ところが海軍は「そんなことはない」といって、暗号を変えなかった。実際には、ドイツ駐在武官の言うとおり暗号書は奪われていたのだ。翌年4月、前線視察中の山本聯合艦隊長官の搭乗機は、この暗号解読によって米機に待ち伏せされて、撃墜された。海軍が東大数学科の教師や生徒を暗号解読に動員したのは、終戦の年の1945年になってからだという。それでは現代はどうかというと、これもまた心細いものである。次のようなエピソードが語られている。海上自衛隊の暗号担当者が、
外務省の暗号を解読して「こんな簡単なものではすぐ解ける。危険ですよ」と警告したところ、「余計なことをするな」と叱られたという。
山本長官機撃墜の暗号解読については別の意見もある。昨年12月刊行された『真珠湾攻撃総隊長の回想』で、淵田美津雄中佐は次のように言う。ブーゲンビル島の根拠地隊司令は、航空略語暗号という簡単な暗号で、配下の部隊に、山本長官の視察日程を知らせている。これが解読されて、山本長官機は待ち伏せされた。当時のわが政府機関は、軍部といわず、外務省といわず、暗号を重視しなかった事実は疑いない。海軍では軍令部第三部が情報を担当したが、そこは日の当たらない閑職であったという。わが海軍に関する限り、暗号の防禦と解読についての心構えと技術において、英米海軍に比べ数段遅れていたのではなかろうか。
山本長官のこのときの前線視察について、聯合艦隊司令部の最初の電報の後、各地の指揮官から、麾下の部隊に対して、いくつかの連絡電報が発信された。これらの電報は、指揮官の立場に応じて、機密性の異なる暗号書によって発信された模様である。同一内容の電報が異なるシステムの暗号で打たれたのだ。解読者にとっては、またとない解読のチャンスであったろう。
所見
アングロサクソン民族というのは、戦争の企画・遂行と戦闘技術の合理的なこと、また、謀略の発想とその実行の仮借ないことにおいて、わが日本人よりも数段上を行く。今から1600年前の推古天皇の時代に、聖徳太子は『17条憲法』を公布した。その第一条の冒頭に「和をもって尊しと為す・・・」という言葉が出てくる。 争いをこととしないで、仲良くやるというのがわが民族の特質である。この草食動物的日本人が、肉食恐竜的アングロサクソンに、闘争に於いて勝つことは難しいだろう。これが、大東亜戦争敗戦の教訓でなければならない。
(平成19年10月15日)
戦艦大和 栗原俊雄著 岩波新書 平成19年8月刊
 |
| 表紙カバー
|
戦艦大和は民族の誇りか
このほど岩波書店から 『戦艦大和』 と題する新書が出版された。早速読んでみた。著者は資料を博捜して、戦艦大和の沖縄突入作戦の意義を追求している。聯合艦隊が敢えて、この無謀な作戦を強行せざるを得なかった事情を詳述する。一方では、この作戦に参加した兵員の聞き書きで、戦争の悲惨さを語る。この作戦で、大和乗り組みの3056人が戦死し、生存者はわずかに276人であった。第2艦隊全体では約4千余名が戦死した。ここでこの沖縄突入作戦のわが方の陣容を見てみよう。戦艦大和を囲んで、軽巡矢矧を旗艦とする第2水雷戦隊の駆逐艦8隻が、輪形陣を形成して沖縄に向け出撃する。昭和20年4月7日正午過ぎ、屋久島西方160マイルの海上で敵機の空襲に遭遇する。約2時間の激闘の後、戦艦大和、軽巡矢矧は沈没、駆逐艦磯風、浜風、朝霜、霞が沈没、涼風は大破する。完全な形で生き残ったのは冬月、雪風、初霜の3隻に過ぎない。
著者は、戦艦大和および第2水雷戦隊旗艦、軽巡矢矧の戦闘詳報の一部を紹介する。
大和の戦闘詳報:「・・・思いつき作戦は精鋭部隊をみすみす徒死せしむるにすぎず」
2水戦の戦闘詳報:「・・・作戦はあくまで冷静にして打算的なるを要す。いたずらに特攻隊の美名を冠して、強引なる突入戦を行うは、失うところ大にして、得るところ甚だ少なし」
筆者は新聞記者らしく、「海軍内部の批判」 という小見出しの中で、何等評価を加えないで、この戦闘詳報を引用する。どちらかといえば実施部隊の戦闘詳報に同情的に見える。ずさんな作戦に投入されて、多大な損害をこうむった当事者が、聯合艦隊司令部を批判するのは当然である。しかし、この作戦を戦果と被害の面からだけ評価するのは当を得ていない。
当時は日本の敗戦がほぼ確定した時期である。燃料は底をつき、航空部隊は壊滅し、如何なる精鋭艦隊といえども、敵機動部隊に一撃を与えることのできない時期である。軍令部や聯合艦隊の知恵者も、有効な作戦を立てようもない時期なのだ。一時の精鋭艦隊も、この当時は無用の長物と化していたのだ。当時の実施部隊が、戦争の大勢を知らず、上級司令部を批判するのは、あるいはやむをえないことかもしれない。しかし、敵味方の情報をすべて見ることのできる現代人の著者が、これに、そうだ、そうだと同調するのはいただけない。以下は私見である。
敗戦後、大和が無傷で米国の手に渡ったらどうなったか。米国に持っていかれて見世物になった果てに、ビキニの水爆実験の標的にでもされただろう。帝国海軍の象徴、強国日本の象徴ともいうべき戦艦大和が、そんな惨めな終末を遂げたら、それは、日本民族の永遠の心の傷となるだろう。戦艦大和は、沖縄突入作戦で死処を得たのである。日本人はこれを誇りに思っている。戦後折にふれて起こる戦艦大和ブームは、このことを証明するものだろう。
第2艦隊の将兵、4千余名の霊よ、君たちは帝国海軍の栄光のために殉じたのだ。以て瞑すべし。
初霜救助艇事件
吉田満著 『戦艦大和の最後』 は、昭和27年に講談社から出版された。著者の吉田は海軍少尉として大和に乗り組み、この戦いを大和の艦橋からつぶさに観戦した。大和が沈没すると海中に投げ出されたが、幸い救助されて生還した。戦後、この戦いの模様を書き下ろして、世に問うたのがこの本である。戦い前夜の、大和艦内の緊迫した状況や、凄絶な対空戦闘の始終が、簡潔な文語文で書かれている。一読、手に汗握るような緊迫感があり、
忽ちベストセラーになった。
昭和20年4月7日、午後2時過ぎ、屋久島西方160マイルの東支那海で大和は沈没する。上空に第2波の敵機が去った後、生き残った3隻の駆逐艦から、内火艇が下ろされて、波間に漂う沈没艦の乗組員の救助に当たる。このとき、初霜から出された救助艇の艇員が、舷側に手をかけて救助を求める漂流者の手首を、日本刀を振るって斬るという衝撃的な場面が出てくる。参考までに 『戦艦大和の最後』(角川文庫版) からその場面の一部を紹介する。
”・・・ここに艇指揮および乗組下士官、用意の日本刀の鞘を払い、犇く腕を、手首よりバッサ、バッサと斬り捨て、または足蹴にかけて突き落とす。せめて、すでに救助艇にある者を救わんとの苦肉の策なるも、斬らるるや敢えなくのけぞって堕ちゆく、その顔、その眼光、終生消えがたからん。剣を振るう身も、顔面蒼白汗滴り、喘ぎつつ船べりを走り回る。今生の地獄絵なり―――”
漂流者を目一杯に収容した救助艇は、あとから救助を求めて殺到する漂流者を、拒否してもよいとする。拒否する手段はべつに問われない。状況が切迫している場合は、銃や剣を使うことも想定されるだろう。すでに救助艇に助け上げた多数の漂流者を救うためには、新たな収容は出来ないのだ。この救助艇寓話は日本だけでなく、世界中に流布されている。私たちは、この寓話を、海軍兵学校の「寝言」(注)で一号生徒から聞いた。それは、軍隊というところは、大の虫を救うためには、小の虫を殺すのもやむをえない非情の世界だということを、まだ娑婆気の抜けない新入生に教える教材であったろう。
よく出来たこの海事寓話を、著者の吉田も、海軍入隊後のオリエンテーリングの期間に、教官か先輩から聞いている。吉田は4期の予備学生であった。この寓話を自著に、脚色して挿入したというのが、ことの真相である。著者自ら声高く、ドキュメンタリー作品と謳いあげるこの小説の中に、フィクションを挿入して、しかもそれが事実であったと強調しているところに、この問題の発端がある。
昭和42年、初霜艇指揮として、この救助作業に当たった海兵73期の松井一彦氏は、全く事実無根のこのエピソードを、再版の場合には削除するよう著者に書面で申し入れる。著者はこの申し入れに対し「考えさせてくれ」と答える。しかし、昭和49年の再刊には、この話は、削除も訂正もなく残った。その上、吉田は再刊のあとがきに「・・・細部にいたるまで事実の検証には努力を怠らなかった」と書くのである。その後の松井氏の抗議にたいして、彼はあのようなことが起こりうるのが現代戦争の特質で、それを明らかにすることに、この作品の意義があると答える。理屈にもならない屁理屈を並べて、削除を拒んでいるうちに彼は死んでしまった。『戦艦大和の最後』は、英訳されて広く英語世界で読まれる。この話は事実として世界中に流布されたのである。
以下は私の推理である。昭和42年4月、松井氏から削除要請の手紙を受け取った吉田は、出版社と相談したに違いない。相手の松井氏が弁護士であることから、吉田がこの手紙を軽々に処理したとは思えない。相談を受けた出版社は、この残虐で猟奇的なエピソードは、この本のセールスポイントの一つであるとして、削除を承知しなかったのであろう。事実を曲げた上、訂正要求にも応じなかった
ことは、終生、吉田の心の傷として残ったであろう。これは、その後、彼が新聞、雑誌に発表した随筆の中に、屈折した暗い影を残している。
この本の著者は、吉田のエピゴーネンたちが、今なお、「手首斬り」を事実であると強弁していることを指摘している。一人は言う。「吉田さんが書いたことと似たようなことは、恐らくあったはず」(岡野注:第二次大戦中、帝国海軍には「手首斬り」など一件もなかった。一時、ガダルカナル撤収作戦中、「手首斬り」があったという噂が流れたが、すぐに、ためにする流説であることがわかった)。また言う。吉田さんが根拠のない嘘を書くわけがないと。
この本の著者は、毎日新聞の現役の記者である。新聞記者らしく両論を併記して公平を期している。片やフィクション、片や事実の両論を併記して公平を装うのは、フィクションの側に加担しているといわれても仕方がない。あらゆる証拠は「手首斬り」が事実でないことを示している。著者の調査は不十分であるといわざるを得ない。この件を知り合いの元大和乗組員に詰問された吉田が、この部分はフィクションであると認める場面が、この本の中に出てくる。この本の著者は、「手首斬り」が事実でないことを知りながら、敢えてこのような表現をとったとも考えられる。
注:海軍兵学校の「寝言」
海軍兵学校では、就寝の際、当直監事の巡検が終わってしばらくの間、最上級生である一号生徒が、下級生に向かって語りかける。内容は海軍常識、海事常識、海事格言、怪談など多岐にわたる。日頃厳格で、下級生の一挙手一投足にきびしい目を向けて臨む一号生徒が、この時ばかりは、砕けた語り口で、兄が弟に言うように語り掛ける。新入生徒は、談笑の間に海軍のしきたりや、常識を知らず知らずのうちに覚えるのである。これを「寝言」と称した。寝言の上手な一号生徒は下級生から敬愛された。教官の言ったことは大方忘れても、巧妙に語られた寝言は、今なお鮮明な記憶として残っている。救助艇寓話もそのうちの一つである。
(平成19年9月6日記)
真珠湾攻撃総隊長の回想ー淵田美津雄自叙伝 編/解説 中田整一 講談社 2007年12月刊
 |
| 表紙カバー
|
プロフィール
南雲中将の率いる第一航空艦隊は、昭和17年12月7日未明(現地時間)、ハワイ真珠湾を奇襲して大東亜戦争の口火を切った。このとき九七艦攻に乗って攻撃隊を指揮したのが淵田美津雄中佐であった。この本は淵田氏の自叙伝である。氏が戦後書き溜めた自叙伝の原稿を、米国在住の氏の長男が保管していた。これがこのほど陽の目を見たわけである。編者によると、氏の自叙伝の原稿の7割が本書に収められている。氏は海軍兵学校第52期、高松宮のクラスである。
第52期は、大正10年10月8日、海軍兵学校に入校した。採用人員はこれまでと同様300名であった。ところが同年12月には、ワシントン海軍軍縮条約が審議に入り、世界は海軍軍縮の流れとなる。とばっちりを受けて第53期は50名クラスに激減する。校長の千坂智次郎中将の方針で、鉄拳制裁は禁止された。淵田氏のクラスは、上級生に殴られたことも、下級生を殴ったこともなく卒業した由。卒業は大正13年7月、卒業生は235名であった。
彼はミッドウエー海戦を、機動部隊旗艦赤城の飛行甲板で観戦する。というのは、機動部隊が柱島泊地出撃後、彼は盲腸炎を手術して、病室で闘病中であった。飛行甲板の片隅で、担架上、毛布にくるまって観戦中、赤城は被弾する。爆風で飛ばされて、両足を骨折、担架に簀巻きにされて、司令部とともに、軽巡長良に移乗する。内地帰投後は、陸上の教官配置や、戦訓調査などの閑職につく。その後、航空戦隊の幕僚勤務を経て、豊田長官時代、聯合艦隊の航空甲参謀となる。レイテ沖海戦における小沢艦隊の囮作戦は、彼の発案であったという。彼はまた名文家としても有名であった。部下部隊や特攻隊への長官感状の多くは彼の手に成るものであった。曰く「・・・・悠久の大義に殉ず。忠烈万世に燦たり」。
彼は、大東亜戦争で、飛行機隊を率いて個々の戦闘に参加するばかりでなく、戦争の後期には、参謀として、聯合艦隊の作戦の枢機に参画している。交際の範囲は、下は、乗機の電信員から、上は聯合艦隊司令長官にまで及ぶ。活動範囲が広範なため、ひとつひとつのエピソードが、バラエティに富んでいて極めて面白い。
山本司令長官凡将論
彼は山本五十六大将凡将論を展開する。理由は三つ:1)真珠湾作戦終了後、南雲機動部隊を空母2隻ずつの3個戦隊に分離して、南西太平洋方面の支作戦に使用した。大量投入によって、はじめて高い戦果をあげうる航空艦隊を、小規模化するのは、緒戦の戦訓を無視した愚策であった。空母6隻基幹の大部隊のまま、ハワイから米国西海岸を遊弋させて、敵の残存空母を一掃すべきであった。2)ミッドウエイ作戦では、聯合艦隊司令部は、南雲部隊の後方300海里にあって、無意味に戦況を傍観するに終始した。戦艦、重巡戦隊を挙げて輪形陣を形成し、機動部隊の護衛に任ずべきであった。3)イ号作戦(ガダルカナル航空戦)では、空母艦上機をラバウルに上げて、敵の陸軍機との戦闘で消耗し、機動部隊を再建不能に陥れた。この作戦で得た戦果と、失ったものとの差はあまりに大きい。この自叙伝の編者は、淵田氏の山本大将凡将論には組しない。聯合艦隊全般のみならず、陸軍との協同も考えなくてはならない山本長官の立場と、実際の戦闘に参加する現場指揮官との視野は当然違うわけである。
広島原爆
昭和20年8月上旬、海軍総隊(聯合艦隊に代わるものとして、昭和20年4月に設置された)参謀であった彼は、要務のため、広島市細工町の大和旅館に長期滞在中であった。8月5日、打ち合わせのため、彼は建設中の大和基地(本土決戦の場合、海軍総体司令部となる予定、奈良県)に呼び出される。打ち合わせが終わり、翌8月6日朝、連絡機で岩国に向かわんとしているときに、広島に原爆が落とされたことを聞く。
彼は中央から派遣される調査団の一員として、原爆被害の調査を命じられる。実地調査の結果、原爆は細工町の上空500メートルで炸裂しているのであった。彼が定宿としていた大和旅館は跡形もない瓦礫と化していた。爆発時間の8時15分といえば、いつもなら朝食中である。彼は大和出張によって、危うく一命を取り留めたのであった。このときの調査団は、政府の技術畑のお偉方から構成されていた。この調査団は、広島の原爆の調査に引き続き、8月9日の長崎原爆の調査に赴いた。もちろん、放射能に対する何のプロテクションもないまま、1週間以上も爆心地をさ迷い歩いたのであった。調査団員のほとんどが、後に原爆症で亡くなったという。彼は広島原爆の調査報告のため、日吉の司令部に呼び戻され、長期間にわたる2次被爆の被害を免れたのであった。淵田氏が調査中に見た広島の惨状が、後の基督教帰依の最初のきっかけであったと書いている。
キリスト教への回心
淵田氏は昭和26年、49歳で洗礼を受け、キリスト教に帰依する。彼はスカイ・パイロットという特殊な教団の招きで、米国内を講演行脚する。彼の講演はいつも満員であったという。真珠湾攻撃の総隊長という彼の履歴は、戦争の記憶の生々しい米国人にさまざまな関心を呼んだ。敵ながら天晴れという関心も強かった。一方では、憎悪の入り混じった好奇心もあったであろう。講演旅行の途中、アイゼンハウアー大統領、トルーマン元大統領、ニミッツ提督、マッカーサー大将などに招かれて、会食を共にする。こちらからVIPに会見を申し込んで断られることはない。当時、淵田氏は米国でもっとも著名な日本人であった。
その後の人生行路に於いて、彼が座右の銘とするのは、ルカ伝の中の次の言葉であった。
”父よ、彼らを赦し給へ。その為す処を知らざればなり。”この言葉はキリストが、十字架上でまさに処刑されようとしているときに、死刑執行人のために、神に祈った言葉とされる。
彼は日本での講演では、よく新渡戸稲造の次の和歌を引用したという。
”憎むともにくみ返すな憎まれてにくみ憎まれ果てしなければ”
この座右銘や和歌の中に、彼の心情が読み取れるのである。この本の中には、彼をキリスト教信仰に向かわせた感動的なエピソードが詳述されている。
彼のキリスト教への帰依は、海軍兵学校の同期生から強い批判を受けた。単なる宗教問題だけではなく、山本大将凡将論も不評を買った原因であったろう。日本内地はもとより、米国内でも彼は批判を受けた。特定の宗派の広告塔として利用されているというのである。しかし彼は、一切の非難を意に介しなかった。昭和51年没、享年73歳。
(平成20年2月15日記)
エニグマ・コード ー史上最大の暗号戦 ヒュー・S=モンテフォーリ著 小林朋則訳 中央公論新社 2007年12月刊
 |
| 表紙カバー
|
エスピオナージ
エニグマとは謎の意である。エニグマ・コードとは、ドイツ軍が1920年代後半から使ってきた暗号である。ナチス・ドイツはこの暗号を永久に解読不能と豪語していた。この暗号を英国情報機関が如何にして解読したかというのが、この本の主題である。
ドイツ国防省暗号局の上級職員が、フランス情報局のスパイに、国防省の機密を売るところからこの長い物語は始まる。彼がこの売国的な取引を始めるのは、金のためである。彼は1925年(大正14年)から1928年(昭和3年)にかけて、暗号局長であった。暗号表を保管してある金庫を開けるのも、彼の権限である。1931年(昭和6年)、彼は、エニグマ暗号機の操作法マニュアルをフランス側スパイに手渡して、予想外の報酬を得る。その後彼は情報局内の要職に替わるが、ドイツ軍の高度の情報に接する機会に恵まれていた。フランス情報局は、彼に高額の報酬をはらいつづけるのであった。
フランスは、この暗号操作法のマニュアルで、エニグマ暗号の解読に挑戦するが成功しない。英国の情報機関に相談するが、これも効果がない。そのうちに、1939年(昭和14年)9月、英仏はドイツに宣戦布告して、ここに第2次世界大戦が始まる。翌1940年(昭和15年)6月、フランスはドイツに降伏して、ヴィシー政権が誕生する。ここで、ドイツ国防省職員と接触していたフランス情報部員はドイツ側に逮捕される。彼の自白で、元ドイツ国防省暗号局長の非行が明らかとなり、彼は逮捕された後、独房内で青酸カリで自殺する。グレアム・グリーンやジョン・ル・カレのスパイ・スリラーを地で行く話である。
暗号機
エニグマ暗号は先ず原文を一字づつ、暗号機のキーボードに打ち込むと、暗号機に内装された4個のローターとその各々に組み込まれたリングの設定によって、暗号化された文章や記号、数字が流れ出てくる仕組みである。暗号文を受け取った方は、送信の場合と逆の操作で、これを暗号機にかけて、原文に復元するのである。暗号機の接続設定、ローターの設定、リングの設定により、無数の組み合わせが発生する。戦争の進展とともに、ドイツ海軍はエニグマを更に強化するため、ローターを8個に増やす。これによって、リングもまた8個に増え、当時の貧弱な解読技術では、到底解読不能とドイツ海軍は考えていたのであった。このエニグマ暗号機は、当初、商業用として開発された。各国の情報機関はこれを入手して、自国の暗号システム改善の参考とする。我が国ももちろん例外ではない。エニグマは、仮に暗号機が敵手に渡っても、書面による指示でローターやリングの設定を変えれば、再び解読不能となるという優れものである。
ドイツ戦艦ビスマルク
1941年 (昭和16年) 5月、英海軍に、エニグマ暗号解読を急がせる事件が発生する。ノルウェーのベルゲンを出港して、通商破壊戦に出撃したドイツ艦隊は、アイスランド北西のデンマーク海峡で、優勢な英艦隊に遭遇する。ドイツ側は戦艦ビスマルクと重巡プリンツ・オイゲン、英側は就航したばかりの戦艦プリンス・オブ・ウェールスと巡洋戦艦フッド、それに随伴の駆逐艦数隻である。ビスマルクの15インチ (38サンチ) 主砲の数斉射目の1弾は、フッドの第3砲塔下の火薬庫を直撃、フッドは一瞬にして爆発沈没する。司令官、艦長以下1400余名の乗組員が戦死し、生存者は僅かに3名であったという。プリンス・オブ・ウェールスもまた被弾して、戦場を離脱する。ビスマルクも被害を受けるが、この戦いはドイツ側の完勝といえた。その後、ドイツ艦隊は北海上で踪跡をくらます。英海軍は面子にかけて、大西洋に所在する全艦艇、航空機をあげてドイツ艦隊を捜索、追跡する。数日後、フランスに向かうビスマルクを発見し、空母と艦隊の協同作戦で撃沈する。ようやく、デンマーク海峡での敗戦の汚名を晴らしたのである。この一連の海戦は、英海軍首脳部に、エニグマ暗号解読の緊急性を痛感させることになる。
群狼作戦
1940年(昭和15年)8月から、1941年(昭和16年)12月頃まで、ドイツ海軍のUボートによる、カナダから大西洋を横断する英国輸送船団の被害が激増する。輸送船団を発見したUボートは、無線で仲間のUボートを呼び寄せ、複数で攻撃する。これを群狼作戦と称した。1941年(昭和16年)12月8日、日本は米英と戦端を開く。日本の同盟国ドイツは、同年12月11日、対米宣戦を布告する。Uボートにとって、新たな獲物が現れたのだ。とくにカナダのファリファックスから、ソ連のムルマンスクにいたる航路は、対ソ連軍事援助のルートであった。ここにUボートが蝟集して、群狼作戦を展開する。1942年2月、ドイツが連合国共通暗号である海軍暗号第3号を解読するに及んで、輸送船団の被害は最高に達する。1942年1月から、同年8月までの間に、Uボートが沈めた船舶は400万トンに達した。
英海軍は、何とかUボートの暗号を解読して、船団の進路を変更するなど、対策を立てたい。そのためには、エニグマ暗号機の入手が必要であった。
暗号機奪取作戦
英海軍はエニグマ暗号機の入手に全力を上げる。というのは、当時の解読技術では、暗号文の解析だけから、これを解読することが不可能であったのだ。英海軍は、沈没に瀕したUボートに乗り込んで、これを手に入れようとした。爆雷攻撃で沈没必至の状況になったUボートは、浮上して乗組員は海上に逃れる。脱出前に、艦底のキングストンバルブを開けるか、または時限爆弾を仕掛けておくことが多い。Uボート乗組員は、非常の場合、艦を離れる前に、暗号機を破壊した上、自沈装置を起動するよう、教育されている。しかし、乗組員としては、生死を分ける非常の場合、これらの命令どうり実行できるかどうかは不確実なのだ。ここが、暗号機を奪取しようとする側の乗ずるところになる。しかし、
浮上して放棄された潜水艦に乗り込んで、暗号機と暗号表などを探し出して持ち出すのは、成功率の低い決死の作業であった。ある場合は失敗し、ある場合は成功した。
英海軍のエニグマ暗号機入手作戦はこれにとどまらない。巡洋艦を旗艦とし、駆逐艦数隻からなる特殊戦隊を編成して、北海上のドイツ気象観測船を襲うのである。またもっと強力な戦隊で、ノルウエーのドイツ海軍基地を襲い、陸上の事務所や、停泊中の艦艇からこれを奪うこともあった。このようにして、1941年(昭和16年)の終わりには、ついにエニグマ解読に成功する。英情報局は、戦後、天才的な数学者によってドイツの暗号は解読されたと公表していたが、実状はこんなところであった。実状が明らかになったのは、戦後50年たって、戦時中の公文書が公開されてからであった。
ドイツ海軍も暗号保全について、無策であったわけではない。暗号機のローターやリングの設定をしばしば変更する。ひとたびこれが変更されると、全く解読不能となる。英海軍はまたまた、大規模な暗号機奪取作戦をしなければならない。本書では、英独暗号戦争の虚々実々の物語が展開する。
所見 1
第2次世界大戦当時(1938.8~1945.8) 近代国家が数理技術の粋を尽くして作り上げた暗号システムは、容易に解読できないものであった。ナチス・ドイツがエニグマ暗号を、永久に解読不能と豪語したのもあながち、間違いではない。暗号電文を何十枚集めて解析しても、当時の幼稚な計算機の性能では、破ることは出来なかった。英国情報部は早くこれに気づき、海軍をあげて、エニグマ暗号機奪取作戦を展開した。この作戦によって手に入れた暗号機と暗号文を参照しながら、天才的数学者がついに解読するのである。戦後、最後まで解読できなかったものが、複数のコンピュータを接続する方法でやっと解読できたのは、2006年2月であったという。とにかく、今から半世紀ほど前には、今日のような電子計算機も、コンピュータも存在しない。近代的暗号を解読するには、暗号機や暗号書の入手が不可欠であった。
戦時なら、兵力を使って奪取し、平時ならスパイによって盗み取るのである。この本の冒頭に、ドイツ国防省高官による、スパイ行為が詳述されるのも故なしとしない。吉田一彦著 『暗号戦争』 は、連合国は枢軸国の暗号解読を原子爆弾開発に次ぐ重要問題としていたと書いている。
主として、日米海軍が戦った太平洋戦争の場合はどうか。この本は英独海軍間の暗号戦争を述べているので、日米間については一行の記述もない。以下の「所見2」は、戦争初期の、日米暗号戦争の概略である。
所見 2
昭和16年1月20日、石油積み込みのためサンフランシスコに入港したタンカー日新丸は、米官憲による検疫を受けた。検疫自体は恒例のものであるが、この時は、官憲は船長室の金庫を開けさせて、船舶暗号書を押収した。船長の制止にもかかわらず、官憲は暗号書を強奪して行ってしまった。総領事の抗議により、数時間後に暗号書は返還されたが、その間に暗号書は盗撮されていた。米国は暗号書入手のためなら、あからさまな非合法も敢えてするのである。このとき検疫官に扮して乗船してきたのは、米海軍情報部員であった。(本件は実松譲『情報戦の思い出』による)
昭和17年(1942)1月、イ124号潜水艦は豪州北方海域で撃沈される。水深45メートルの浅海に沈没した潜水艦は、米豪海軍によって引き上げられ、艦内から次の暗号書が持ち出された。
戦略常務暗号書D
戦術暗号書乙
航空機暗号書F
商船用暗号書S
漁船用暗号書Z
補給造修用暗号書
これらの暗号書はただちに米国の情報部に送られて解読されるが、戦略常務暗号書と戦術暗号書は解読不能であったと、半藤一利氏は、近著 『山本五十六』 に書いている。私見では、これら2つの暗号書は海水に浸すと消えるインクで印刷されていたのだろう。
昭和17年(1942)8月、ギルバート諸島のマキン環礁に、米海兵隊が未明に奇襲上陸してきた。マキン環礁は、大東亜戦争開戦当初、わが方が占領して、兵曹長を長とする1個小隊の陸戦隊がこれを守っていた。米海兵隊160名は、2隻の潜水艦に分乗して来襲した。数時間の戦闘でわが守備隊は全滅、「0905全員従容として戦死す」の電報を最後に消息を絶つ。来襲の敵兵もすぐに潜水艦で退却してしまう。わが方は所在の航空機による偵察をした後、数日後、陸戦隊を派遣して同環礁を再占領する。
聯合艦隊はこれを敵の偵察上陸と見て、大して意にとめなかった。当時はガダルカナル島に上陸してきた敵との戦闘に忙殺されていたのだ。私見ではこれは暗号書奪取のための作戦であった。1月の、イ124号潜水艦からの暗号書入手は不成功であった。わが潜水艦は、敵の爆雷攻撃で沈没に瀕しても、決して浮上しない。潜水艦から手にいれることが不可能と知った米軍は、防備手薄な島嶼を狙ったのだ。暗号書を入手しても、解読には数ヶ月の時日を要しただろう。しかし、これ以後、わが暗号は解読されていたと考える。翌、昭和18年4月、山本聯合艦隊長官機の待ち伏せ襲撃はこの解読によるものだろう。ドイツ駐在武官が、暗号書が奪われたはずと忠告してくれたことはすでに、上の 『帝国海軍VS米国海軍』 で指摘されている。
昭和18年(1943)1月、イ1号潜水艦は、ガダルカナル島西北の珊瑚礁に座礁する。積んでいた20万冊の暗号書が、米軍の手に落ちただろうと 『暗号戦争』 は書いている。この記事は米書、『The Codebreakers』 からの引用として取り上げられている。この暗号書は、各基地に配布する新しい暗号書ということである。イ1号潜は、この暗号書を、ソロモン方面に散在する各基地に配達していたというのであろうか。わが海軍は西南太平洋の諸島に多数の基地を作ったが、20万冊の暗号書とは荒唐無稽の数字である。その容積と重量を考えると、狭い潜水艦内の何処に積んだのか。昭和18年1月29日といえば、ガダルカナル島撤収作戦開始の3日前である。イ1号潜は何故、多量な暗号書を積んで、敵地であるこの危険水域を航海していたのか。信じがたい話である。この話はサミュエル・エリオット・モリソンの『第2次世界大戦海戦史』による。真相は次のようなものであった。
昭和17年の年末には、ガダルカナル島の放棄が大本営によって決定された。その頃になると、同島の制海権、制空権は完全に米軍側の手に落ち、わが水雷戦隊による補給活動も、ままならない状況であった。糧食の補給は潜水艦に頼らざるを得ない。潜水艦は、陸兵の待機する海岸に接近して、米の入ったドラム缶をホーサーで繋いで海に放つ。陸岸に待機している陸軍の大発がこれを回収する。昭和17年12月末から、翌昭和18年1月末までの1ヶ月の間に、伸べ26隻の潜水艦がこの糧食輸送に従事した。在島3万の陸兵はこれで命を繋いでいたのであった。潜水艦は帰りは傷病兵を運ぶのである。イ1号潜水艦は、ガ島補給任務に付いた潜水艦のうちの1隻であった。
昭和18年1月29日、ガダルカナル島北端、エスペランス岬の西方、カミンボにおいて、糧食揚陸中のイ1号潜水艦は、米軍哨戒艇に襲われる。浮上して砲戦の後、擱坐沈没する。生存者による暗号書処理が不十分であったというので、爆撃機による爆撃、潜水艦による雷撃など試みられたが不成功。
イ1号潜は米軍の手に落ち、米軍は価値ある文書を入手したというのである。
所見 3
大東亜戦争開戦時、わが外交暗号が米国によって解読されていたことは今では、誰でも知っている。わが機動部隊の真珠湾攻撃の前夜、すなはち、1941年(昭和16年)12月6日夜(現地時間)、最後通牒の解読版を読んだルーズベルト大統領は、「これは戦争だ」とつぶやいたという。全く緊張感を欠いていた、わがワシントン大使館では、暗号電文による最後通牒の解読は遅れに遅れた。12月7日午後1時に、国務長官に手交せよという本省の指示にもかかわらず、野村大使が最後通牒をハル国務長官に手渡したのは午後2時20分のことであった。そのとき、ハワイ真珠湾では、わが航空部隊が攻撃の真っ最中であった。
わが外交暗号は開戦の前年には米側によってすでに解読されていた。児島襄著 『太平洋戦争上』 によると、少なくとも昭和16年6月からの外交暗号電報は完全に解読されたと見られる。それでは外交暗号はいかにして解読されたか。米側の言うように、卓越した暗号技術者の超人的な技能で解読されたのか。数理技術の粋を尽くし、周到に作り上げられた暗号システムは、当時の計算機の性能では、事実上、解読できないのだ。わが97印字機もエニグマに引けをとらない堅固なものであった。日本側は解読不能と信じていた。それが解読されたのは、エニグマ暗号と同じ状況なのだ。暗号機や暗号書の現物が相手方の手に渡ったと考えられるのである。
吉田一彦著 『暗号戦争』 によると、わが暗号機は外務省、陸海軍のほか13の海外公館に配布されたという。この海外公館のいずれかで、暗号機は米側のスパイに盗まれたのだ。別の本によれば、ワシントン大使館には3台の暗号機があった。2台は、日常業務に使用されるので、事務所の金庫に保管されていたが、1台は倉庫にしまってあったという。相手方のスパイにとってはまたとない状況である。何らかの手段で倉庫内の1台を持ち出す。暗号機を分解して型取りをし、暗号書を写真撮影するのに2日もあれば十分だろう。後は暗号機と暗号書を、こっそり倉庫内に収めておけばいいのだ。平和時の暗号解読はスパイ活動以外に考えられない。当時の大使館スタッフのモラルの低下は著しく、わが外交暗号がここから盗み出された疑惑は拭えない。上にも述べた英米情報機関の、なりふりかまわないスパイ活動を見れば、この疑惑はますます深くなる。米国政府はこのようなケースでは関係文書を公開しない。真相は永久に藪の中である。
顧みれば、日露戦争の前夜、わが外交暗号はロシヤ側に完全に解読されていた。ロシア側から頼まれたプロの外人スパイは、日本の在外公館から暗号書を盗みだし、写真撮影した上、これをロシアに売る。スパイが目をつけたのは、オランダ日本公使館であった。オランダはヨーロッパの小国で、本省からの暗号連絡が頻繁でないとスパイは睨んだのであった。スパイは公使館に勤めるメイドを篭絡して、公使公室の事務机の、鍵のかかった引き出しから暗号書を盗み出させる。全頁を写真撮影した後、5日後にこれを公使の引き出しに返しておいたのであった。スパイの思惑通り、暗号書を盗み出した5日の間、本省からの暗号連絡はなかった。
ここまでは、ロシア側の暗号書獲得作戦は成功したのだ。しかし、ロシアはスパイに支払うべき報酬を値切って、小額で済ませた。腹を立てたスパイはロシアに報復する。暗号書のコピーを持って、パリにあるわがフランス大使館に現れ、買取を要求する。外務省が、外交暗号がロシアに漏れていることを知ったのは、小村全権団が、米国、ポーツマスの講和会議に臨むため、横浜を出発する直前だったという。急遽、新しい暗号書を持たせて、全権団を送り出したのはいうまでもない。この項は、吉村昭著 『ポーツマスの旗』 によった。
1921年(大正10年) のワシントン海軍軍縮会議においては、主力艦の保有比率を対米英7割とするというのが、日本の強い主張であった。ところが、米国との衝突を避けよという、代表団に対する本省の訓令電報は、米側に解読されていたのだ。会議の席上、如何にわが代表が7割を主張して頑張っても、わが方の腹のうちを知っている米国が譲歩するはずはない。結局、米国主張どおりの6割に落ち着くのである。数年後、真相を知った幣原外相は、米国を 「信義に反する」 と非難するのであるが、後の祭りだ。暗号戦争には信義則は通用しない。この項はロナルド・ルウィン著 『日本の暗号を解読せよ』 によった。
明治以来、わが国外交の重要局面では、ほとんど暗号は相手方に解読されていたようである。ひとり外務省だけではない。わが海軍においても、国運を賭する大規模海戦の場面では、暗号は解読されて、わが手の内は米側に読まれていた。暗号保全に対する関心と、暗号更新の機敏さ、それに相手方暗号を解読しようという貪欲さにおいて、外務省といわず、海軍といわず、わが国の脇の甘さは際立っている。現代でも、情報といえば、いかに早く、いかに正確に、いかに詳細に、公表するかということばかりが議論される。国家的重要情報の秘匿の必要性について、ジャーナリズムで真剣に論じられることは先ずない。わが国においては、情報秘匿の関心が薄く、秘匿すべき情報を堅固に保護せず、情報漏えいの場合の対応が不適切であると、一般的に言えるのではなかろうか。わが国は国際政治の真っ只中を、ただ漫然と成り行きに任せて泳いでいるように見える。信義を以て接すれば、相手も信義で応じてくれるとでも思っているようである。これでは、飢えた虎や狼が彷徨する荒野を、裸で歩いているようなものである。
(平成20年3月1日記)
昭和の名将と愚将 半藤一利+保阪正康共著 文春新書 2008年2月刊
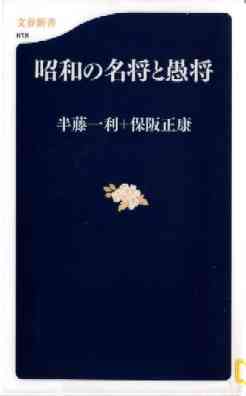 |
| 表紙カバー
|
名将の条件
この本は共著者二人の対談で構成されている。対象となっているのは、前大戦中、わが陸海軍の戦略、戦術の作成や実行に関与した将軍たちである。著者の二人はともに著名なノンフィクション作家である。両著者ともここに取り上げた将軍たちの多くと生前、面談している。それだけに、対談の内容にふくらみがあって、単なる言いたい放題の放談の域を脱している。
それでは名将の条件は何か。保阪は次のように言う。理知的であること、部下に尊敬されていること、原則論を振りかざさないこと。最後に、陸大で恩賜の軍刀組でない人を付け加える。また、駐在武官経験のある人も客観的に物を見る目があるという。
半藤の条件は次のとおり。第一、決断を自分で下す人、第二、任務の目的を部下に明確に伝えられる人、第三、情報を自らの目や耳で掴む人、第4、過去の成功体験にとらわれない人、第五、常に焦点の場所に身を置いた人、第六、部下に最大限の任務の遂行を求められる人。
こうしてみると両者の基準には相当な開きがある。自然科学の定理や法則ではないので、これでなくてはならないという厳密な基準は存在しない。結論は落ち着くべきところに落ち着くものであろう。両者の基準の大きな特色は、本人の性質素行や部下統率の技術に集中していることである。結果の業績については問題にしていない。彼らの挙げるこれらの基準に合致する人は、立派な業績を上げるといいたいのであろうか。両者とも、基準の想定に当たっては、硫黄島を死守して玉砕した小笠原兵団長栗林忠道中将の業績が頭にあってのことと思われる。本書の冒頭を飾る名将が栗林中将であることがこれを立証している。
それでは、愚将の条件とは何か。名将の条件ほどハッキリした記述はない。瀬島龍三編に出てくる 「国家の一大事と自分の点数を引き換えにする軍人」 などという表現が、愚将の条件の一部を表しているようである。
名将と愚将
 |
| 名将と愚将
|
ここに取り上げられた将軍 (一部佐官も含む) は海軍8名、陸軍14名である。先ずこの本の構成を見ると、名将編は昨年、月刊誌に連載されたもの、愚将編は書き下ろし (語り下ろしというべきか) である。一冊の新書の形にするために、愚将編を付け加えたものと思われる。
一回の連載の分量を確保するためか、一回の対談につき複数の将軍が選ばれる。陸軍の栗林中将は例外として1人で一回分を占める。大体、海陸別々になっているが、「今村均と山本五十六」 は例外である。
この本に取り上げられた人物の人選も、その評価も、概ねこれまで言われてきたことと大差はない。ただ「山下奉文と武藤章」が名将として登場するのには一寸違和感があった。山下は二・二六事件の当時、陸軍省軍事調査部長で、叛乱将校に同情的な進退をして、昭和天皇から嫌われていた。武藤章は、開戦時は軍務局長にすぎなかったが、東京裁判で刑死した。不当な死を迎えねばならなかった両将軍に対する、名誉回復の意もあったのであろうか。東京裁判で死刑判決のあった直後、被告たちは、死刑組、有期刑組が別々の部屋に入れられた。有期刑組の部屋から,嶋田繁太郎のうれしそうな高笑いの声が聞こえたと、当日の武藤の日記に書かれている由である。
伊藤整一中将は、昭和16年9月から、昭和19年11月まで軍令部次長の職にあった。この期間は帝国海軍が組織的で大規模な作戦を展開する能力を持っていた時期である。彼はこの全期間を通じて海軍の作戦の中枢にあった。軍令部総長は永野修身であった。彼は昭和16年4月、伏見宮から総長職を引き継ぐ。昭和18年には元帥に補された海軍の最長老である。昭和19年2月、海軍大臣嶋田繁太郎に総長職を譲る。永野の総長職は伊藤の次長職とほぼ重なる。だから伊藤は大東亜戦争の海軍作戦の実質的責任者であったといえる。敗軍の将が何故名将か。それには、彼が第二艦隊司令長官として、大和と運命をともにしたことがあげられる。大和沈没の直前、艦橋から長官室にこもって、中から鍵をかけたといわれる。その前に 「作戦中止」 を命じていることが、著者に評価されている。もしこの命令がなければ、残存の3隻の駆逐艦は沖縄に突入して、撃沈されていたことであろう。新たに約千名の戦死者を加えたことになる。この作戦での戦死者は、6千人に達したであろう。要するに、彼は、死に際の潔さと敗戦の後始末の適切さによって評価されている。
大和は昭和20年4月7日14:21、弾火薬庫への誘爆で瞬時にして沈没する。大和を護衛していた第2水雷戦隊の9隻の艦艇のうち、無傷で生き残った3隻の駆逐艦は、先任艦、雪風を先頭に沖縄に向けて進撃を続ける。
16:39、聯合艦隊から作戦を中止し、生存者を救助して、佐世保に帰投せよとの命令を受信する。伊藤長官が作戦中止命令を出そうが出すまいが、聯合艦隊命令で作戦は中止されたのである。記録によると、波間に漂う生存者の救助が終わったのは18:15であった。その後、航行不能に陥っていた2隻の駆逐艦を処分するのに手こずり、結局、翌4月8日09:50佐世保に入港したという (この部分は、平成2年、松井一彦氏の法曹ネービー会での講演の記録によった)。
伊藤整一は愛妻家としても有名であった。彼の遺書は感動的な名文である。将帥の資質と無関係なこれらの私行上のエピソードもまた、彼の評価を高めるものであった。彼の長男、
伊藤叡(海兵72期)は零戦パイロットとして、昭和20年4月28日、沖縄上空の戦闘で戦死した。この日は奇しくも、父整一の戦死の公報が家に届いた日であったという。
余談であるが、彼の長女純子は私の妻みよ子と、戦前、実践女学校の同級生であった。しとやかでおとなしい大和撫子タイプで、成績は常にトップであった。昭和17年3月の卒業式では、在校生総代として、卒業生を送る言葉を述べ、翌昭和18年3月の自らの卒業式では、卒業生を代表して、在校生を励ます言葉を読んだという。
南部仏印進駐
昭和16年7月下旬、わが国はフランスのヴィシー政府との間に南部仏印進駐の協定を結んだ。両国政府がこれを発表するや、米、英、蘭三国政府は報復として、わが国の在外資産の凍結と石油の対日輸出の禁止を実施した。艦艇や飛行機の燃料を米国からの輸入石油に頼っていた海軍は、たちまち窮地にたたされる。
これより先、昭和15年7月には米内内閣が総辞職した。同年9月には日、独、伊三国同盟が調印される。同盟締結に終始反対してきた米内光政が政界を引退して障害がなくなったのである。米内退陣後も、依然として英米よりの態度を崩さない吉田善吾海相は、海軍中堅クラスの親独・反米路線と首脳部の対英米融和の方針に挟まれて、煩悶焦慮の末、精神に異常をきたして、海相職を及川古志郎大将に譲る。
これらの政治情勢の変化に責任ありとして、岡敬純中将と石川信吾大佐が 「愚将」 欄に名を連ねる。対米強硬派の両氏は、米内光政ー山本五十六ー井上成美トリオが在職中から、尖鋭に対立していたのである。
前月の6月22日にはドイツとソ連が開戦した。陸軍の仮想敵国であるソ連が、欧州において窮境に立たされたことは、陸軍の北進論に力を与えた。
同年7月7日発動された「関特演」は、動員兵力85万人、徴用船舶80万トンにおよぶ大規模なものであった。独ソ戦の様相如何によっては、ソ連との開戦も辞さないというものであった。
陸軍は南部仏印進駐に反対であったとこの本はいう。たしかに、陸軍省の事務局は南部仏印進駐が米国の対日禁輸をまねくとして、これに反対であった。しかし、同じ陸軍でも参謀本部は南進論・北進論をともに主張して陸軍省と対立していた。海軍はどうかというと、6月22日の独ソ開戦によって、北辺の脅威がなくなったとして、南進のチャンス到来と見たのであろう。結局、陸軍は海軍の南進論に組して、南部仏印進駐は実現するのである。半藤の言うように、海軍が陸軍の反対を押し切って南進を主張したとまではいえないだろう。この時点で、海陸の中堅幹部は、たとえ日本が南部仏印に進駐しても、米国は敢えて、戦争を招くような対日禁輸はしないだろうと見ていた。文書の上では「開戦も辞せず」と勇ましい表現をしながらも、わが強硬態度は、かえって彼の自重を促すと思っていたのである。
6月12日の大本営政府連絡会議において、永野軍令部長は「南部仏印進駐が英米蘭の妨害を招けば、断固これを打つべし」と強気の発言をする。結局、7月下旬、陸軍第25軍の南部仏印への進駐が実現する。米英はただちに反応して、日本資産の凍結と対日石油禁輸を実行する。それはともかく、昭和16年6月、7月のこの時点では、岡・石川両氏等の対米強硬論が海軍の政策変更の原動力となった。海軍のこの決然たる政策変更は、政界各方面に違和感を与えたようである。以下は私見である。インテリコンビの及川海相・澤本次官は、事務局の強硬論を抑えきれなかったのだろう。それに、6月22日の独ソ開戦は、海軍首脳を強硬論に踏み切らせる最後の引き金になったのだろう。
将でもない佐官の石川が何故 「愚将」 とされるのか。誰でも不審に思う。
もし責任を云々するのであれば、海軍大臣や次官を槍玉に上げるべきではないか。ここで共著者の1人半藤は、永野軍令部総長の 「いまの中堅クラスが一番よく勉強しているから彼らに任せる」 という言葉を紹介している。これでは、満州事変以来の下克上の陸軍と選ぶところがない。この項の小見出しは 「だらしのない海軍のリーダーたち」 というのである。結局、半藤は、日本海軍の本質はこちらであって、米内ー山本ー井上のラインは異端であったと結論する。
特攻隊の責任者
愚将編の最後に特攻隊の責任者として、海軍では大西瀧治郎、陸軍では冨永恭次・菅原道大の3人があげられる。彼ら3人は何故愚将なのか。彼らは、特攻という愚行を発案し、遂行した責任者だということだろう。陸軍の両将軍は、特攻隊の出発を見送るたびに、「君らだけを行かせはしない。最後の一機で本官も特攻する」 といっていた由である。それにもかかわらず、終戦後は、のうのうと余生を送って、天寿を全うした。武士の風上にもおけない背徳漢である、ということのようである。
それでは海軍の大西瀧治郎はどうか。彼は第一航空艦隊長官として、特攻を始めて、その遂行を指揮した。終戦に当たって、彼は壮烈な割腹自殺を遂げた。海軍の特攻戦死者2千余名に詫びつつ、自らの行為の責任を取ったのである。何故愚将か。
昭和19年6月、サイパン放棄が決まってから、海陸の首脳が集まった席で、伏見宮は 「もはや特別な攻撃方法でやるより方法はない」 といって出席者の賛同を得る。これが軍令部、参謀本部に伝えられ、特攻攻撃はお墨付きを得たと半藤はいう。それまでの海軍では、必死の攻撃は許されないというのが公式見解であった。大東亜戦争の劈頭、真珠湾を攻撃した特殊潜航艇も、最初は兵器として採用することに山本長官の許可を得られなかった。結局、湾内に潜入して敵艦を攻撃後、港外に待機する親潜水艦に収容される段取りを整えた後に、許可されるのである。
昭和19年10月25日、關行男大尉 (海兵70期) の率いる5機の特攻機はフィリッピン、サマール島沖の米護衛空母群を攻撃して、特設空母1隻を撃沈し、他の3隻に被害を与えた。これ以後、特攻攻撃がわが海軍航空隊の主要な戦闘方法のひとつとなる。この特攻を創始し、指揮したのが大西瀧治郎である。故に大西は愚将であるといいたいようである。一方ではまた、軍令部が特攻を承認し、大西はただ職責上、引き金を引いただけだとも言いたいようである。大西に関する限り、半藤の論旨は不明というほかはない。
所見 私の名将論
多数の将軍の中から名将を選び出すためには、選出の基準がなくてはならない。著者の2人は本書の冒頭で、自らの基準を披露している。内容はこの小論でも紹介した。共著者の1人保阪の基準はあまりに抽象的である。また、陸大の成績がよく、恩賜の軍刀をもらって卒業した将軍に名将はいないと言いながら、陸大を2番で卒業した栗林を名将の冒頭に取り上げて、賞賛している。半藤の基準はひとつ何々、ひとつ何々と、一見具体的であるが、あまりに細か過ぎて大局を見失っている。将官ではない
軍務局の石川大佐を、愚将の列に入れながら、中堅クラスに任せるといって、海軍に下克上を許した元帥の永野修身は、愚将とされることを免れている。要するに見当違いの議論が展開されているのである。本書は肩のこらない戦史漫談というところであろう。
それでは、お前は誰を以て名将とするのかと反問されるだろう。先ず名将の基準である。私は、統率力があって、いくさに強い将軍を名将とする。陸軍の栗林忠道中将やインパール作戦で善戦した宮崎繁三郎中将などがこれに入る。海軍では第一次ソロモン海戦で著功を立てた三川軍一中将や、ミッドウエー海戦で、爆装のまま戦闘機の護衛なしで、敵空母を攻撃せよと進言した第二航空戦隊長官、山口多聞少将などをあげる。
名将として賞賛されるべきは、ただに戦場の名将だけではない。軍政においてすぐれた業績を残した将軍もまた名将である。古くは大正時代、首相になった山本権兵衛は文句のない名将である。彼は強力な統率力で帝国海軍の基礎を築いた。また、山本の前に首相になった加藤友三郎も名将の範疇に入るだろう。彼はワシントン海軍軍縮会議では首席全権を務め、首相になってからはシベリア撤兵や軍縮を実行した。太平洋戦争前や戦争中でいえば、米内光政、山本五十六もこのカテゴリーの名将に入れてよいだろう。米内、山本両提督は、日独伊三国軍事同盟に反対して終始揺るぎがなかった。
しかし、私の基準では、敗戦国においては名将の数が少なくなるのはやむをえないところである。
名将論の最後に愚将という用語を問題にしなければならない。愚将とはおろかな将軍という意である。この本にあげられた愚将の中には、陸軍の服部卓四郎、辻正信、海軍では岡敬純、石川信吾などがある。彼らを知るほどの人は、家族友人知己はもちろんのこと、戦記ものでわずかにその言行を知るわれわれのような人間でも、彼らを愚か者と断ずるには抵抗を感ずるだろう。
たとえば服部卓四郎である。彼は昭和14年のノモンハン事件では、関東軍の作戦課において部下の辻正信と組んで、事件を計画し、推進した。結果は装備のすぐれたソ連軍のために、散々痛めつけられた上、惨敗するのである。その後は現地軍と中央をわたり歩いた末、再び参謀本部の作戦課長に迎えられる。戦後は、「服部機関」 なるグループを作って、米占領軍のために戦史編纂に協力する。旧高級軍人が生活に喘いでいた敗戦後の日本で、米軍に取り入って、ひとりわが世の春を謳歌するのである。昭和20年の終わりには、『大東亜戦争全史』 を出版する。支那事変から大東亜戦争の前後を通じての、このような彼の行動に照らして、愚か者といえるのであろうか。むしろ賢いといったほうが正確な表現ではないか。世の潮流の変化に機敏に反応して、常に陽の当たる場所を歩く人間は何処にでもいる。彼らを愚者ということは出来ない。服部は、a lot of smart person
(多数の抜け目のない人たち) の典型といえるのではないか。
本章に登場する人たちは、歴史的人物であるので敬称を省略した。また著者のおふたりは、文壇、論壇のVIPとして知名度が高いので、これも敬称を略した。
(平成20.5.9記)
特2トップへ、
補遺 そのニへ、
補遺へ、
ホームへ





 文芸春秋8月号で「昭和の海軍」が大きく取り上げられた。この記事は管理職のビジネスマンに大反響があったという。柳の下の2匹目のどじょうを狙って、再び帝国海軍が誌面を飾った。帝国海軍にはまだまだ市場価値があるのか。それはともかく、負けた海軍と勝った海軍を比較するのだから、負けた側のわれわれから見るとちっとも面白くない。しかし、斯界の権威者が薀蓄を傾けて、秘話を披露するのでなかなか読みごたえがある。始めて目にするエピソードもあり勉強になった。座談会参加者は次の方々である。
文芸春秋8月号で「昭和の海軍」が大きく取り上げられた。この記事は管理職のビジネスマンに大反響があったという。柳の下の2匹目のどじょうを狙って、再び帝国海軍が誌面を飾った。帝国海軍にはまだまだ市場価値があるのか。それはともかく、負けた海軍と勝った海軍を比較するのだから、負けた側のわれわれから見るとちっとも面白くない。しかし、斯界の権威者が薀蓄を傾けて、秘話を披露するのでなかなか読みごたえがある。始めて目にするエピソードもあり勉強になった。座談会参加者は次の方々である。