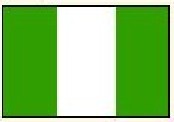平和の時代 その三
はじめに
ボムベイ事務所閉鎖
アンバサダー(インド製乗用車)
私はインドのボムベイで、本社の許可を得て高価な社宅を購入したが、それを十分活用することもなく 昭和45年(1970)3月には事務所を閉鎖し、社宅を売って帰国するよう指示された。インドは当時、国際収支の赤字に悩まされており、また国内産業の保護のため厳重な輸入制限を実施していた。いきおい日本からの雑貨や機械などは全く
というほど入ってこなかった。したがってわが社の定期船の寄港もほとんど期待できない。事務所を開いておく意味がないというのである。かたや産油国であるペルシャ湾岸のイラン、イラクなどは巨額な外貨を持っており日本雑貨の好顧客であった。またその豊富な石油の埋蔵量は、タンカー業を営む川崎汽船にとって目配りをしておく必要のある重要地域であった。そこでわが社は新しく イランの首都、テヘランに事務所を開設し,ボムベイ事務所を閉鎖したのであった。事務所閉鎖については会社関係と私の家族の帰国のためさまざまな問題の処理が必要であった。なかでも金額的に見て大物は社宅と社用車の処分であった。

|
|
アンバサダー MK2型
|
まず
社宅であるが私が買った値段で代理店の社長に譲った。次は自動車である。インドは乗用車の需要が多いにもかかわらず供給がこれに伴っていなかった。乗用車はイギリス系のアンバサダーとイタリア系の何とかというのが国内で生産されていた。アンバサダーは英国のモリスを先祖とする国産車で圧倒的なシェヤーを誇っていた。乗用車の輸入には禁止的な高関税がかかる。転勤のときに持ってくる以外には持ち込む方法はない。国内生産は需要に追いつかずウエイティング・リストに登録してから車が手に入るまでに2、3年はかかるという状況であった。ただし代金をドルで払えば即時引き渡しが可能である。インドは極端な外貨不足で小麦などの食糧以外のあらゆる品物に厳重な輸入制限があった。私はインドに到着して直ぐに運転免許を取り、ドル払いでアンバサダーを申込んだ。それでも手に入れるまでに1ヵ月半はかかった。この車は排気量1650cc、5人乗りの中型乗用車であった。正確な価額は忘れてしまったが8千ドルぐらいではなかったか。 当時1ドルは360円だから290万円弱という今では信じられないほどの高価額である。
業者の店頭で引き取って自宅の駐車場に入れ、エンジンを切り、車外に出てドアをバタンと閉めたら驚いたことにドアの取っ手がポロッともげた。鋳物が粗悪なのである。再び車を運転して業者の店に行った。業者は驚く風もなく、修理には1週間かかるという。車を買ってから半月ぐらいたったときに子供を後部座席に乗せてドライブしていた。座席の窓側天井についているつり革に子供がぶら下がったらこれまたポロッと取れてしまった。業者はあのつり革は飾り物だから触ってはいけないといったものだ。当時アンバサダーの国産化率は90パーセントを超えていた。これはインド政府の自慢の種であったが同時に国産化率の上昇とともに品質が低下するというジレンマがあった。新車の入手がこんな状況なので中古車市場は活況を呈していた。私が1年半ほど乗った車はほぼ買値で売れた。ここで述べたアンバサダーの品質に関する私の経験は、あくまで今から30数年前のものであることをいそいで付け加えておきたい。(上の写真は Phil Seed's Virtual Car Museum から借用した)。
アリタリア航空
私たち家族の帰国の便は昭和45年3月下旬の某日、午前5時半か6時ごろボムベイ空港発羽田行きのアリタリア航空であった。多数の日本人会の皆さんに見送ってもらった。そのさなかにアリタリア航空の女性スタッフとの間にひと悶着が起きた。家族の手荷物重量が制限を超過しているので超過料金を取るというのである。この程度の重量超過は国際旅行の常識として看過すべきものであると主張してインド人女性スタッフとやりあった。私はインド駐在中、数回ペルシャ湾岸諸国に出張した。ボムベイ発デュバイ行きのエコノミークラスの中はペルシャ湾岸に出稼ぎに行くインド人で足の踏み場もない有様であった。彼らは家財道具や身の回りのもの一切をかついで客室に入ってくる。私はそんな実情を知っているだけに、規則をたてにわずかな重量超過を問題にするインド女性にカチンときた。インドのような遅れた国では (現在ではない。今から30年も前の話である) 航空会社に勤めるインド人の社会的ステータスは高い。ましてアリタリアは外国航空会社である。彼女はエリート中のエリートをもって自ら任じているのだ。日本人を見下したような横柄な態度にはらわたが煮えくり返ったが、大勢の見送り人の手前、いつまでも女性スタッフと口論しているわけにもいかない。超過料金何万円かを支払った。今後金輪際アリタリア航空には乗らないと心に誓ったものだ。
後に私はイランの首都テヘラン空港からクエート行きのイラン航空の中型機に乗る機会があった。前部の入口からファーストクラスの乗客、後部の入口からはエコノミークラスの客が乗り込むことになっていた。私は後部の長い列の中でタラップを上る順番を待っている。見るともなく 前部のほうに目をやると、タラップの下のスチュアーデスがこちらを指差しながら険悪な顔をして何ごとか怒鳴っている。前部の列の中のエコノミークラスの客を怒っているのであった。列を間違えた 5、6名の客がこちらにやってくる。私の前に並んでいた白人の客が私に向かって片目をつむってウインクして見せた。当時の発展途上国の飛行場ではよくある光景であった。貧しい国内総生産(GDP)と乏しい文化と情緒の伝統が彼女ら現地人スタッフの粗暴な客扱いの背景にある。
激変する世界情勢
ニクソン・ドクトリン
昭和45年(1970)4月、私は油槽船部の課長として帰国した。翌年の2月にはニクソン米大統領のいわゆるニクソン・ドクトリンが発表された。これによって米国はドルと金の交換を停止した。また日本とドイツに対し為替レートの切り上げを要求した。ここに戦後25年間にわたって維持されてきた1ドルは360円の固定レートが廃止され変動相場制になった。昭和46年末の為替レートは1ドル308円であった。昭和48年(1973)10月には第四次中東戦争が勃発した。この戦争でエジプト、シリアはよく 戦って、勝敗の帰趨もにわかに決めがたい状況になった。ここでアラブ産油国は米国・イスラエルに肩入れする国に対し原油の供給停止を発表して、エジプト、シリアを全面的に応援する。西欧先進国もここにいたって対岸の火災視しておられなくなった。国連を動かして停戦を働きかけ、戦争は勝敗もあいまいなままにわずか3週間足らずで終わる。
これを契機に世界は石油危機いわゆるオイル・ショックに突入する。この年年末には原油価格は1バーレル11.65ドルに高騰した。1960年代以降1バーレル1.8ドルであったものが7倍弱にも値上がりしたので世界経済は甚大な影響を受けることになった。インフレなのである。トイレット・ペーパーや洗剤に買占め騒ぎが起こり世間はパニック状態に陥った。日銀は公定歩合を9%に引き上げ、福田蔵相は狂乱物価と命名した。私は昭和49年2月に中東・アフリカへの出張の途中、ロンドンに寄ったが川崎汽船の駐在員事務所ではトイレット・ペーパーを何処で買えるかという話題が出ていた。
産油国詣で
このような社会情勢、経済情勢のもと、わが国の石油会社は長期的な原油の確保に奔走した。石油会社幹部による産油国詣でが始まった。この頃ではすでに各産油国は欧米系メジャー石油会社の支配を脱して、完全自立を果たしていた。また一方わが国では新規油田の開発を目指して石油開発会社が乱立して、石油開発公団がこれを支援した。わが国の船会社もこの石油会社の動きに巻き込まれ、何とか原油の獲得に一枚加わって、それをベースにタンカー船隊の拡充を図ろうとする。わが川崎汽船は原油の獲得は石油会社や石油開発会社の仕事であるとしてこの競争に加わることはせず、自立を果たした産油国を動かしてタンカーの合弁会社を作るべく動き出した。 たまたま南米のエクアドルでタンカー合弁会社の設立が成功したので、この経験をもとにこの構想を推進することになった。
このため私は昭和48年(1973)から昭和50年(1975)にかけて9回も中近東、アフリカに出張した。イラク、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ナイジェリアなど見込みのありそうな産油国の石油大臣や担当官に会って、タンカー合弁会社構想の概要を説明して勧誘した。彼らはしかし、はじめての原油の売手市場の中で、手に入れた原油の処分権の行使や原油価格の改定の交渉に頭が一杯で、タンカーまでは手が回らないという風であった。 この頃産油国の石油相の事務所には諸国の石油会社、船会社の連中が殺到し、待合室はそれこそ門前市(イチ)をなす有様であった。現地のホテルや石油相の待合室で、わが国の石油会社、船会社の友人と鉢合わせするのも珍しいことではなかった。私はレバノンの首都ベイルートを基地にしてペルシャ湾岸の産油国通いをした。
ベイルートでは仕事柄、豪華なフェニキヤ・ホテルに泊まった。ここでたびたびブローカーや産油国の石油省の要人に会った。当時すでにレバノンでは地方において内戦の気配があったが首都ベイルートは全くの平和境であった。砂漠の中の産油国の苛酷な環境からここベイルートに帰ってくると緑は多く、ホテルやレストランのサービスも先進国のそれと遜色はなく、世界三大カジノの一つカジノ・ド・レバンも盛況で、命を洗われるような安堵の気持ちに浸れた。 ベイルートが 「中東の真珠」 といわれるのも納得できた。
それもしかし昭和50年(1975)の初めまでで、その年半ばには戦火はついに首都に及んだ。各宗派が民兵を組織して、地盤の争奪をするようになり、それぞれホテルを占拠して銃撃戦、砲撃戦を展開した。湾内を望んで高地に屹立していたフェニキア・ホテルも例外ではない。某宗派が占拠して、外壁は弾痕で穴だらけ、客室は家を失った信徒の収容所となり、かつては豪華だったロビーを泥靴の民兵が腰にピストルをぶら下げて、うろついていると新聞は報じた。そのころ何回かロンドンからミドルイースト・エアラインでサウジアラビアの首都リアドに飛んだ。飛行機は給油のためベイルート空港に立ち寄らねばならない。乗降客は皆無だ。薄暮であったが、離着陸の際、低空から見る市街には人影もない。ベイルート銀座といわれたハムラ通りには街灯が赤々とついているだけで無人、まさに死の街というたたずまいであった。このレバノン内戦は1990年(平成2年)まで続くのである。
昭和の終わり
昭和54年(1979)6月には原油価格は1バーレル18ドルに引き上げられ第二次オイル・ショックが始まる。金融引き締めは強化され不況は深化する。この年、ルーマニアの首都ブカレストで世界石油会議が開かれた。私は当時、日本タンカー協会会長であったわが社の若松常務のお供でこれに参加した。とくに協会として発表する議題があるわけでもなく、講演を聞いたり、映画を見たりと気楽な旅であった。社会主義体制下のルーマニアでは物不足であった。大きなデパートにも商品は少なく、土産に買って帰りたいようなものは何もなかった。陳列棚にはほこりが溜まっていた。帰途、ギリシャのアテネに寄り、ピレウス港でタンカー係船の現場を見学した。世界的なタンカー・オーナーであるギリシャ船主は、持ち船の用船先を見つけることができず、ペロポネソス半島とギリシャ本土の間の細長い湾に多数のスーパータンカーを錨泊させていた。
昭和56年(1981)10月には原油価格はついに1バーレル34ドルに高騰する。このときの為替レートは1ドル、240円をつけていた。昭和60年(1985)9月には、先進5カ国の蔵相、中央銀行総裁がニューヨークのプラザ・ホテルに会して、いわゆるプラザ合意を発表してドル安を容認することになった。この結果、円は急騰し2年後には1ドル120円までになった。世は円高不況に突入する。しかしこの円高も悪いことばかりではない。円高のため輸入原材料価格は激落し、これが製品価格の低下をもたらして内需を刺激した。昭和62年7月には経企庁は円高不況の終了を宣言するのである。
昭和62年(1987)半ば頃から体調の不良を伝えられていた昭和天皇は昭和64年(1989)1月7日、薨去された。病名は十二指腸乳頭周囲腫瘍(腺癌)であった.私は昭和58年(1983)から神戸船主の太洋海運に役員として移っていた。勤務場所は東京支店であったが、月に1回の役員会には本社のある神戸に出張した。昭和64年7月、ここをやめ37年間の船会社生活に終止符を打って悠々自適の身になった。最後に原油価格の現況を付記しておきたい。本日(平成17年8月9日)の夕刊は8月8日のニューヨーク原油市場において1バーレルが64.27ドルと取引所開所以来の最高値をつけたと報じた。ちなみに、平成20年(1908)7月11日には原油価額は1バーレル147.27ドルの高値をつけた。しかし、これを境にして価額は次第に降下に転ずるのである。
FLOPEC(フロペック)

合弁タンカー会社
1960年(昭和35年)代になると南米諸国の太平洋岸に豊富な石油の埋蔵が報じられるようになった。1970年(昭和45年)代に入ると実際にこれらの油田から採掘が始まった。ペルー、次いでエクアドルである。エクアドルは南米の太平洋岸、ペルーとコロンビアにはさまれた赤道直下の小国である。
エクアドル政府は自国消費の後の余剰原油を輸出しようとする。それにはタンカーが必要である。タンカーを運航するためにタンカー会社が必要だ。これはエクアドルとしては有史以来のことで自力ではどうにもならない。そこで世界の海運業者の中から信頼できる相手を選び合弁タンカー会社を作って、タンカー運航のノウハウを得ようとする。
1972年(昭和47年)4月、エクアドル政府はこの合弁会社の相手方を公募するのである。数社の応募があったが審査の過程で最後まで残ったのはわが社とドイツ籍船会社の2社であった。もともと南米へは第二次大戦前からドイツと日本が経済的な触手を伸ばしていた。このたびの合弁船会社の選択に、日独の2社が残ったのは決して偶然ではない。わが社もこのドイツの船会社も戦前から南米定期航路を経営していたのである。
そのような状況のもとにあった某日、このドイツの船会社から、10万ドル呉れれば競争を降りるがどうかと打診があった。拒否する。結局、わが社が合弁相手に選ばれた。
(右の地図は帝国書院 の『エッセンシャル アトラス』 から借用した)。
1972年7月、当時油槽船部の課長であった私は合弁契約交渉のためエクアドルに派遣された。新しい合弁タンカー会社の管轄は首都キトーの国防省海軍部であった。エクアドルでは海上輸送は官民を問わず海軍の所管であった。海軍部が選んだ私の交渉相手はレオン中佐とペネフェレラ中佐の2人であった。先ず合弁契約の基本的な事項、たとえば資本金、出資比率、役員、わが方から派遣するスタッフの人数とそれぞれの役割、新造船計画などで大体の合意の線を出しておいて、相手方の提出した合弁契約書案の逐条審議に入る。英訳された合弁契約書案はそれほど大部のものではなかったが、交渉は予想以上に時間がかかった。私は一流ホテルとされるホテル・コロンに泊まって毎日、国防省まで通った。
交渉はウィークデイだけなので土曜、日曜をもてあました。首都キトーは海抜2800メートルの高地にあり、空気の薄いことが肌に感じられた。坂道を登ってそのてっぺんで気分が悪くなり、暫く しゃがんで回復するのを待つということも時々あった。アルコールの回りが速く、普通のペースで飲むと直ぐに気持ちが悪くなった。商社などでは駐在員と家族に毎年1ヶ月の高地休暇
(海抜ゼロ・メーターの場所での休養) を与えるところもあった。キトー郊外に赤道標がある。これは観光スポットになっている。赤道を人が跨げる場所は地球上に、此処とアフリカのどこやらの2箇所しかないということであった。何分此処はマニヤーナ(Philosophy of mañana、明日主義、mañana はスペイン語で明日の意)
の世界である。明日やってもいいことを今日やるべきではない、という社会なのだ。われわれはどうかというと、今日出来ることを明日に延ばしてはいけないと言われながら育ってきた。交渉の進捗度の評価が彼と我とでは全く異なるのであった。
契約の調印を終わってエクアドルを出たのは丁度入国してから2ヶ月目であった。
表題のFLOPECはFlota Petrolera Ecuatoriana の 略語である。日本語に訳すとエクアドル国営タンカー会社となる。
合弁契約交渉
レオン中佐

|
|
エクアドル国旗
|
|
真ん中の模様は国章
|
私の交渉相手のレオン中佐は私よりは2、3歳の年長、快活、率直で誰とでも友達になれるような開けっぴろげなところがあった。私はコマンダンテ・レオン と呼びかけて直ぐに親しくなった。
かたやペネフェレラ中佐は私よりも若干若かったが沈着無口で、冗談など口にしたこともなく、契約条項の一点、一画もゆるがせにしない風があった。エクアドル海軍はこの対照的な性格の2人を組み合わせて、外国人との始めての商談に臨むことにしたようであった。契約交渉のやりかたもエクアドル海軍方式というか独特なものであった。交渉員の両中佐はわれわれの間で合意した条項を海軍に持ちかえって全体会議に付する。しかしそれがすんなり海軍部内で認められることは稀で、あそこを直せ、此処を直せといってくる。議論はまた最初からやり直しである。こうして修正提案のキャッチボールをしていると、一つの条項の確定に何週間もかかることがある。一旦合意した条項を日がたってから又変えてくれといってくることもしばしばであった。私は油槽船部の課長として東京に残してきた懸案事項もあるし、何時までも此処で先の見えない交渉に張り付いているわけにはいかない。次第にあせり始めた。

|
|
レオン中佐
|
交渉開始から1ヵ月半もたち、漸く妥結の最終案が出来上がろうとしていたときに、先任交渉員のレオン中佐が突然、合弁会社のゼネラル・マネージャーはエクアドル国籍でなければ駄目だといいだした。法律に明文の規定があるというのである。すでにわが社では合弁会社のゼネラル・マネージャーが内定しており一両日中にも発令されるという段階であった。
私は怒り心頭に発した。こういう基本的な事項は交渉の前に確認しておかなければならないことだ。もとより私はエクアドルの国内法には何の知識もない。そのために弁護士を雇っているのだから、今までに弁護士から何らかの話があるべきであった。ゼネラル・マネージャーの職務権限についてはすでに何日も議論して決まったことである。この議論はゼネラル・マネージャーを川崎汽船側から出すことが前提であった。
だまし討ちのように今頃そんなことを言われても、「はい、そうですか」 と承知するわけにはいかない。私は明日にでも東京に帰って状況を本社に報告する。タンカー会社の経営に何の経験、知識のないエクアドル人のゼネラル・マネージャーの下にわが社から人を出すということは考えられない。契約交渉をやり直すことになるのでわが社から新しい交渉人が派遣されるだろう。
レオン中佐は私の反応が予想外に厳しいものであったらしく 困惑のていであった。というのは私の弁護士はレオン中佐の親類で、同中佐の推薦で雇ったものであった。もう 60歳を過ぎた老人の弁護士は、エクアドルには沢山の法律があるので弁護士といえどもすべてに通暁しているわけにはいかないとスペイン語で言い訳をした。この弁護士は英語が出来ないのであった。
われわれの交渉中、ただ黙って座っているだけであった。私が当の契約の相手方の推薦する弁護士を雇うという非常識をあえてしたのは、
この交渉をスムースに進めたかったからであった。レオン中佐は海軍部内でもう少し検討したいので、川崎汽船の本社にはこのことを報告しないでしばらく余裕をくれという。
1週間ほども海軍部内ですったもんだやっていた。結局、この合弁タンカー会社はエクアドルとしては有史以来のことで、大統領令か何かで特別扱いとすることが決まった。このゼネラル・マネージャーの国籍問題は降って沸いたようなトラブルであったが、しかしこれを契機に交渉はとんとんと進捗し、交渉開始から2ヶ月目に漸く妥結した。合弁契約の調印式は国防省の会議室で海軍長官はじめ海軍部の高官列席のもと、厳かに行われた。わが社からは私と前島ジェネラル・マネジャーが参列した。私は調印式が終わるやその日の正午の飛行機でニューヨークに向かった。
反米感情
合弁契約交渉の顔合わせの初日、雑談中、私が米国のことをアメリカと言ったところ、レオン中佐が異議を申し立てた。レオン 「アメリカというのは此処のことだ。此処エクアドルがアメリカだ。あなたが言うアメリカはどこをさすのか」。私 「もちろんアメリカ合衆国のことだ」。レオン 「その場合は合衆国(United States) と言ってくれ」。 当時エクアドル政府はガラパゴス諸島の周辺の漁場をめぐって米国政府と争っていた。ガラパゴス諸島周辺の海域は南氷洋に発するフンボルト寒流とマリアナ諸島付近から北上し、日本南岸を経て太平洋を東進する黒潮の交流する場所であった。まぐろ、かつお、いわしなどの豊かな漁場なのである。
エクアドルは第二次大戦後早くから領土の周辺200海里以内を自国領海とすると主張していた。これに対し米国は12海里領海説を採って譲らなかった。第二次大戦中、エクアドルは自国領のガラパゴス諸島をアメリカ海軍の自由使用にゆだねていた。そのとき以来米国漁民はこの諸島水域をあたかも自国領海であるかのように自由に出入りしていたのであった。私がエクアドルに滞在しているときにも、米国漁船を領海侵犯で拿捕したという新聞記事が出ていた。大体、南米諸国はその考え方の基調において反米であった。第五代モンロー大統領 (在任期間:1817~1825) の昔から、北米・ラテンアメリカをひっく るめて、あたかも自国の庭であるかのごとく 振舞う米国に対し、憤りの気持ちを持っていた。また南米諸国は自国の経済が米国経済圏に囲い込まれ、巨大な米国資本に牛耳られていることも癪の種であった。
交渉の準備
エクアドル政府の公開入札でわが社が落札してからというもの、私は契約交渉の準備に忙殺された。先ずスペイン語を習うため大阪ビルのスペイン語講座に通った。1週間、2回、午後6時からの講義には14、5名の女性に混じって私はただ一人の男性であった。女性のなかには、なぜスペイン語初級講座に来ているのかわからないような、流暢なスペイン語をしゃべる人もいた。全くの初心者の私は毎回、テキストの訳読に大汗をかいた。
次に私はいろいろな本や資料を読んで南米に関する知識の集積につとめた。先ずジョン・ガンサー (1901~1970)の 『南米の内幕』(Inside South America by John Gunther) を読んだ。なかに軍閥 (Military Junta、ミリタリー・フンタ)という言葉が頻出する。また20世紀に入ってから南米各国の政権の移動は平均2年半という。ここに政権の移動とはたとえば森首相が小泉さんに政権を移譲するといったものではない。革命なのだ。陸軍の戦車が大統領官邸を包囲し、空には空軍の戦闘機が飛び交ううち、大統領は空港に待機する特別機で南米の何処かの国に亡命する。こんなことが2年半に1回の割で繰り返されているというのである。とんでもない国と商売をすることになったと改めて身の引き締まる思いであった。
合弁会社のパートナーとなることは一回限りの商品の売買と違って、資金と人を長期にわたってその国に貼り付けることになる。後になって知るのであるが南米諸国の革命というのは政権交代の一つの方法であった。民主主義国では選挙によって大統領や首相が選ばれる。南米諸国では首長の選出を革命によるわけだ。だから革命といっても死者の出ることは極めて稀なのだ。政権交代の手続きが民主主義国とは違うというだけのことのようであった。Howell Davies の 『The South American Handbook』 1972年版も読んだ。この本によるとエクアドルの人口は6,090,000である。エクアドル政府のインターネットの公式サイトによると現在の人口は12,562,496である。この30年の間に人口は倍増したことになる。
人口の内訳はインディアン39%、メスティーソ41%、白人10%、黒人および東洋人10%。この人口の構成比率は南米各国ほとんど似たようなものである。ちなみにメスティーソとはインディアンと白人の混血をいう。スペイン、ポルトガルは大航海時代以来、男性が単独で新大陸の占領地に進出した。これがイギリスの植民地と違って混血が増える理由であった。余談であるがガンサーの最初の内幕もの 『ヨーロッパの内幕』 (Inside Europe Today) は欧米の読書界に迎えられて爆発的なベストセラーとなった。以後彼の著す内幕ものはすべてベストセラーとなり、彼は名声と富を獲得した。彼は1930年代、世界でもっとも著名なアメリカ人3人のうちの1人に数えられていた。他の2人はルーズベルト大統領と大西洋無着陸横断飛行で有名なリンドバークである。また一説によれば、上に挙げた 『ヨーロッパの内幕』 でナチスをこき下ろしたためヒトラーに睨まれて、ゲシュタボ (ドイツ秘密警察)の暗殺者リストに登録されていたという。
マリア・ルス号事件

|
|
大江 卓
|
明治5年(1872)6月、ペルー籍帆船マリア・ルス号はマカオから支那人苦力(クーリー)230名を乗せて南米に向かう途中横浜に寄航した。横浜停泊中、何人かの苦力が船内の虐待に耐えかねて海に飛び込み、英国軍艦に泳ぎ着いて窮状を訴えた。彼らは奴隷として南米に売られていく 途中であった。知らせを受けた神奈川県参事大江卓は人身売買の現行犯として船長を逮捕し裁判にかける一方、支那人苦力全員を解放して清国公使に引き渡した。これに対しペルー国はわが国を相手として損害賠償の裁判を起こした。明治8年、露都モスコーで行われた国際裁判ではわが国の処置が妥当と認められて勝訴した。この事件は揺籃期のわが国司法、外交界をゆるがした大事件であった。
ここで注目すべきは明治の初年、沢山の支那の貧民が奴隷として南米に売られていったことである。上海、アモイなどの港から南米への奴隷航路が存在していた。これらの船は通常わが国に寄港することなく太平洋を横断するのであるが、マリア・ルス号は暴風雨で船体が破損したので修理のために横浜に寄航したのであった。たまたまこの事件が報道されてはじめて、奴隷航路の存在が白日の下にさらされたのであった。奴隷として南米に売られた支那人苦力は鉱山労働や鉄道建設などの土木工事に酷使された。爾来、南米の諸国では支那人に対する人種偏見が存在するようになった。支那人は奴隷身分の劣等人種というのである。
私もキトーの町を歩いていて現地のインディアンに 「チノ!」 と罵声をあびせられたことが何度かあった。チノは chino で支那人の蔑称である。それも子供ではなく、成人のインディアンがいうのである。彼らには支那人も日本人も区別はつかない。或る日、現地の女性と結婚して日本の商社に勤めている20代後半の日本人と連れ立ってキトーの繁華街を歩いていた。2、3人のグループのインディアンの中の一人がすれ違いざまわれわれに向かって 「チノ!」 と叫びかけた。私の同伴者は直ぐに振り返って 「アフリカーナ!」 と叫び返した。アフリカーナも人種偏見にもとづく差別用語として使っているのである。上に挙げたガンサーは 『南米の内幕』 のエクアドルの項で Negro-mulatto (ニグロ・ムラットウ) が全人口の10%を占めるという。ニグロ・ムラットウとは黒人と白人の混血人種をいう。南米はアフリカの黒人も奴隷として輸入していたのである。
No problem (ノー プロブレム、問題はない)
ホテル滞在も長くなると従業員とも親しくなる。ホテルの売店の40歳ぐらいのおかみさんと雑談を交わすようになった。或る日、雑談中にこのおかみさんが、私は日本に派遣されているエクアドル大使と友達である。あなたが帰国するときに大使に small present (小さな贈り物) を持って行ってく れないかという。私は日本を発つときに麻布のマンションの一階にある大使館にこの大使を表敬訪問してきた。単なる儀礼的なものであったが満更知らない仲ではない。旅行かばんに入るぐらいの小さいものなら持っていってあげようといって、両手の平を合わせて大きさは手の平サイズのものであることを示した。
1週間ぐらいたってから売店に行くと、荷物が出来たからお願いしますという。傍らには縦1メートル、横5、60センチ、幅は10センチもあろうかというハトロン紙の包みが厳重に紐をかけて置いてあるではないか。私は直ぐにこれはスモール・プレゼントではないといって持っていく のを断った。彼女は持ちやすいように取っ手をつけたとか軽い木を選んだとかいろいろと言い訳をいう。私がこんな重たくて、でかいものを持って旅行するのが如何に大変であるかを説明していたところ、彼女はいきなり両手を開く大袈裟なしぐさをして No problem .(ノー プロブレム)と叫んだ。大したことはないというのである。私は頭にきて、大したことであるかないかは私が判断して決めることだ。あなたがかれこれいう資格はない。約束違反のこんな大きな荷物を預かることは出来ないと峻拒した。彼女は私の拒否の決意が固いのを知ると、しぶしぶ鋏で荷物の包装を破って中身を見せてくれた。それは立派な木彫りのエクアドルの国章であった。エクアドルの国章というのは上に掲げたエクアドル国旗の中の紋章のことである。大使の事務室の机の脇に立てて置くものだという。
ノー プロブレムという言葉は海外出張中時々聞いた。当時海外に出て行く日本人にはお人よしが多かったのかもしれない。彼らは英語が下手なことの埋め合わせに、少々無理な頼みも聞く傾向があったのだろう。ノー プロブレムは頼みの履行が難しいという説明の途中、相手から発せられる言葉であった。最初この言葉を聴いたときには驚くやら腹を立てるやらしたが、おしまいにはまたかと思うだけで特別の感慨もなくなった。
あれはボムベイ駐在員としてボムベイに到着して2週間位たったときであったろうか。事務所で書類を読んでいるところへ、真っ白いインド服を着た紳士が入ってきた。自分は代理店の社長の顧問であると自己紹介をした。私は代理店の一室を借りて川崎汽船のボムベイ事務所としていたのである。旅行はどうであったかなど通り一遍の世間話をした後、彼が話し出したのは次のようなことであった。
半年ほど前、日本人の女友達から手紙が来て、日本で発行されている何とかという宗教雑誌が鈴木大拙の特集号を出したという。自分は鈴木大拙に関心を持っているので是非この雑誌を買いたい。代金は印度ルピーで支払うので手に入れてくれ。私 「あなたは仏教徒か」。彼 「私はヒンズー教徒である」。私 「ヒンズー教徒のあなたがどうして仏教の雑誌を求めるのか」。彼 「鈴木大拙に関心がある」。私 「あなたは日本語が読めるのか」。彼 「日本語は読めないが記念に欲しいのだ」。私は先ず初対面の日本人に向かって、読めもしない雑誌を取り寄せてくれというこのインド人の厚かましさにあきれた。この雑誌は日本人がその名前を聞けば誰でも知っているようなポピュラーなものではない。しかも半年以上も昔のバックナンバーではないか。雑誌名を確かめ、出版社名を確かめ、しかも在庫があるかないかを確かめるだけで普通の日本人には厄介な仕事なのだ。私がこの雑誌を手に入れようとしたら、妻を通してやるよりほかはない。小学生の2人の子供の世話に追われている妻に、この雑誌を手に入れてボムベイの私のもとに送らせることがどんなにわずらわしい仕事であるかは考えるまでもなく 明らかなのだ。
私はそのことを訥々とした英語で話し出したら、件(クダン)の紳士は皆まで言わせず、大きな声で No problem.(問題はない) と叫んだ。私は何を言われたかわからず、エッ と聞き返した。再び No problem.といって今度はご丁寧に It’s easy .(簡単なことだ) と付け加えた。彼が何を言っているのかわかって私の顔色は変わっただろう。何とか怒りの言葉を投げつけようと思うのだが英語がすらすらと出てこない。とにかく 私はお断りする。もしどうしても欲しいのであればあなたの日本に住む女友達に頼めといって話を打ち切った。彼は両手を広げて大袈裟な絶望のしぐさをしながら部屋を出て行った。私はそのあと2、3日不愉快な思いで過ごした。
Salsa Inglés (サルサ・イングレ、英国風ソース)
外国旅行のたびに私の世代の日本人が困るのは毎日の食事である。今ではニューヨーク、ロンドンなど世界の主要都市には何百軒も日本料理屋があるというが昭和40年代に中近東、南米、アジアの辺鄙なところを旅行すると日本料理屋のあるところは稀であった。中国料理屋があれば御(オン)の字であった。 適当な値段で口に合う食べ物にありつくのは難しかった。
私は先にボムベイ駐在員としてインドに2年間住んだ。最初の下宿では不味いインド料理に閉口した。家族が来てからは日本料理のできるコックを雇って、時々は刺身や天麩羅なども作らせ、日本と変わらない食生活をした。食材が安いだけむしろ日本以上の食生活であった。朝食は家族はパン食であったが私はオートミールに卵料理を常食にした。食後の果物は毎食後マンゴーかパパイヤであった。それに私だけは起きぬけに椰子のジュースを一個ぶん飲んだ。椰子の中身を1ダースほど冷蔵庫に入れて冷やしておいて、殻に穴を開けてこのジュースをコップに移して飲むのである。これがまた驚くほど安いのだ。一個の椰子の実が日本で昔、毎朝配達される牛乳1瓶ほどの値段であった。たしか椰子の実の固い殻に穴をあける特別の器具もあったな。家族は不味いといって誰も飲まない。私はインドにいる間、毎日これを欠かしたことはなかった。この椰子の実のなかの生臭いジュースは牛乳に勝る完全食品であるといわれていた。
私は会社を代表して契約交渉に来ているのだからエクアドルの首都キトーでは一流ホテルに泊まった。ここでもしかしホテルのメイン・ダイニングルームで出される料理はろくなものではなかった。ステーキのミディアムを頼んでも、なかなか噛み切れない固い、しかも味のない肉が出てくる。魚料理といえば粗悪な油で揚げた得体の知れない魚が出てくる。宗主国のスペイン本国にはパエリアなどという日本人好みのお米料理があるのにここにはそんなものはない。立派なのは部屋の装飾とメニュー・ブックだけである。私は早々にメイン・ダイニングルームの食事をあきらめ、カッフェテリアで食べることにした。朝食はオレンジ・ジュース、トースト・パンに卵料理、コーヒーと毎日変わらない。昼食と夕食にはボイルド・ライスの上にポーチド・エッグを2個載せてフォークでぐじゃぐじゃに砕き、これにソースをかけて食べようと思った。エクアドルのような熱帯ではとにかく あっさりとした食べ物が欲しいのだ。
そこでウエイターにソースを注文するとトマト・ソースを持ってくる。ノーというと今度は中華料理の真っ黒い奴を持ってくる。またノー、またノーと何時までたっても私が日本で肉料理にかけていたさらさらとして淡白な風味のソースが出てこない。そのうちに私は日本のソースの壜のラベルにウースター・ソースと書いてあったことに気が付いた。「ウースター・ソース!」というとウエイターは怪訝な顔をするばかりだ。またそのうちに私はウースターというのが英国のソースの名産地の地名であると聞いたことがあるのを思い出した。「イングリッシュ・ソース!」と言ってみた。ウエイターは両手を大きく広げて「オー!サルサ・イングレ!」と叫んだ。最初にソースを注文してからここまで来るのに15分ぐらいかかったであろうか。サルサは sauce,イングレは English である。やっと目的に到達したのであった。しかしカッフェテリアにはサルサ・イングレの現物がないので、ウエイターは3階のメイン・ダイニングルームまでとりに行った。壜の蓋をとって懐かしいソースの匂いを嗅いだ。ボイルド・ライスとポーチド・エッグの混ぜご飯にこれをかけて食べた。ソースの味は日本のものと多少違っていたが、この混ぜご飯は私が事前に想定した味と大差のないものであった。私はその後この混ぜご飯を常食にした。自分で食べただけでなく、日本からの出張者に勧めた。これはオカノ・スペシアルとして好評を博した。
私はその後、昭和50年代にしばしば中近東の国々に出張した。はじめてイラクの首都バクダッドに行ったときにはエアーポート・ホテルに泊まった。最初の日の夕食に出たステーキは仁王様の草鞋ほどもあろうかという特大の肉であった。のこぎりの刃のついたナイフでごしごし引いてもなかなか切れない。次の日の夕食には魚料理にした。ティグリス川で取れた大きな淡水魚の切り身を油で揚げたものであった。皿の上に小山のように盛り上がった茶褐色のその姿を見ただけで食欲を失った。私は直ぐボイルドライス+2ポーチドエッグ+ソースのオカノ・スペシアルに変えた。ところがなかなか目指す日本風のソースが出てこない。ソースと注文して出てくるのは何処の国のレストランでもトマト・ソースであった。次に出てくるのは中華風のソースである。ここは英国文化圏だからというので「イングリッシュ・ソース!」といっても、似ても似つかないものを持ってくる。最後の切り札として「ウースター・ソース!」と言ってみた。
ウエイターは両手を広げる大袈裟な驚きのしぐさをしながら「オー!ウースターシャー・ソース!」といったものだ。ウースターシャー (Worcestershire) は西イングランドの州の名前でソースの名産地である。物心つかない子供のときに舌の味覚中枢が記憶した味は一生涯消えない。私のウースター・ソースはまさにこれで、中年になっての外国旅行中私の命を支えてくれた。

|
|
長女15歳の誕生日、自宅にて
|
話は全く違うが私の孫はオーストラリアに住んでいる。英国人とわが娘との混血児である。長女は17歳、今年ハイスクールを卒業する。長男は15歳、ハイスクール在学中、次男は 13歳、小学生である。彼らが学校に上がるまでは毎年、我が家に来て1ヶ月ぐらい滞在した。幼児のときから日本食に馴染んだ彼らは日本の食べ物なら何でも大好きである。刺身、天麩羅、寿司、うどん、蕎麦など何でも食べる。お寿司の納豆巻などを買ってくると、3人が争って食べる。納豆はオーストラリアのスーパーでも売っているが不味い上に値段が高い。私は瀬戸内海沿岸で生まれ育ったので、納豆をはじめて食べたのは22、3歳、東京に出てきたときであった。何というけったいな食べ物かと驚いたが、すぐに好物になった。考えてみれば生まれてこの方、醤油の味、味噌汁の味で成長したのである。納豆は大豆のアミノ酸の味なので身体が直ぐに受容するのであろう。
FLOPEC(フロペック)の現在

|
|
FLOPECのファンネルマーク
|
FLOPECは1973年(昭和48年)1月、エクアドル海軍55%、川崎汽船45%の出資比率の合弁会社として発足した。1978年(昭和53年)には合弁契約を解消して技術援助契約に切り替えた。エクアドル側がタンカー会社経営のノウハウを得るにつれて会社形態を変えていき、1982年(昭和57年)には完全に独立の船会社となった。今では従業員400人、タンカー7隻30万トンを保有する南米きっての船会社に成長している。同社の公式サイトによると現在船齢20年を超える小型タンカー3隻を売却交渉中という。左図はFLOPECの社船が煙突に描いている社章である。
外国出張

「平和の時代 その三」は年代的にいえば昭和45年(1970)から昭和64年(1989)までを対象にしている。ただし中近東の産油国を中心とする外国出張についてはこの章にまとめた。すなはち昭和44年、昭和45年、私のボムベイ時代のペルシャ湾方面への出張もこの章に入れた。右の地図はGEORGE PHILIP の MODERN HOME ATLAS から借用した。一部の地名が現地綴りになっている。
イラク
バスラ出張

|
|
イラク国旗
|
私がボムベイ駐在中の昭和44年(1969)3月はじめ、本社から至急イラクに出張するようテレックスの指示が入った。イラクでは前年(1968)7月、戦後何度目かの革命がおきて、バース党が政権の座についた。本社からのテレックスは次のようなものであった。
新聞報道ではイラク国内がごたごたしているようである。今年2月に入って国内の混乱がますます大きくなり、2月末にいたって代理店との通信が途絶えた。ペルシャ湾にはわが社の定期船が1隻、バスラを目指して航海中、別にタンカー1隻がイラク南部のファオに向かって航海中である。大至急バスラに飛んで代理店と交渉してこの2隻の安全とクイック・デスパッチをはかり、あわせて状況を報告せよというのであった。クイック・デスパッチは quick despatch と書く。早期荷役、早期出港を意味する海運用語である。コスト高の大型船は1日滞船すれば数百万円のロスが発生する。積荷港、揚げ荷港での荷役を素早く済ませ、運航船舶の回転を如何に早くするかに船会社の収益がかかっている。
旅行会社のトーマス・クックに航空便の予約に行って次のようなことがわかった。外国人がインドを出国して外国で用務を果たし、再びインドに入国するには次のような手続きが必要である。先ず、インド中央銀行で所得税完納証明書を発行してもらう。次に所轄の警察署で無犯罪証明書を入手する。次にイミグレーションオフィスで再入国ビザを発行してもらう。それから相手国総領事館で入国ビザを貰う。バスラに行く場合はクエートから車になるのでイラクの入国ビザのほか、クエートへの入国、再入国ビザがいる。すべての手続きが終わってから航空便の予約に来いというのである。
中央銀行の窓口は蜿蜒長蛇の列である。1時間以上かけてようやく窓口に辿り着くと、書式が不揃いなので書き直して来いという。書き直してまた列の後ろに並ぶ。警察に行けば窓口は黒山の人だかりで列さえもない。インドの役所で証明書を貰うのは体力勝負なのだ。これらの手続きにはパスポートが必要なので、同時並行的に処理することができない。
こうして必要書類を整えて、ロンドン行きのインド航空便に乗ったのは本社の指令が来てから一週間以上もたったときであった。
エデンの園

|

|
|
エデンの園
|
説明文
|
クエート空港からイラク国境まで砂漠の中をタクシーで走ること2時間半、国境で出入国手続きを済ませてからイラクのタクシーに乗り換え、バスラまで同じく砂漠の中を走ること1時間、漸く代理店に着いた。驚いたことに代理店は国営化されているのであった。それまでいた社員は皆くびになって、素人がやっているようであった。さてこそ東京本社とのコミュニケーションもなかったのだ。あなたの会社の船は今埠頭で荷役中という。船長から散々苦労話を聞かされた。直ぐに代理店にとって返し、一部始終を本社にテレックスする。翌日本社から私宛にテレックスが届く。それによると代理店から本船の到着電報が来たので荷役の見通しや出港予定、社会情勢など聞いてやったがなしのつぶてで心配していたという。私の出張目的はとりあえず達成されたのだ。入港していた本船も揚げ荷役を終了して2日後には出港していった。
代理店の担当者と雑談中、バスラでも2、3日前に旧政権の幹部が公園で公開処刑されたという。死体がまだあるかもしれないから見に行くかという。直ぐにお断りして、バスラ近郊の名所古跡を見たいといったところ、運転手つきの車を出してくれた。方々連れ回されたが今でも覚えているのは 「エデンの園」 だけである。バスラはシャッタルアラブ川 (Shutt al Arab) 右岸の港である。トルコ山地に源を発するチグリス川、ユーフラテス川はバスラ北方において合流してシャッタルアラブ川になってペルシャ湾にそそぐ。この川の左岸にはイランの港コーラムシャがある。ペルシャ湾航路の定期船はペルシャ湾ではこの2港が定期寄航地ある。それはともかく車はこの大河のほとりのナツメヤシの畑に入っていく。アダムとイブの等身大の銅像がある。運転手はここが禁断の木の実の伝説の場所、「エデンの園」 だという。私は運転手より先に車に戻ってふとダッシュボードを見るとなんと小型のピストルがある。その後数年して私はベイルートにたびたび出張した。ここでもタクシーに乗って時々ダッシュボードにピストルがあるのを目にした。武器の所持を禁止されている日本人にとっては何となく不安で違和感があった。上掲の写真右の「説明文」の意味は大略次のとおりである。
”今から4千年前、われらが父祖アダムは、チグリス川とユーフラテス川の合流するこの聖地に、この聖木を植えた。すなはちこれはエデンの園を象徴するものである。”
イラク革命
イラクはもともと第一次世界大戦後、イギリスが作った人工国家であった。イギリスはメッカ地方の有力部族の首長を連れてきてイラクの国王に据えた。当然のことながらこの地方にもともといた部族たちとの間に親近感はない。新国王はイギリスの武力を後ろ盾にして国を統治していたのである。ところが昭和31年(1956)7月、エジプトのナセル大統領は突然、スエズ運河の国有化を宣言する。運河の所有者である英仏は同年8月、イスラエルとともにエジプトを攻撃してここにスエズ戦争が勃発する。戦闘は英仏軍の優位に進んだがソ連と米国がこれに介入、11月に停戦が成立する。スエズ運河は完全にエジプトのものになったのである。イギリスはスエズ運河を失うとともにアラビア半島における権威も失墜する。このような国際情勢の下、イラクでは昭和33年(1958)に左派軍人による軍事クーデターが起こって国王一家は革命軍に暗殺される。昭和38年(1963)2月、民族主義者将校団によるクーデターでこの革命政権は転覆したが、新政権もまたこの年11月には反対派に倒される。この反対派政権も昭和43年(1968)7月、軍部と提携したバース党によって政権を奪われる。目まぐるしいクーデターの連続なのである。今回の海外代理店国有化はこのクーデターの結果であった。余談であるがサダム・フセインはこの新政権のバース党内で次第に実力をつけていく。昭和54年(1979)7月、彼は前任者を追ってイラク大統領となり、今回の対米英戦争で失脚するまでイラクの独裁者として君臨する。
バスラ再訪
翌昭和45年(1970)3月,
私は再びバスラに赴く。このたびはイラク政府が代理店の国有化をやめて、私企業に任せることにしたから、新しくわが社の代理店を選ぶ仕事であった。イラクの新政権としては海外の船会社や保険会社の代理店は、座してドル貨を稼ぐ魅力ある商売と思っていたようである。ところが実際に自分たちでやってみて、ことはそう簡単ではないことを痛感した。海外の船会社や保険会社のことを彼らはプリンシパルと呼んでいたが、プリンシパルとの間の本船の動静電報のやりとりさえ満足にやれないのであった。各国のプリンシパルは一斉に苦情をいってくる。一刻を争う商売上の問題は軍閥官僚の手にあまるものであった。そこで再びこれを私企業の手に戻し、利益を税金で吸い上げる従来の手法に戻したのであった。私がバスラのホテルにチェックインすると数社の代理店業者から接触があった。ある社の社長はシャッタルアラブ川畔の彼の倶楽部で夕食をご馳走してくれた。倶楽部の運営は全く英国式のようであった。この倶楽部のメンバーであることは社会的なステータスとして誇りうるもののようであった。イギリスは去ったが英国文化は残っているのだ。本社へは国有化以前の代理店を推薦しておいた。とくにミスがないのに代理店を変更するのは得策でないと意見を付しておいた。日本の大企業がサウジアラビアで代理店を替えてその後数年にわたってトラブルに見舞われた例を挙げておいた。この際はアラブ人のメンタリティーを尊重すべきだというのが私の結論であった。日本人やアメリカ人と違って、アラブ人は不当な扱いを受けたと感じた場合、何時までも根に持って恨み続け、時に実力行動に出る。
ワヒム氏
今回の革命の以前から使っていた代理店を指名するよう本社に意見具申して私の役目は終わった。あすはクエートに引き上げるという日の午後、ホテルの部屋で出張報告を書いていたところ、今回の代理店選考で落選した社長の一人から電話があった。一度食事をしたいというのである。
彼は船会社の代理店を引き受けようというのに船会社の経験も船会社代理店の経験も皆無だった。ただ長く英国の保険会社の代理店をやっているという。
私は無経験なものを代理店に指名することはできないとはっきり断った。彼は優秀な経験者を雇うので仕事に支障はないとなおも粘ったが私はけんもほろろに断った。電話の主はその社長ワヒム氏であった。代理店の件はよくわかったのであきらめる。しかし日本の事情などいろいろ聞きたいことがある。ついては一夕自宅のディナーに付き合ってく れないかという。冷たく 断った相手から如何なるサービスを受けることも常識に反することであったが、現地の中上流階級の家庭や生活を見てみたいという誘惑に抗しがたく オーケーした。
ワヒム氏の邸宅は高級住宅地の入口にあって塀をめぐらしたコンパクトな一戸建てであった。アラブの水準からいえば決して豪華とはいえない。ベイルートにある湾岸諸国の金持ちの別邸ではドアの取っ手や水道の水栓に金(キン)を使ったのも稀ではない。そういう過度に贅沢な屋敷やフラットから見ればこの家はまあ中流の上といったものであった。しかし居間の天井にはさぞ手入れが大変だろうと思えるシャンデリアが輝いており、絨毯や食卓、椅子の類も金のかかったもののようであった。ワヒム氏は色白のふとりじし、濃い眉毛、鼻や口の造作が大きく、この地方の上流階級特有の風貌をしている。居間のソファーで食前酒を飲みながら世間話をする。夫人は小柄な色白の美人で召使の小女(コオンナ)を指揮して、てきぱきと食卓の用意をする。
召使を奴隷のごとくこき使い、ののしる家庭が多い中、この夫人の使用人に対する態度は日本人からみて違和感のないものであった。夫妻には小学校低学年の2人の男の子があった。子供たちの食卓のしつけもちゃんとしており、夫妻の教養の程も察しられた。何をしゃべったか覚えてはいない。私はおもに日本の生活について話したのだろう。ワヒム氏は今の職業が父親の代からのものであるとかイラクの現状について話しただろう。砂漠の中の殺伐な出張旅行で私は久しぶりに家庭的な和やかな一夕を過ごすことができた。その後バグダッドでも何度か彼に会った。いつでもワヒム一家は商売気を離れて私を歓迎してくれた。
あれは昭和50年代の後半、私が川崎汽船をやめる1年ほども前のことであったろうか。その頃はもう第二次オイルショック(昭和54年)の影響も巨大な日本経済の中に吸収され、石油会社、船会社の産油国詣では一段落していた。
ある日の午後、一人の米人弁護士が私に会いに来た。応接室に通して話を聞く と、何と彼はワヒム氏の雇った弁護士であった。弁護士が言うにはワヒム一家はイラクを脱出して米国に亡命してきているのだ。米国の永住許可を得たいという。永住許可を得るためには何らかの技術や技能を持っている必要がある。そしてそれを第三者が証明しなければならないという。さてこそワヒム氏は私のもとへ弁護士をよこしたのだ。
第二次大戦後の米国は亡命者であるからといって無条件で受け入れるわけではない。とくに当時はイラン・イラク戦争の真っ最中で、米国はイラクに肩入れしてさまざまな支援をしていた。イラクは米国の友好国なのだ。友好国からの亡命者を受け入れる大義名分は立ちにく い。永住許可は米国にたいして貢献できる人物に限るという。現在ではたとえば電子技術の専門家とか環境問題に造詣の深い人というようなところだろう。米国に貢献できるかどうかの審査が厳重になるのは避けがたいところであった。私としてはワヒム一家が願いどおり米国に永住できるために、私にできることがあれば何でもしてやる気持ちであった。数年前のワヒム氏との交友を弁護士に詳しく話した。弁護士はメモを取りながら時折質問をはさんでくる。私は保険業界人、代理店業界人としてのワヒム氏の能力を多少オーバーに表現して賞讃した。翌日、弁護士は私の話を口供書にして持ってきた。直ぐにサインする。弁護士は私が終始協力的であったことに感謝し、私の話の内容にも満足して帰っていった。
弁護士の語るワヒム氏のイラク脱出行はスリリングなものであった。1979年(昭和54年)、サダム・フセインが大統領になって以来、イラクでは政権に反対するものや外国人と交際しているもの、知識階級などへの締め付けが厳しくなった。密告が奨励され、突然警察に逮捕されて帰ってこないものが出るようになった。ワヒム氏は英国人や日本人との交遊があることから、言動には何時も細心の注意が必要であった。締め付けは次第に厳しくなり、保険業の代理店も開店休業の有様になり、ワヒム氏はついに国外脱出を決意する。彼は父親からかなりの資産を受け継いでいたようであるがそれをどのように処分したかはわからない。しかし英国の保険会社代理店という家業は個人資産の海外移転にも好都合であったに違いない。すべての準備を整えた後のある日、彼ら一家は使用人に休暇を与えた上,居間の電灯をつけたまま車で空港に向かう。バグダッドで国際線に乗り換えて国外脱出に成功する。ワヒム一家が無事米国の永住許可を取ったかどうかは今では確認できない。米人弁護士が私の前に現れてからまもなく、私は川崎汽船をやめたからである。ご本人からお礼の電話があったようでもあるし、礼状を貰ったような気もするが今やたしかではない。
国際電気
今回の出張はイラクとイランの代理店選定が主目的であった。イラクの代理店が片付いたので次はイランの番である。バスラからタクシーでクエートまで戻り、そこからペルシャ湾の対岸イランに渡り、アバダン、コーラムシャ、テヘランと回ることになる。バスラからクエート国境まではイラクのタクシー、そこで出入国手続きを済ませてからクエートのタクシーに乗る。 クエート側のタクシー乗り場には数台のタクシーが客待ち中である。先頭の車はいかにもおんぼろで、運転手も乞食まがいのボロ服の老人である。車の後ろに回ってみると後輪の左右がちゃんと平行に立っていない。私は直ぐ2台目のタクシーと交渉を始めた。ところが客待ち中のタクシー運転手数名が私を取り囲み、何ごとかをわめきながら私を威嚇する。何を言っているかわからないのだが、どうも順番を守って先頭のタクシーに乗れと言っているようである。砂漠の中を3時間もこんな危険なボロ車で走ることは真っ平ごめんだ。私はまたイミグレーションの事務所に帰り、後からきてクエートに帰る客がこのボロ車に乗るのを待つことにした。そうすれば私は比較的ましな2番目のタクシーに乗れる。ところが待てど暮らせどクエート行きのお客は来ないのである。大抵の人は自家用車でどんどん行ってしまう。小一時間も待ったであろうか。ついに私は痺れを切らして、先頭のタクシーで出発する破目になった。案の定、車はガタガタ音を立てる。左後輪が外れて飛べば死なないまでも身の安全は保てないだろう。気が気ではない。
出発してから1時間半ぐらいたって、クエート市街へあと1時間ぐらいというところで、エンジンがブスブスと気味悪い音を立てて止まってしまった。後ろに回って後輪の状態を見ると、左側車輪のねじれは出発時よりも大きくなっており、とても運転を継続できる状態にない。私は車外に立って通る車にピックアップしてもらうべく手を揚げ続けた。車は砂塵を巻き上げて走り去るだけで止まってくれるものはいない。暫く立っていると砂ほこりのため目や喉が痛くなり、照りつける太陽のため頭が痛い。運転手を車外に残して車内で暫く休息する。車内といっても冷房があるわけではない。酷暑の砂漠の中で熱射病で倒れるのかと不安が湧く。
再び車外に立って手を振り続ける。何台目かの車が止まる。窓から身を乗り出しているのは日本人である。彼 「日本人の方ですか。どうされましたか」。私 「タクシーがエンコして困っています。クエート・シェラトン・ホテルまで送ってもらえませんか」。彼 「私は国際電気の技術者です。バスラ港湾局の仕事が終わってクエートに引き上げるところです。どうぞお乗りください」。砂漠のど真ん中の道路わきで手を上げているのがどうも日本人らしいというので止まってくれたのであった。地獄に仏とはまさにこのことであった。
タクシーの車内からバッグを取り出して国際電気の車に乗り込もうとすると、運転手が前に立ちはだかって大声でわめく。料金を払えと言っているのだ。私は頭にきて、クエート・シェラトンまで私を運んで幾らという契約である。途中でエンコして契約が履行できないのだから運賃は払えないと英語で怒鳴り返す。運転手には英語が通じない。彼は私の背広の裾を捕まえて放さない。大声でわめき続ける。国際電気の現地人運転手が車を降りてきて、運賃を払うべきだと言う。何時までも私の運転手と争いを続けて、仏様に迷惑を掛けるわけにはいかない。さりとてこんな大迷惑をこうむりながら当初に約束した運賃を支払う気にはなれない。私は窮余の策として契約運賃の半額を財布から取り出し、これが受け取れないなら一文も払はない。クエート交通局に出頭して審判をあおぐ、と宣言する。国際電気の運転手が何ごとかを私の運転手にしゃべっている。通訳しているのであろう。私の運転手は仏頂面のまま私の差し出したクエートディナール紙幣をうけとってそばを離れた。私は親切な国際電気の社員にシェラトン・ホテルまで送ってもらった。
イラン
コーラムシャ

|
|
イラン国旗
|
イラン航空機はクエート空港を飛び立ったかと思うと直ぐに降下を始める。ペルシャ湾の対岸イランのアバダン空港まで所要時間はわずかに25分である。アバダンはイラン原油の積出港である。三井グループの巨大なイラン石油化学コンビナートが挫折するのはもっと後のことである。ここからわが社の定期船の寄港地コーラムシャまでタクシーで1時間もかかったであろうか。事務所で代理店マネジャーに現地事情を聞く。本社の定航部はこの地方の有力代理店を総代理店に指名して、ペルシャ湾内のすべての港を管理させたい希望であった。総代理店が有能であれば本社の定航部の負担は大幅に軽減されるので本社にとっては魅力ある案に違いない。しかし私はこの案には前から問題ありと思っていた。大体、1国1港としてもペルシャ湾内の数カ国の港を統括しうるような組織力のある大きな代理店はどこにもない。それに国によって定期船や貨物をハンドリングするやり方に微妙な違いがある。また国境を接する国と国の間には対抗意識、敵対意識がある。後のイラク・イラン戦争、イラク・クエート戦争を見ればこのことは明らかだろう。また宗教の問題も見逃せない。同じモスレムでも宗派が違えば上下の関係に組織化しにく い。今回、クエート、イラク、イランと回って私の以前からの考えに間違いがないことを確信するようになった。ペルシャ湾の代理店は本社が直接管理し、テヘラン駐在員に監督させればよい。
夕食はお客20名ほどで一杯になる小さなレストランでご馳走になる。タンドリ・チキンを頼んでビールを飲む。パーレビ王朝下のイランでは米国と友好関係を結んで自由化が進んでいる。インドと違ってアルコール類は自由である。ディナー・ショーがあるという。出てきたのは 20代半ばと思われる日本人の夫婦である。和洋こき混ぜた奇妙な格好をしている。数個のお手玉を夫婦でやり取りしたり、唐傘の上で独楽を回したりする。寄席の色物といえようか。今ならさしづめ大道芸というところである。お世辞にもうまいとはいえない。演技中お手玉を何度も落とした。日本ではとても金をとって見せるわけにはいかないだろう。ペルシャ湾の奥のうらぶれた港町まで来て修行中なのであろうか。それでもイランには親日家が多い。一つの芸が終わるたびに観客は皆拍手をする。同胞とはいえ心からエールを送ることができないのが悲しい。
テヘラン
テヘランではセミラミス・ホテルに泊まった。ロビーから雪をいただいたエルブールズ山脈の4千メートル級の山並みが望見される。砂漠の砂ほこりの中からやってきた身にとっては、心をあらわれるような清冽な風景であった。ヨーロッパ風の落ち着いたホテル内部は、つい先日まで宿泊していたクエート・シェラトンの明るさとは対照的だ。米系の明るく清潔なホテルも好ましいが、欧系の、間接照明を多用し、けばけばしさを抑えた雰囲気も捨てがたい。このホテルは代理店社長の邸宅に歩いて10分ぐらいの距離にある。早速自慢の邸宅にうかがう。
社長は私よりも5、6歳年長、短躯で
でっぷりと太っている。夫人に紹介される。後に知ったことであるが夫人は大金持ちの娘とか。これもまた社長の自慢の種である。3人で居間でコーヒーを飲みながら雑談をする。居間のインテリアは何となくアールデコ調である。椅子の背もたれの木枠には金箔が施されている。邸宅の建設に当たってはあらかじめ家具職人をパリに派遣して、本場のインテリア装飾の技術を勉強させたと自慢する。夕食に近所のレストランに行く。イラン料理はインド料理よりは私の舌に合う。タンドリ・チキンなどはさしづめ日本の焼き鳥といったところか。西瓜も出た。体積にして日本の西瓜の2倍はあろうかというデカ物である。社長は日本にあるものは何でもあると胸を張る。しかし味はかなり違う。大味なのだ。
イランの現国王はパーレビ王朝の二代目である。先代は素性も定かでない貧民の出で,
コザックから自らの才覚で1925年(大正14年)イランの国王に上り詰めた。現国王は1953年(昭和28年)先代を継いだが、モサデグ首相を解任して実権を握る。モサデグ首相は先年、アングロ・イラニアン石油会社を国有化して国際的に孤立していた。これ以後、国王はモサデグ追放に熱心であった米国政府と組んで国内の自由化、米欧化に邁進する。当然イスラム教保守派との間に緊張が生ずる。国王はこれを秘密警察を使う恐怖政治によって切り抜けようとする。宮殿の前庭は滑走路になっていて、中型の旅客機が市内から望見された。革命が起こった場合には直ぐに国外に脱出できる用意といわれた。私がイランを訪問したのは今から35年も前のことであった。私がこの自分史を書いている現在とは余りにイラン、イラクの政治情勢が変わっているので、ここで現在までの推移を概観しておきたい。(2005.8.27)
実際に革命が起こって国王がエジプトに亡命したのは即位して26年後の1979年(昭和54年) 1月のことであった。パリに亡命中のホメイニ師が国民歓呼のうちに帰国して政治の実権を握る。これ以後イランの対米関係は悪化した。この年(1979年)11月には米国大使館人質事件が起き、国交断絶したまま今日に至っている。翌1980年(昭和55年)9月にはサダム・フセイン大統領のイラクは領土回復を旗印にイランに侵入した。イラン・イラク戦争の勃発である。米国は敵の敵は味方の論理にしたがってサダム・フセインを支援する。戦争の当初はイラクの勢いが盛んで、イラク軍は各方面でイラン国内に侵入する。しかしイランは人口六千五百万人を超える中東の大国である。動員できる壮丁の数もイラクの2倍はある。次第に盛り返してイラク軍を駆逐する。逆にイラク領内をうかがう形勢となる。
国連の仲介で戦争が終わったのは7年後の1988年(昭和63年)9月のことであった。サダム・フセイン大統領はこの無益な戦争から何の教訓も得なかったのだろう,
1990年(平成2年)8月には、南に国境を接するクエートに侵入する。たちまち米国を主力とする多国籍軍との間の全面戦争に入る。湾岸戦争がこれである。クエートに侵入したイラク軍は多国籍軍に駆逐される。翌1991年(平成3年)4月には、苛酷な条件で停戦に応じなければならない破目となる。もっともサダム・フセイン大統領は停戦条件の一部を無視したり、拒否したりしながら端倪すべからざる対応を示す。2001年(平成13年)9月11日のアメリカ同時多発テロはニューヨークだけで三千人以上の死者を出す惨事となった。この報復としてアメリカはアフガニスタンに侵攻してタリバン政権を倒す。同国には親米政権が出現するが、いまだに同時多発テロの首謀者を逮捕することはできない。2003年(平成15年)3月にはイラクが大量破壊兵器を隠匿しているというので、英米軍はイラクに侵攻する。この年12月、サダム・フセインは逮捕され翌2004年(平成16年)6月、暫定政権が発足する。今年1月には国民議会選挙が成功裏に実施された。しかしテロが頻発して国内不安はやまない。普通の市民が自由に行き来できる状況ではない。以上イラン、イラクの現在までの状況を概観した。
ペルセポリス

|
|
ペルセポリス・謁見の間
|

|
|
ペルセポリス・側壁浮彫り
|
折角イランにきたので2500年前の都跡、ペルセポリスを見て帰るつもりだと言ったところ、社長は代理店本社のゼネラル・マネジャーをつけてく れた。今はペルシャ暦の正月にあたり、名所古跡には観光客が殺到しているので外国人の一人旅は難しいという。案の定、ペルセポリス観光の基地、 シラーズでは宿が満員でとれない。ゼネラル・マネジャーの顔で漸く木賃宿のシングルルームが取れたのはもう深夜であった。私がベッドで休み、彼はソファーであった。敬虔なイスラム教徒である彼はメッカの方向に向かって、室内で頭を床につける例の礼拝をする。後に聞くところでは彼には数名の奥さんがおり、高給の割に生活は苦しいとか。
翌日タクシーでペルセポリスに向かう。シラーズから小1時間もかかったであろうか。ペルセポリスは巨大な石柱がまばらに残る、2500年前の宮殿の廃墟であった。回廊や階段の側壁には、外国使節、朝貢者、衛兵、捕虜などの見事な浮き彫りが残っている。石柱の高さは20数メートルもあり建設当時の威容もしのばれる。これを建設したのはダリウス一世、その子クセルクセス一世である。
この強大なペルシャ帝国を滅ぼしたのはマケドニアのアレクサンダー大王である。 紀元前 330年のことであった。それ以来ここは廃墟のままである。14、5世紀頃まではここが何の遺跡かわからず 「ソロモンのモスク」 などといわれていたと井上靖は 『アレクサンダーの道』 に書いている。彼は昭和48年、考古学者の江上波夫や画家の平山郁夫たちとここを訪れてこの旅行記を書いた。
1971年(昭和46年)10月はじめ、パーレビ国王は各国の元首を招待してここ宮殿の廃墟で盛大な建国2500年祭を行った。わが国からは三笠宮が参加された。祭りは数日間続き,
なかでも 「歴史パレード」 が人々の注目を集めた。イラン軍の将兵1800名に、各王朝の軍服を着せて、時代順に行進させたというのである。このイベントのためにパリのマキシムから200名の料理人を呼んだと新聞は報じた。この贅沢なイベントはパーレビ国王が彼の業績を内外に誇示するためのものであったが、国内のイスラム教徒との溝はこれによってますます深くなった。彼がついに国外亡命のやむなきに至るのは7年後のことである。私がペルセポリス遺跡を訪問したのは、このお祭りの前年のことであった。当時アメリカのどこやらの大学の考古学ティームがクセルクセス宮殿のはずれのほうで発掘調査をしていた。米国とイランの蜜月もこの時代が最盛期であった。
イッソスの戦い

|
|
ダリウス三世を追うアレクサンダー大王
|
アレクサンダー大王は紀元前330年、ギリシャの宿敵、アケメネス朝ペルシャを滅ぼした。このときペルセポリスは灰燼に帰した。その3年前には小アジア(今のトルコ東部)のイッソス(Issos)でダリウス三世の大軍を破っている。すでにその時点で勝負はあったのである。大王は捕虜にしたダリウス三世の家族を丁重に処遇したという。アレクサンダーの父、フィリップ二世は息子にギリシャの哲学者アリストテレスを家庭教師につけて帝王学を学ばせた。彼は単なる勇猛な武人ではなかった。このイッソスの戦いを描いた有名な二つの絵がある。
一つは19世紀、ポムペイ(Pompeii)の遺跡から発掘された。ポムペイ遺跡というのは紀元79年、ベスビオス火山の噴火で火山灰に埋もれて歴史から消息を絶ったイタリアの古代都市である。18世紀半ばから発掘が行われ、今では南イタリア観光の中心となっている。発掘された美術品のうちもっとも有名なのが
「イッソスの戦い」である。このモザイック画はポムペイの 「牧神の家」 と名付けられた豪邸の談話室から発見された。上の「イッソスの戦い」をクリックすると全体図が見られる。上の図はこの絵のなかのアレクサンダー大王の拡大図である(この拡大図はWikipediaから借用した)。世界中何処の国でもアレクサンダー大王を知らないものはいない。彼らは大王のイメージをこの絵からえている。カッと見開いた大きな目、顔面のみならず上半身全体にみなぎる緊張感は、この世界史の英雄のイメージにふさわしいものである。全体図の中央右寄りあたり馬車で逃走するのがダリウス三世とされる。馬車を牽く馬の疾走する姿には躍動感があふれていて、画家の技術の高さを物語っている。
私はこの絵を旧制中学の西洋史教科書ではじめて見た。原画は横6メートル、縦3.4メートルの大型でナポリ国立考古学博物館に収められている。同館の目玉展示品である。私は実はこの絵の実物を見ていない。今から10数年前、妻とともにイタリア観光のツアーに参加した。事前に公表された旅行日程にナポリも含まれているので、てっきりこの絵に会えると思っていた。ポムペイの遺跡を見物した後、ナポリに寄ったがそれは昼飯に海鮮料理を食べるためであった。昼食後は帰路に着き、カメオの工場で1時間以上も時間をつぶして、散財させられただけであった。
もう一つの絵は16世紀初頭のドイツの画家、アルトドルファー(Albrechet Altdorfer)
の「アレキサンダーの戦い」がこれである。リンクの「アレキサンダーの戦い」にカーソルの手の平マークを当ててクリックして拡大図にし、更にもう1回、緑十字のマークをクリックして最大図にして見ていただきたい。画面中央左寄り、白馬の三頭立て馬車で逃げるのがダリウス三世である。その後ろを長槍を横たえて騎馬で追っかけているのがアレクサンダー大王である。 この絵 (1.58m×1.20m) はミュンヘンのアルテ・ピナコテークに収蔵されている。この絵も未見である。
レバノン
ベイルート

|
|
レバノン国旗
|
レバノンは産油国ではない。しかし中東産油国の玄関に当たる場所にあり、国土に砂漠がなく、地中海に面して温暖な気候であるため中東の金持ちの保養地として昔から栄えた。郊外にはカジノ・ド・レバンという賭博場があった。大規模なディナー・ショーが売り物で、夕食を食べながら舞台のショーを楽しむという趣向である。私が行ったときには実物大の人工衛星を持ち込んで、美女たちが乱舞するという絢爛華麗なものであった。この出し物は米国の人工衛星アポロ11号の月面到着を主題としたもので、もう 3年もやっているということであった。
ここは
フランスのカジノ・ド・パリ、米国のラスベガスと肩を並べる世界三大カジノの一つだと、案内してくれた代理店社長は自慢した。この社長はエリ・ザロウビ(故人)というパレスティナ人で
パレスティナを逃れて兄弟三人、ここで手分けして商売をやっているのであった。ザロウビ一家の商売は、海上輸送、陸上輸送、物品の売買など船会社と商社を合わせたようなものであった。商売の主範囲は地中海沿岸であった。使用する言語もアラビア語はもちろんのこと英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ギリシャ語と多岐にわたる。エリ・ザロウビはアラビア語で生活し、フランス語で考え、英語で契約書を書くといっていた。右のレバノン国旗の中央の緑色の植物はレバノン杉である。レバノンはフェニキアの古代から杉の名産地であった。濫伐の結果、今日ではほとんど杉林を目にすることはできない。
1973年(昭和48年)から1974年にかけての石油危機の時代には、各国の政府、石油会社、商社、船会社の関係者がレバノンの首都ベイルートを基地にして盛んに産油国詣でをやった。かく いう私もその中の一人であった。私の泊まったフェニキア・ホテルは地中海を見下ろす高地にあり、海岸にあるホテル・セント・ジョージが目の下に見えた。いずれも高級ホテルである。レバノン内戦時にはそれぞれ異なる宗派の民兵がこれらのホテルを占拠して迫撃砲で打ちあったという。この内戦時、わが社の代理店、ザロウビ氏は一家を挙げてギリシャの首都アテネに移り住み、その外港、ピレウスに会社を移して活発な商売をしていた。私は2度ほどそこを訪れたが、彼らはベイルートの住処が難民に占領されているというのに少しも落ち込んだところがなく、商売も繁盛の様子であった。打たれ強いというか幸運というか、彼等の生活力の旺盛なことに感心したものであった。最近の新聞によると、内戦の終わったベイルートには日本料理屋数軒が進出しているという。和風料理を出す店に至っては100軒はあろうという。私がここを訪れていた頃、日本料理屋は 「とうきょう」 と 「リビエラ」 の2軒だけであった。
ミドル・イースト・エアーライン

|
|
ミドル・イースト・エアーラインのロゴマーク
|
レバノン内戦以前、サウジアラビアでの仕事を終え、ベイルートに帰ってきた。そこからロンドンに寄り、ロンドン支店で交渉の経過報告をしたのち帰国する段取りである。ベイルート空港でミドルイースト・エアーラインの便を待っていた。チェックインも終わり搭乗口を入ったところの待合室で本を読んでいた。もうまもなく搭乗も始まろうという時間である。航空会社の制服を着た男性のスタッフが私に近づくや、いきなり背広の胸ポケットの搭乗券を抜きとり、あなたの座席が変わったといいながら別の搭乗券を胸ポケットに差し込んでいってしまった。私がひと言も口をきく機会のない瞬間の出来事であった。見れば新しい搭乗券はファーストクラスのものである。要するにエコノミークラスが満員でファーストクラスに座席の余裕があるところへ、新しくエコノミークラスの乗客が現れたのだ。航空会社としては、この新しい客を満員といって断るよりは、エコノミークラスの一人をファーストクラスヘ移して、新しい客を乗せたほうが採算効率がいいわけだ。そこで私はファーストクラスの客としてふさわしい人物として係員に選ばれたわけである。そのときの私は背広にネクタイをつけ、椅子に腰掛けて英語の小説を読んでいた。大体、中近東の飛行場でネクタイを着けた乗客は珍しいのだ。私は係員が私を選択した理由に思い至って苦笑するほかなかった。しかしまあロンドンまでの3時間をファーストクラスの客になるのも悪くない。
ファーストクラスの座席の隣席には先客があった。もう50歳代も後半であろうか。小柄で貧相な男が窓際に座っている。大会社の係長クラスか。それにしてはファーストクラスで出張とは豪勢だな。軽く会釈をして席に座り、上着を脱いだり、かばんから本を取り出したり、これからロンドンまでの時間つぶしの準備も一段落した頃、いろいろ話しかけてくる。何処に行ったのか、何しに行ったのか、これから何処に行くのか、国籍はと畳み掛けてくる。私が川崎汽船という日本の船会社の社員だというと、「オオ!川崎!」 といって大仰に驚いてみせる。川崎は立派な会社だと誉めそやしながら、だれかれの人名を挙げて、知っているかと訊く。あなたの言う川崎は川崎重工のことである。わが社の姉妹会社だが大きな会社なのでその人たちを知らないと答える。
訊かれてばかりいるのも業腹で、私も彼の戸籍調べを始める。彼はバーレーンの政府で働いているという。バーレーンの政府で何をやっているのかと訊く。彼、会計をやっている。産油国の政府ともなれば会計の係長でもファーストクラスで出張するのかと一寸ばかりやっかむ。双方の戸籍調べも一段落して私が本を取り出して読もうとすると、身を乗り出してきて何を読んでいるのかと聞く。本の表紙を見せる。「オオ!私は彼の作品が大好きだ。家で何時も読んでいるがその本はまだだ」。私はベイルートのホテルの売店で、ジョン・ル・カレか誰かの最新作を買って読んでいたのだ。私はそのころイギリス作家のスパイ・スリラーに凝っていて、グレアム・グリーンとかル・カレとかは新刊が出るたびに買って読んでいた。ル・カレは諜報機関勤務の経験もある英国の外交官で、作品にも彼の経験が色濃くにじんでいた。1973年に出版した『寒い国から帰ってきたスパイ』(The Spy who came in from the Cold、邦訳、早川文庫) は世界的なベストセラーとなって、彼は一躍スパイ・スリラー界の寵児となった。
もう30分もすればヒースロー空港だという頃、本から目を離して一寸目を上げたときに彼は黒いアタッシュケースを開けたところであった。驚いたことになかにはシャネルの香水の小瓶の黄色い箱が整然と並んでいるのであった。どうも2段に並んでいるようでそのほかにはケースのなかに何も入っていないのだ。彼は読みかけらしい2、3枚のペーパーをその中にしまうとケースを閉じた。飛行機が空港について停止すると黒服に地味なネクタイの2人の紳士がファーストクラスの扉を開けて入ってくる。2人はわれわれの席に近づき、私の相客の係長と握手をしている。係長は私に向かってシーユーとかグッドラックとか何かいいながらそのまま2人と一緒に出て行った。
手にシャネルの香水の入ったアタッシュケースを持ったきりであった。空席になった窓際の席から何気なく外を見るとタラップのそばに黒い大型車が止まっている。係長は2人の紳士と一緒にその中に消えた。翌日ホテルの食堂で朝食の際、タイムズ紙を開くと、一面の下段に大きな人物写真が出ている。何と昨日の飛行機の相客ではないか。説明文を読むとバーレーン政府の大蔵大臣(Finance Minister)であった。アカウンタント(Accountant)というからてっきり会計係長とばかり思っていた。
エジプト
アレクサンドリア

|
|
エジプト国旗
|
イラクの首都バグダッドに滞在中、本社からの指示でエジプトに行くことになった。エジプトからも原油が出るようになったので、運輸省や石油省で合弁タンカー会社の交渉を
せよ
というのである。エジプトの運輸省は首都カイロでなく、港町アレクサンドリアにあるという。この港にもわが社の代理店はあるが定期航路の寄港地ではなく、一応、代理店名簿に載っているだけの名目的なものである。私の抱えているタンカー合弁会社プロジェクトは海のものとも山のものともわからない不確実なものである。わが社から一文も収入のない代理店に、こんなことで金や時間や気を使わせるわけにはいかない。運輸省との会談の状況によっては帰りに寄ってもよい。隠密旅行をすることに決めた。
バグダッドとカイロ間の飛行機を予約して飛行場にいってみておどろいた。私が予約した飛行機は乗客が集まるまで出ないというのだ。私、それではホテルで待機しているから出発時間が決まったら知らせてくれ。彼、乗客が集まり次第出るのでそんな余裕はない。ここで待て。結局、3時間ぐらい遅れたろうか。中型機に乗って再びおどろいたことに、エコノミークラスの 100名足らずの座席に乗客は数名しかいない。おかげでカイロ郊外、ギザのピラミッド群やスフィンクスを上空から堪能するまで眺めることができた。トイレに行ってまたまたおどろいた。便座には何年前についたともわからないような糞便が一面にこびりついて化石のようになっている。
エジプトの仕事が終わってロンドンに帰り、日本商社の駐在員にこの話をした。彼はロンドン駐在歴前後10年というベテランである。彼いわく、あの航路はヨーロッパの旅行者から 「空飛ぶ棺桶」 と呼ばれている札付きの線で、白人で利用するものはいない。あなたは無事にロンドンまでたどりつけて幸運であったと。
カイロ駅でアレクサンドリアまでの汽車の切符を買うのがまた大変であった。切符売り場の窓口が混雑しているのだ。どうも中近東やアフリカの発展途上国では飛行機や汽車の切符を買うなどの作業は紳士のやることではないようであった。アレクサンドリアまでの急行列車の一等車はガラガラで、豪奢なコンパートメントにふんぞり返って、窓外に飛びすぎていく 椰子の並木を眺めながら快適な2時間半の旅をした。右上の国旗の中央に描かれたエムブレムはエジプトの国章、サラディンの金の鷲である。
運輸省でどんな交渉をしたか、相手がなんと言ったかなど今になっては一つも覚えていない。ホテル名も覚えていない。記憶に残っているのは海岸の椰子の並木道を散歩したこと、古い家並みの、狭い道路の両側に靴屋が多かったことぐらいである。そもそもエジプトは前項で述べたアレクサンダー大王が紀元前三百数十年前に征服した土地である。アレクサンドリアという地名は大王にちなむものである。彼はオリエントの各地に70のアレクサンドリアを作ったといわれる。今もその名前が残っているのは数箇所に過ぎない。ここエジプトのアレクサンドリアはそのうちでもっとも大きく、もっとも有名な都市である。大王はここに麾下の武将を置いて統治させた。 彼は紀元前323年、 バビロン遠征中32歳の若さで急死する。彼の打ち立てた大帝国はたちまち瓦解する。アレクサンドリアに配置された武将はここで自立する。すなはちプトレマイオス朝の始祖である。あのクレオパトラ女王はこのプトレマイオス朝の300年後の最後の王である。最近の新聞報道によるとアレクサンドリア沖の海中でクレオパトラの宮殿が見つかったという。プトレマイオス朝は300年間この地を首都としていたのである。
カイロその他

|
|
クフ王のピラミッド
|
再び鉄道でカイロに帰り、折角の機会だというのでクフ王のピラミッドにいってみた。ギザのピラミッド中最大のもので、現在内部が公開されているのはこれだけである。このピラミッドは高さ 137メートル、底辺の一辺の長さ230メートルの正四角錐である。写真に見えているのは北側の斜面で、正面の孔状になっているのが正規の入口である。この入口は4500年前、王のミイラが石棺に納められたときに、この儀式に従事した祭司や作業員がここから出て以来というもの開けられたことはない。観光客はこの正規の入口の下方にある盗掘者の入口から内部に入る。内部に入ってからは正規の上昇通路を上って玄室 (王の死体の入った石棺のある部屋) までいける。玄室には石棺があるほか王のミイラはもちろん副葬品は一切盗掘されていてない。
ピラミッドは近くによって見ればこの写真のように醜い大石の堆積物である。建造当初はこんなではなかった。アラバスター(雪花石膏)の化粧石で全面が覆われていたのだ。
太陽に輝く ピラミッドの壮麗な眺めは王の墓にふさわしいものであっただろう。ギリシャの旅行家ヘロドトスが紀元前450年にここを訪れたときにはまだちゃんとしていたらしい。彼は著書 『歴史』(邦訳、岩波文庫全3冊) に、ピラミッドの上にはこれを建造した労働者の食料費の明細がエジプト語で書いてあったと書く 。その後いつの間にか個人や公共の建物の建築材料としてこの化粧石は持ち去られてしまったのだ。上の写真は
「秋山さんの世界遺産訪問」から借用した。
カイロ博物館にも行った。二階の特別室には王や王妃のミイラが展示されている。そのなかに入口近くひときわ凄惨な一体がある。セケンエンラー・タウアー二世のミイラである。この王は今から3600年前の人である。当時、エジプトはアジアから来たヒュクソス族に占領されていた。彼は占領軍との解放闘争のなかで戦死したのである。右耳の下には大きな剣創らしきものがあり、顔面いたるところに黒いブツブツの傷がある。顔は苦悶の表情にゆがんでおり、手足は曲がったまま硬直している。この部屋の他のミイラとは全く異なった外貌をしている。あわただしい戦闘のあいまにミイラの応急処理がなされたのである。
展示品以外に石像や壁画の類が通路のあちこちに乱雑に積み上げてある。先進国の博物館では見られない光景である。博物館に入るのに入場料を払ったのに
この特別室に入るのにまた入場料を取られた。そうそう鳩料理が名物だというので試してみたが名物にうまいものなしの例外ではなかった。

|
|
ハトセプスト女王葬祭殿
|
会社をリタイアして暫く して夫婦でエジプトの観光ツアーに参加した。この時はカイロ周辺のみならず、アスワンのアブシンベル神殿やルクソールの王家の谷まで見て回った。余談だが1997年(平成9年)11月、わが国の新婚旅行のツアーが王家の谷を見物中、待ち伏せていたイスラム原理主義のテロリストに襲われて、10人死亡するという気の毒な事件があった。このときスイスのツアー客は43人も犠牲になった。上の写真の画面左寄り傾斜路を登りきるとテラスがある。さらにもう一段登った奥の門柱の並んだ建物が葬祭殿である。自動小銃を持った6名のテロリストがこの神殿の奥で待ち伏せしていたという。テロリストは全員駆けつけた警官に射殺された。この建物は今から3500年前、時の権力者ハトセプスト女王が建造させたものである。この建物の修理復元を担当したドイツ・ティームが余りに近代的に直しすぎて、古代遺跡の面影を失わせたと非難を受けた。そういえば葬祭殿内部の壁画も最近描いたもののように生々しい感じであった。
ナイジェリア
ラゴス
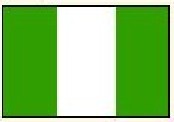
|
|
ナイジェリア国旗
|
ナイジェリア石油省の大きな会議室で、石油省幹部にわが社のタンカー合弁会社計画を説明したのは昭和49年(1974)2月下旬のことであった。わが方からは私のほかにラゴス駐在員の川本洋君が出席した。某商社の企画部の担当者2名も参加した。ナイジェリアは世界第7位の産油国で、アフリカ随一の大国なので商社の期待も大きかった。ビアフラ内戦が終わって4年たち、戦後の復興も軌道に乗ったかに見えた。政府の官僚も近代的国家の建設に意欲十分の様子であった。
それにしても首都のラゴスの混雑はすさまじいものであった。空港からホテルまでの道路は車の列がぎっしり詰まって,何時動き出すかわからないような有様であった。街のいたるところに建築中のビルが見える。港には揚げ荷役の順番待ちの船が七十数隻も滞船している。原油価格が高騰して、莫大な石油収入が転がり込む。このときとばかり、世界中の国からありとあらゆる品物を買い付ける。買い付けた貨物を積んだ船はどんどん入ってくるのに、揚げ荷役をするための埠頭が足りない。やっと埠頭に船をつけても今度は貨物を収容する倉庫が足りない。倉庫から貨物を運び出そうとしてもトラックが足りない。やっと貨物をトラックに積んでも道路網が整備されていないため肝心の貨物がいつ目的地に着くかわからない。鉄道も貨車も不足。
要するにインフラストラクチャーがなっていないのである。ふんだんにあるのは石油収入のドルばかり。外貨の氾濫がかえって国全体を混乱に陥れているようであった。現在の経済的な混乱を如何に克服するかが緊急の課題で、タンカー船隊の保有などは不急不要なプロジェクトのようであった。ナイジェリア政府は人口増加と無秩序な経済活動によって都市機能の麻痺したラゴスを捨てて、首都を新天地に移すことにする。私がラゴスに行った翌々年の1976年、内陸のアブジャが新首都と決められた。実際に首都を移転したのは1991年のことであった。しかし現在もこの国の経済の中心は旧首都のラゴスのようである。ナイジェリアは1960年(昭和35年)独立した。国旗は公募によって選ばれた。緑は農業を白は平和と統一をあらわすという。油田が発見されるのは独立以後のことである。
ビアフラ戦争
1967年(昭和42年)5月、ナイジェリアの東部、南部を主な居住地とするイボ族は、ナイジェリア共和国からの独立を宣言してビアフラ共和国を樹立する。イボ族としては、最大部族のハウサ族が政権を牛耳って、イボ族支配地域の富を収奪することに我慢できなかったのである。イボ族支配地域の富とは、同国の東部、南部に埋蔵された豊富な石油資源である。政権を支配するハウサ族はもとよりこれを容認できない。石油収入がナイジェリアの歳入の70数パーセントを占める。ここにナイジェリア内戦が始まるのである。政府側を英国とソ連が応援し、ビアフラ側をフランスが支援して戦争は泥沼化する。ビアフラ側は多数の白人傭兵を雇って兵力の不足をカバーする。一時はいいところまで行くのであるが結局、政府側に軍配が上がって1970年(昭和45年)1月、3年間の内戦は終わる。戦死・餓死をあわせたビアフラ側の死者は200万人といわれた。
英国人フレデリック・フォーサイスはこの戦争をロイター通信の記者として現地で取材した。彼は敗戦のビアフラ軍首脳と深い絆で結ばれる。ビアフラ戦争後の1971年、彼は処女作ともいうべき 『ジャッカルの日』(The Day of the Jackal、邦訳、角川文庫) を出版する。この本は世界的なベストセラーとなる。内容はアルジェリア叛乱軍の残党が、ジャッカルという暗号名の殺し屋を雇って、ドゴール・フランス大統領の命を狙うという荒唐無稽の物語である。物語はフィクションであるが、細部の描写にリアリティーがあり、文章が易しいので、私は手に汗握って読んだ。映画も見た。映画もよくできていた。フォーサイスはこれによって多額の印税を手に入れる。彼はこれを元手にして敗戦のビアフラ軍人と組んで、赤道ギニア共和国に革命を起こそうとする。この計画は事前に漏れて挫折する。この計画がとんとん拍子に進んで、革命戦争が起こったことを想定したフィクションが、彼の第二作 『戦争の犬たち』(The Dogs of War、邦訳、角川文庫) である。それにしてもフォーサイスのビアフラ戦争への入れ込みようがうかがえる。
先日、NHKのテレビがナイジェリアの石油事情を放映した。国名の元になったニジェール川は、ナイジェリア西部を南北に貫流して大西洋に注ぐ大河である。この川の河口のデルタ地帯は古来、好漁場であった。ところが独立後、ここに豊富な油田が発見され、今ではこの国の重要な原油の産地になっている。ここに住む小部族は、自らの土地の下の石油資源を自らのものと考えている。大部族が牛耳る中央政府がこの資源を収奪して、所有者である自分たちになんらの見返りがないことを承服できない。彼らは河口の海中を縦横に走るパイプラインに穴をあけて、原油を盗掘する。その量が1日あたり10万バーレルにもなるとこの番組はいう。1バーレル60ドルとして円換算すると、年間2千億円になる。彼らは武装して中央政府に対抗している。採掘を担当している米系石油会社は手を焼いて、この部族に何がしかの金を渡して事態を乗り切ろうとしている。しかしこの涙金がなくなればまた紛争になるのは必至で、抜本的な解決にはならない。このような盗掘によって原油が漏れ出し、海水を汚染して太古から住民の生業である漁業がお手上げになっているともいう。部族間の反目、宗派間の争いが資源配分をめぐって表面化する。これは埋蔵資源の豊富な発展途上国の宿痾である。(2005.9.15)
ナイジェリア航空
私は発展途上の産油国に出張する場合、なるべくその国の国営航空を利用することにしていた。理由はそれがその国の政府との交渉に役立つからというわけではない。これを話題に取り上げることによって、会談の場の雰囲気を和らげる効果があると思えるからであった。少なくとも本題に入る前の世間話の一つとしては都合の良いものであった。ロンドンからラゴス行きのナイジェリア航空のファーストクラスをちょっと覗いたところでは、華やかな民族衣装の女性連が多かった。ラゴスでの仕事が終わってロンドンに帰るときもナイジェリア航空であった。
座席について暫く して私はチケットを無く していることに気づいた。航空会社の窓口でチェックインしてからゲートを入ると税関の手荷物検査がある。その時にはパスポートとチケットを提示しなければならないので、そこまではあったことがたしかなのだ。
自分で探しに行く時間はもうない。搭乗員に頼むほかはない。そのとき私はラゴス駐在員の川本君の話を思い出した。彼はナイジェリアでは賢そうに見える人が賢いというのだ。日本では一見賢くなさそうで賢い人は大勢いる。ついこの間まで首相であった福田さんや自民党の大物の竹下さんはちょっと見には賢そうに見えないが超一流の賢人である。また賢そうで賢くない人も大勢いる。このナイジェリアではそういうことはないというのだ。賢い人はかならず賢そうな容貌だというのである。
私は自分のそばを通った美人のスチュワーデスをやり過ごし、となりの通路にいるスチュワードを手を上げて呼んだ。私は機内に入ったときから、このナイジェリア人のスチュワードの、目から鼻に抜けるような利発そうな風采に気がついていた。態度動作も自信に満ちており、キビキビとスチュワーデスたちを指揮して動き回っている。私は彼に一部始終を話した。彼は大事なチケットを無く した私を非難する風もなく、ここで暫く待っていなさいというや足早に機首のほうに去っていった。出発時刻は刻々と迫る。私は気が気ではなかった。スチュワードがチケットの束を持って帰ってきたのは出発時刻を過ぎて20分ぐらいたったときであった。税関の荷物検査の台の下に落ちていたのを、誰かが見つけて届けてく れていたのだ。もし見つからなければ ロンドンから東京までの運賃数十万円を自腹をきって払わなければならないところであった。私はあらためて川本駐在員の件(クダン)の話が、私の咄嗟の判断を助けたことに感謝した。(2005.9.15)
あとがき、 昭和史・第四部続、ホームへ