少年時代
高等科1年生
昭和13年(1937)3月、私は尋常科6年の課程を終えて高等科1年に進んだ。その年の1月頃から慢性盲腸炎がぶり返して体調が悪く、私は中学校受験の機会を逸した。これは私の中学進学に消極的な両親の意に沿うものでもあった。当時の日本の田舎では長男は故郷にとどまって家を相続し、先祖の墳墓を管理するのが当たり前と思われていた。高等教育を受けた一人息子は家と親を捨てて他郷に奔るだろうと両親は恐れたのであった。事実はまさにそのように進んだので当時の両親の心配は妥当なものであった。
高等科の勉強は実学が中心であった。田舎の実学は農業である。授業は農業用の教科書による座学と学校菜園での実習が中心となる。わが家は自営業者であったのでこのような農業中心の学校には大いに違和感があり、私は中学校進学を真剣に考えるようになった。一方、学校成績の優秀な倅を田舎に朽ち果てさせるなと両親を説得する人も現れて、私は翌昭和14年(1938)4月から、汽車で30分かかる忠海町の忠海(ただのうみ)中学校に通うことになった。
広島県立忠海
中学校
環境
私が高等科一年修了後入学した広島県立忠海
中学校は、広島県豊田郡内では只一つの中学校であった。忠中
の略称でとおった郡内の最高学府であった。 わが吉名小学校では男子六年生一クラスの人数は何時も50名位であった。そのうち忠海中学に入学するものは1ないし2名に過ぎなかった。女子もほぼ男子と同数の一クラスの中から、忠海や竹原の女学校に入るものは男子よりさらに少なく、数年に1名というような有様であった。妻みよ子の入った東京府中野区野方第五小学校では男子も女子も大部分の生徒が中学校、女学校、専門学校に進学したという。戦前は日本の都市部と農村部では教育水準に格段の違いがあったのである。

|
|
戦前の忠海
中学校
|
|
この校舎は昭和50年代に改築されて今は昔の面影をとどめていない。写真手前の線路は呉線、左三原方面、右呉方面、左方向に1.5キロぐらいのところに忠海駅がある。手前左方の三角屋根は武道場、その右は小銃庫、画面中央逆コの字型の建物が校舎、正面2階建て校舎の2階右端がわれわれ3年2組の教室であった。その右方、海岸線に直角に二棟の2階建ての建物がある。寄宿舎である。逆コの字型校舎に囲まれた三角屋根は講堂である。校舎の左方にはグライダーの練習をした広い運動場がある。運動場の東側は、この写真では見えないが、小高い丘になっており、そのてっぺんに記念館があった。われわれはこの丘のことを記念館高地と呼んでいた。沖の海は瀬戸内海で、画面上方中央の黒い小島は、陸軍の毒ガス工場があったことで有名な大久野島である。現在は国民宿舎があり観光地になっている。その背後の薄い島は大三島、その右は大崎上島である。
|
一年生の時間割

|
|
しおり 裏
|
一年生の時間割は右のとおりである。この時間割は、上に掲げた大毎小学生新聞の促販用のしおりの裏面に、当時の私が書いたものである。そのままここに出したかったがインクが消えかけて読みにく いのでエクセルで打ち直した。下の表は上の 「時間割」 にもとづいて私が作ったものである。1週間の授業時間が各課目にどういう風に配分されたかを示す。国漢・英・数で全授業時間の半ば以上を占めていることがわかる。次にシェヤーの大きいのが体力練成部門である。教練、体操、武道、作業で全授業時間の2割を占める。武道は剣道、柔道のいずれかを選択するのである。私は柔道をやりたかったが、小学校の四年、五年のときに手足の骨折や捻挫を繰り返していたので、剣道にした。作業とは学校田(畑)での農作業であった。小学校ではせいぜい1週間2回の体操の時間に、担任の先生の指導で徒競争とかドッジボールをやるぐらいであったが、中学に入ると各部門に分かれた組織的のものになった。教える先生も各部門での専門家であった。これによって虚弱な小学生であった私は飛躍的に体力がついて、健康体になった。
学校は午前八時始業で、朝礼があった。午前中4時限、午後2時限、土曜日は午後1時限であった。朝礼で運動場に整列したときには瀬戸内海の島々がまぢかに見える。島と海面の接点が丸く見える浮島現象をはじめてみた。一年生の修身は校舎2階の畳敷きの三省室に正座して、数田猛校長からじきじきに教えを受けた。数田校長は短躯であったが身体中から精気があふれているという感じのひとであった。さいしょの修身の時間に聞いた「稚心を去れ」 という言葉を今でも覚えている。校長は黒板に大きな字で 稚心 と書いた。一年生はまだ子供であるから、家が恋しくて仕方がない。とくに汽車通学生や寄宿生はやたらに家に帰りたい。校長の言(げん)はまことに時宜に適したものであったが、実際に稚心がなくなったのは半年もたってからであったろう。一年生の理科は生物であった。その日の授業はかえるの解剖であった。生徒は山田先生からあらかじめかえるを持ってくるようにいわれた。私も裏の田んぼで捕まえたかえるを2、3匹、洋服のボタンの空き箱にいくつか穴をあけて、その中に入れて学校に持っていった。呉市など都会から通っている生徒はどうしたのか覚えていない。当時、生徒は解剖器具のセットを購買部で買わされて皆持っていた。休み時間に、麦わらの茎をかえるの尻に差し込んで空気を吹き込み、腹を膨らませて遊んだことを覚えている。代数の把田(たばた)先生は長身で眼鏡をかけ、眼光炯炯(けいけい)としていた。宿題をやっていかなかったものは廊下に立たされた。何時も授業の始めの5分間は計算をやらされた。123456789という9桁の整数の2乗計算であった。今の百ます計算のはしりといえようか。

数字は時限
寧ロ鶏口トナルモ・・・
漢文の先生はもとは小学校の校長であった。中等教員検定試験に合格し,晴れてわが忠中の漢文教師になった刻苦勉励のひとであった。年配としてはまだ30代のなかばというところだったので、校長といっても瀬戸内海の小島の分教場の校長であったのかもしれない。二年生の漢文の時間に 『十八史略』 を習った。今から二千三百年まえの支那の戦国時代の話である。秦、趙,燕などの7国が中原に覇を争っていた。なかでも秦はもっとも強大で、さまざまの要求を突きつけて他の6国を圧迫していた。ここに遊説家(ゆうぜいか)蘇秦(そしん)があらわれる。遊説家とは弁舌を武器に、諸国に合従連衡(がっしょうれんこう)を呼びかける人のことをいう。わが国にその例を探せば、さしずめ幕末の坂本竜馬がこの遊説家に当たるであろう。竜馬はかねて喧嘩ばかりしていた薩摩と長州の間を周旋して、討幕の同盟を作り上げることに成功する。
それはともかく 蘇秦である。蘇秦は6国を回ってその王に説いた。強大な秦に臣従して生存を保証してもらうよりも、小国たりとも王の地位を保ったほうが良い、そのためには6国は合従して秦にあたるべきだというのである。このときに蘇秦は 「寧ロ(むしろ)鶏口(けいこう)トナルモ牛後(ぎゅうご)トナルナカレ」 という諺を持ち出して、6国の王を説得して成功した。
大きくても牛のお尻より、小さくてもにわとりの口のほうが良い、大組織の平(ひら)よりも小組織の長(ちょう)が良いというほどの意味の比喩である。先生は一応意味を説明した後、生徒を指名して、この諺の例を挙げるよう促した。ある者は、大きな駅の助役より小さな駅の駅長とか、金持ちの末っ子より、貧乏人の長男とか皆適切な例を挙げた。私の順番が回ってきた。私が考え付く 例は大方他の生徒が答えてしまっていた。切羽詰って私は、中学の平教員よりも、むしろ小学校の校長のほうが良いといってしまった。教室中の生徒がくすくす笑い出す。頭の格好が瀬戸内海名物の蛸に似ているところから、蛸とあだ名されたその先生は、真っ赤な顔をして私を睨みつけた。
この先生は陸軍の軍歴があったのだろう、教練の先生もしていた。教室でこんなことがあってからしばらく後の教練の時間、分列行進の練習をしていたときに、脚の上げ方が悪いというので、私はこの教師に後ろから尻を蹴られた。靴底に鋲をうった軍隊用の革靴が、私の尾?骨を真下から直撃した。思わずよろめいて、うづくまるほどの痛さであった。この痛みはこの後数ヶ月も続いた。
神聖喜劇
われわれ汽車通学生は年に1回、運動場東端の高地に聳える記念館で集会を行った。記念館は創立何周年かを記念して造られたものだろう。畳の部屋が数室あり、炊事のできる設備もあって、生徒の小集会に時々利用された。汽車通学生の集会は汽車通学の四年生の世話人が、同じく汽車通学の下級生に檄を飛ばして集め、お菓子とお茶でだべる会である。まだ子供であったわれわれ新入生は、大人になりかけた四年生から、男女間の機微や卑猥な数え歌などを教わった。五年生は上級学校受験準備に忙しいという理由で、こういう催し物には参加しなかった。生徒自治の主役はいつも四年生であった。欠礼をしたなどの些細な理由で下級生を殴ったりするのは四年生であった。戦前の中学校では生徒の上下関係は極めて厳格であった。下級生は上級生に対して軍隊式の挙手の敬礼をした。
通学の汽車の乗り方にも厳しい区分があった。当時の呉線の列車編成は6輌であった。一年生の乗車位置は機関車の次、第1輌目の前半であった。二年生は第1輌目の後半から第2輌目の前半にかけて、三年生は第2輌目の後半。四年生は第3輌目の前半、五年生は第3輌目の中央部となる。逆に女学生は最後尾の第6輌目の後部から一年生が詰めていき、順次二年生、三年生と前方の車輌になり、第3輌目の中央部で男女中学生の最上級生が混乗するという仕組みである。後に私は大西巨人の 『神聖喜劇』(光文社文庫 全5巻)を読んで、このような中学生と女学生の通学乗車規律が、わが地方だけのものでないことを知った。大西は福岡市の県立 F 中学在学中、鹿児島本線筑前新宮駅から博多駅までの20数分を汽車で通学するのである。時期は昭和10年(1935)から14、5年のことであるから、大西は私より4、5歳の年長であった。列車の前部車輌に男子中学生、後部車輌に女学生が乗るように、との乗車心得が学校当局から出されていたという。大西は新宮駅の次の駅、香椎駅から乗る女学生に恋い焦がれていたが、この乗車心得のため話すこともできなかったと残念そうに書いている。
わが中学で軟派で有名な某五年生が、列車内で女学生と話をしていたげなという噂は、たちまち学校中に広まった。当時の中学生の男女交際の実情はこんなものであった。
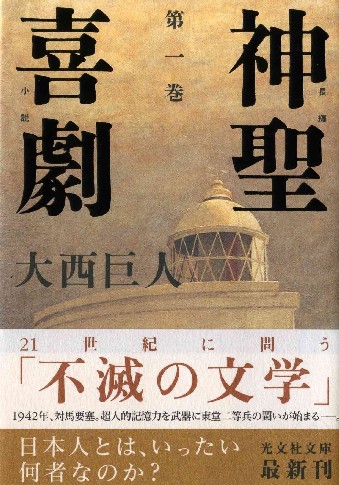 余談であるが、『神聖喜劇』 は著者大西巨人の、少年時代から軍隊時代にかけての自伝的小説である。彼は福岡の F 中学から旧制高校に入るのだが、中退をして就職する。召集されて對馬の砲兵連隊に入り最下級の二等兵からつとめる。陸軍には兵隊の実生活を細かく規制する内務法規がある。下士官や古参兵は、この法規の規定をたてにとって下級兵をいじめる。ところが大西は稀代の記憶力にものをいわして 『軍隊内務書』や『砲兵操典』 を丸暗記し、逆に上級者の揚げ足をとって、いじめに屈しない。古参兵はこの新兵の下克上に腹を立てるのだが、法規の引用と解釈には大西にかなわないので、どうすることもできない。五味川純平の 『人間の条件』(文春文庫 全6冊) の主人公、梶上等兵が体力と胆力で危機を脱するのを、大西二等兵は智力で切り抜けるのである。梶上等兵は終戦直後の満州で、壊滅した関東軍の中から奇跡的に生還する。両書はいずれも日本陸軍の下級兵を主人公にしている。しかし 『人間の条件』 の暗鬱(あんうつ)にたいし、『神聖喜劇』 は明朗である。からりとして明るいのだ。それに著者は小説中に内外古今の典籍を引用して該博な知識を披露する。私は文庫本の各巻が発行されるのを待ちかねて読んだ。戦後のわが国の文学のなかで最高傑作と激賞する批評家もいる。
余談であるが、『神聖喜劇』 は著者大西巨人の、少年時代から軍隊時代にかけての自伝的小説である。彼は福岡の F 中学から旧制高校に入るのだが、中退をして就職する。召集されて對馬の砲兵連隊に入り最下級の二等兵からつとめる。陸軍には兵隊の実生活を細かく規制する内務法規がある。下士官や古参兵は、この法規の規定をたてにとって下級兵をいじめる。ところが大西は稀代の記憶力にものをいわして 『軍隊内務書』や『砲兵操典』 を丸暗記し、逆に上級者の揚げ足をとって、いじめに屈しない。古参兵はこの新兵の下克上に腹を立てるのだが、法規の引用と解釈には大西にかなわないので、どうすることもできない。五味川純平の 『人間の条件』(文春文庫 全6冊) の主人公、梶上等兵が体力と胆力で危機を脱するのを、大西二等兵は智力で切り抜けるのである。梶上等兵は終戦直後の満州で、壊滅した関東軍の中から奇跡的に生還する。両書はいずれも日本陸軍の下級兵を主人公にしている。しかし 『人間の条件』 の暗鬱(あんうつ)にたいし、『神聖喜劇』 は明朗である。からりとして明るいのだ。それに著者は小説中に内外古今の典籍を引用して該博な知識を披露する。私は文庫本の各巻が発行されるのを待ちかねて読んだ。戦後のわが国の文学のなかで最高傑作と激賞する批評家もいる。
藤村忠雄
藤村忠雄の編入
私が忠中に入ったときに、二年生に藤村忠雄がいた。藤村は私の小学校の同級生であった。昭和13年(1938)4月、彼は同級の他の1名とともに忠中に入った。私はいろんな事情で小学校を卒業してから高等科に進んだ。そこから翌年、忠中に入ったために藤村らとは1年遅れとなった。藤村の両親は私が小学校五年の前期に何処からか、わが吉名村に引っ越してきて、平方(ひらかた)部落の煉瓦工場で働きだした。朝鮮人であった。彼はすぐに吉名小学校に転入して、私たちのクラスに編入された。日本人と変わらない流暢な標準語を話すので皆びっくりした。最初は朝鮮名を名乗っていたが、やがて藤村忠雄になった。創氏改姓ということであったろう。背はクラスで一番高かった。それも道理、年齢は標準年齢より2、3歳上であった。和漢の古典では力持ちのことを膂力(りょりょく)衆にすぐれなどというが、彼にはその表現が似合った。それまでのガキ大将も彼には一目置いて遠慮する風があった。彼自身、クラス内の勢力争いや小競り合いには無関心の風であった。当時のわれわれの年齢では、2、3歳も年が違うともう世代が違うといってもいいぐらいで、藤村自身、話が合わないと感じたのであろう。
彼がわがクラスに来て半年ぐらいたったときであったろうか。父が身体具合が悪く新聞配達が出来ないことがあった。そこで父の配達区域であった平方部落を私が肩代わりして配達した。煉瓦工場付属の工員用長屋の一つに新聞を届けた。工員用の長屋のほとんどには朝鮮人の家族が住んでいた。そこは貧民窟の名にふさわしい住居であった。朝鮮人はもともと新聞などは購読しないので奇異な感じを持ちつつも、入口の扉の隙間に中国新聞を入れて、走り去ろうとしたところ、そこに藤村が立っているではないか。彼は肩で私の身体をドンと押すと 「おめぇ、なめーきなことをしょーるとブチまーすど」 といったものだ。「ブチまーす」 とは 「ブッ叩く」 のわが村の方言であった。その頃になると彼も完全に田舎言葉になっていた。私は父の配達区域のほかに自分自身の配達区域があり、まごまごしていると学校に遅れるので気がせいている。逃げるようにして走って近くに止めてある自転車に飛び乗って次の家に向かった。かりに急いでいなくても、彼と喧嘩をしても勝ち目はない。逃げたに違いない。
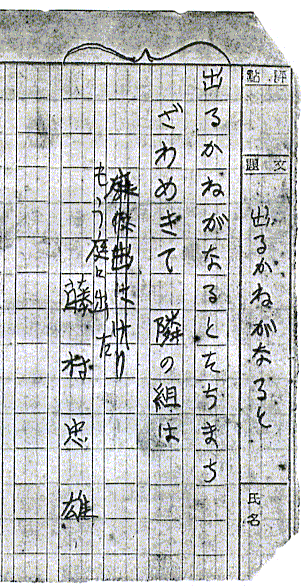
|
|
小学5年生藤村忠雄の和歌
|
その日、学校に行っても彼はそ知らぬ顔をしている。私もそのことをおくびにも出さなかった。彼が転校してきて以来の私との関係は、それほど悪いというほどのものではない。その朝、彼がどうしてそんな粗暴な態度に出たか、いくら考えても理由がわからなかった。今にして思うと、彼は同級生の私に惨めな住宅を見られて腹が立ったに違いない。また学校での私のステータスに日頃違和感をもっていたのであろう。私は五年生のそのとき級長ではなかった。しかし級友からは一目置かれており、ガキ大将にいじめられるなどということは絶えてなかった。和歌や俳句を級友から募集して、優秀作品に賞品を出したりしていたことなどに反発したのであろう。今まで日本の何処の小学校に通っていたかは知らないが、私のように、体格が貧弱なくせに威張っている子供を、見たことがなかったに違いない。彼は成績も良かった。クラスで十番以内には入っていたのではなかろうか。少なくともその程度の成績でなければ吉名小学校から忠中へ入るのは難しかったのだ。
藤村忠雄の和歌
右の写真は、私の和歌・俳句の募集に応じて藤村が提出した和歌である。400字詰原稿用紙を手でちぎった紙片に書いてある。最後の句は”庭に出にけり”を2本棒で消して”もう庭に出た”に訂正している。一昨年 (平成19年) 4月の転居のための家財整理中、父の仕立服注文帳や、母の家計簿などの入った紙箱から出てきた。応募原稿は何人から出たのか。複数であることは間違いないが、他のクラスメートからの原稿はない。この藤村の和歌を入賞させたのだろうか。藤村の原稿だけがあるのは何故か。理由は一切わからない。
出るかねがなるとたちまち
ざわめきて 隣の組は
もう庭に出た
藤 村 忠 雄
1時限が終わるごとに、教頭先生が廊下に吊るされたかねを叩く。それを合図に全校生徒は校庭に出て遊ぶ。ドッジボールや鉄棒をやるものもいる。このかねのことを生徒は「出るかね」といった。15分の休憩時間が終わると,ふたたびかねの合図で生徒は教室に入って次の授業を受ける。このあたりの生徒の規律は実に整然としたものであった。それはともかく藤村の作品である。小学生の作品である。歌の優劣は問うまい。ともかく藤村は、日常茶飯の出来事を、五・七・五・七・七の和歌の形式にまとめることができたのである。(この藤村の和歌に関する記事は平成21年2月に追加した)
軍人勅諭
藤村らのクラスが四年生であった或る日の朝礼での出来事である。配属将校の丸井陸軍中尉が号令台の台上から生徒を見回しながら、軍人勅諭を暗誦できるものは手を上げよといった。何人かが手を上げたが、真っ先に勢いよく手をあげた藤村が指名されて、暗誦することになった。
配属将校とは、大正14年(1925)から全国の中学校以上の男子の学校に、陸軍から派遣されて常駐した現役将校のことをいう。当時、軍備縮小は世界の潮流であった。海軍は大正10年(1921)のワシントン海軍軍縮条約により、米:英:日の主力艦の比率を5:5:3に抑えられた。その結果わが海軍は建造中および老齢の戦艦17隻を破棄させられた。海軍兵学校の採用人員も、これまでの300名から一挙に50名に激減した。陸軍もまた大正14年(1925)、宇垣陸相のもとで4個師団を削減した。陸軍はその代償として配属将校制度の創設を認められ、数千名の将校が整理を免れた。中学校以上の男子の学校全部に、現役の将校を派遣するというのである。中学校以上の全部の男子校といえば、将来の日本を背負ってたつ人材の、すべての養成所を意味する。そこで軍事教育、軍国主義教育ができると、陸軍としては大いに期待するところがあった。事実はまさにそのとおりに進行した。とにかく戦時中の男子中学校における配属将校の権威は絶大なものであった。陸士、海兵など軍関係の学校受験の際、配属将校が採点する内申書の教練課目が丙や不可であったら、先ず合格はのぞめなかった。配属将校の下には予備役の陸軍軍人が2、3名いた。小銃の取り扱い方とか、行進のやり方などなどは、これらの教練の先生から習った。上にあげた漢文の先生もそのなかの一人であった。
軍人勅諭とは明治15年、明治天皇から陸海軍人に賜った勅諭のことである。”我国の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にぞある” で始まる。序論に次いで神武天皇以来のわが国の軍制が略述された後、この勅諭の本旨であるいわゆる聖訓五箇条が述べられている。次のとおりである。
一軍人は忠節を盡すを本分とすべし
一軍人は禮儀を正しくすべし
一軍人は武勇を尚(トウト)ぶべし
一軍人は信義を重んずべし
一軍人は質素を旨とすべし
上の五箇条のおのおのの条文の頭の漢数字の一はひとつと読まなければならない。各条にはそれぞれ詳しい解説がついて、首題の趣旨を敷衍(ふえん)している。たとえば第一条の 「忠節」 の説明の後尾には次のような文言がある。”・・・是国運の盛衰なることを辧(わきま)へ世論に惑(マド)はず政治に拘(かかわ)らず只一途(いちず)に己(おの)が本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は鴻毛(こうもう)よりも軽しと覚悟せよ・・・” このうち 「世論に惑はず政治に拘らず」 の文句は参謀本部長山県有朋が自ら書き加えたものといわれている。それはともかく、戦前の海軍にはこの 「政治に拘わらず」 の雰囲気が、上は海軍大臣から下は少尉候補生に至るまで広く浸透していた。大東亜戦争の開戦決意にさいし、
及川海相は和戦の決を近衛首相に一任した。海軍が開戦に反対すれば、首相がそれを根拠に和平に向かうことが明らかな情勢の下で、海軍としてあえて戦争回避の意思表示をしなかった。海相の胸の中には、海軍は伝統的に政治にかかわらないのだという言い訳があったに違いない。
藤村は全校生徒の前で臆することなく 軍人勅諭を暗誦した。明治以来今日までに出された勅諭のなかで、もっとも長い軍人勅諭は全部暗誦するのに30分はかかる。藤村はこれをよどみなく 暗誦し終えた。この勅諭は陸軍では全将兵に暗誦が義務付けられていたらしい。わが中学でも配属将校や教練の先生はこれを暗記するよう生徒を指導したが、言いつけどおり暗記したものは少なかった。私も暗記はしなかった。ただ上に掲げた五箇条を 「ひとつ何々。ひとつ何々・・・」 と言えるぐらいのものであった。「汝ら軍人能く朕が訓(おしえ)に遵(したが)ひて此道を守り行ひ国に報ゆるの務を盡(つく)さば日本国の蒼生(そうせい)擧(こぞ)りて之を悦(よろこ)びなん朕一人の懌(よろこび)のみならんや 明治十五年一月四日 御名(ぎょめい)御璽(ぎょじ)」 藤村が勅諭を暗誦し終わると、配属将校は藤村を 「わが忠中の宝だ」 と激賞した。藤村は面目をほどこしたのであった。
卒業後の消息
藤村らの組は昭和18年(1943)3月、忠中を卒業した。本稿を草するにあたって、彼の消息を彼の組の生存者に聞いたが誰も知らない。以下は私の推測である。藤村は卒業後陸軍の何処かの学校に入っただろう。配属将校の推薦もあり、彼の努力もあり、終戦の時には上等下士官か准尉にはなっていただろう。終戦である。インテリであった彼の両親は、このできの良い倅をつれて朝鮮に帰国した。朝鮮は北も南も国軍の創設に懸命であったであろう。日本陸軍で中堅幹部の卵であった藤村は、北であれ南であれ、朝鮮軍の将校になったにちがいない。当時の朝鮮軍の指導者は北も南も、日本の陸軍士官学校を卒業した将校であった。昭和25年(1950)6月、朝鮮戦争が勃発する。北鮮軍は一時、釜山を陥れる勢いであったが9月、国連軍が仁川、元山に逆上陸するにおよんで総退却をはじめる。10月、中国軍が参戦して情勢は混乱する。翌昭和26年(1951)6月、ソ連の調停で停戦、北緯38度線で南北朝鮮が分断されて今日におよんでいる。
この朝鮮戦争による人的損害は、信頼するにたる資料が発表されないので今に至るまではっきりしない。作家の児島襄は両軍それぞれ240万人と推定している(『朝鮮戦争』全三巻、文芸春秋)。韓国側の発表によれば韓国側の戦死約41万5千人、負傷および行方不明約42万9千人とある。北朝鮮側にも同じような損害があったとすれば、藤村がこの戦争で死んだと考えても不自然ではない。もし生きていれば青春を謳歌した母校、忠海中学あるいはその後身である忠海高校を、戦後半世紀の間には一度は尋ねてきているはずだ。北朝鮮に住んでいようと韓国に住んでいようと。同級生の誰も彼の消息を知らないということは彼が死亡した証拠になるだろう。私は彼の朝鮮名を知っている。彼が小学校で、私たちのクラスに編入されたときには、彼を朝鮮名で呼んでいたのだ。しかしあえて朝鮮名は書かないことにする。
弁論部
ツーダンフルベース
私が中学二年生の秋であったろうか。講堂に全教員、全校生徒が集まって校内弁論大会が催された。この弁論大会は、そのあと広島市で行われる県下中等学校弁論大会へ、出場する選手選考を兼ねたものであったろう。会も進行して終わりに近く、四年生の弁論部員が 「ツーダンフルベース」 という演題で演説を行った。野球の試合で二死満塁になったあとバッターボックスに立つ打者の、絶体絶命の心境を強調する内容であった。論旨はともかく、私が驚いたのは弁士の態度と発声法であった。弁士である四年生は両手を演壇に乗せ、上体を演壇にかぶせ、平蜘蛛のようなというか平家蟹のようなというか、それまでの弁士が見せたこともないようなスタイルでしゃべるのであった。その声たるや腹の底から搾り出すような悲壮な声なのであった。「ツーーーーダンフルベース」と2回位繰り返し絶叫して演説を終わった。なるほど、二死満塁で打席に入る打者の心境は悲壮なものであろう。しかしこんな格好とこんな抑揚で絶叫されては、弁士の真意が聴衆に伝わることはないだろう。聴衆はしらけてしまうのだ。私は心中、この弁論部員の弁論に強い違和感を覚えた。
天にありては燦
く星

|
|
永井柳太郎
|
私の小学校、中学校時代にはまだ明治・大正時代の雄弁術の伝統が消えかかりながらもわずかに残っていた。小学校六年生であったか、高等科一年生であったろうか。父がもっていた演説速記雑誌 『雄弁』 で,
政治家の永井柳太郎の政談演説を読んだ。月刊雑誌 『雄弁』 は、今の講談社の前身、大日本雄弁会が明治末年に創刊した雑誌である。政治家の演説や学者の講演などの速記の掲載を主とし、論説や評論なども載せる硬派の雑誌であった。主たる対象読者は中央、地方の政治家や学者・名士、政治家志望の青年や学生、政治家の後援会の人々などである。しかし
私の父のように田舎の一庶民まで、時には目を通すというのであるから、雄弁あるいは雄弁術への憧憬が、広く社会に浸透していたことがわかろうというものである。評論家の福田和也は、月刊誌 (『文芸春秋』平成18年2月号) に連載中の 『昭和天皇』 に於いて、朝日新聞記者緒方竹虎の口を借りて、明治末年から昭和の初めにかけてのこの時代を 「言論が社会を動かしていくダイナミズムの時代」 と言っている。
昭和に入って雄弁熱は沈静化しつつあった。しかしこの雑誌が廃刊になったのは昭和16年(1941)、大東亜戦争開戦の直前であった。私がこの雑誌で読んだ永井の演説の内容は全く覚えていない。がそのなかにあった 「天にありては燦く星、地にありては花咲く桜」 という文句だけを覚えている。対句の妙というか表現の調子のよさというか、何度もつぶやいているうちに頭の記憶装置の中に焼付けられたのだろう。当時はそんな美辞麗句や適切な警句を含んでいることが、名演説としてたたえられる重要な要件であった。 永井柳太郎といえば大正から昭和にかけて何度も大臣をやった憲政会の領袖であった。彼はまた雄弁家としても有名で、雑誌 『雄弁』 にしばしば登場するヒーローであった。大正9年(1920)、衆議院で 「階級専政を主張する者、西にレーニン、東に原敬首相あり」 とやって物議をかもした。永井は原首相が資本家の走狗となって、大衆を抑圧していると非難したのである。因みに、三木内閣の文相、永井道雄は彼の次男である。
(写真は『国史大辞典』吉川弘文館から借用した)
詔勅を以て弾丸に代へ・・・

|
|
尾崎行雄
|
政界の雄弁家として永井に並ぶものに尾崎行雄がいた。大正2年(1913)の第30議会に政友会など野党は内閣不信任案を提出した。成立したばかりの第三次桂内閣は組閣の当初からつまずきを繰り返し、その都度、即位後日浅い大正天皇の詔勅やご沙汰をもらって切り抜けた。組閣の大命を拝したときに、桂太郎は内大臣兼侍従長であった。天皇を補佐する最高位の官職についていたのであった。世論は桂首相の態度を、袞龍(コンリュウ)の袖にすがって憲法を無視するものと非難した。袞龍とは天子の制服のことである。護憲運動の波は澎湃として日本国中を覆った。議会開会の当日も、国会は反対する民衆のデモに取り囲まれていた。護憲運動のリーダーであった尾崎は不信任案の提案理由の説明で、ひな壇の首相を指差しながら 「玉座を以て胸壁とし、詔勅を以て弾丸に代へて政敵を倒さんとする」 ものとして首相を論難した。桂首相は当初、議会を解散するつもりであったが、尾崎の演説を機に内閣総辞職を選んだ。尾崎の雄弁が引き金となって、桂首相は総辞職のやむなきに至ったのであった。桂はその年の秋には亡くなるのであるが、口さがないジャーナリズムは、尾崎の雄弁が桂の死期を早めたと囃(はや)したてた。議政壇上に獅子吼(ししく)するという表現は、当時の新聞が国会での名演説を形容する常套句であった。弁士が髪を振り乱し、身振り手振りも大袈裟に演説するのを、雄ライオンがたてがみを逆立てて咆哮する姿にたとえたものである。(写真は昭和11年2月17日、衆議院に於いて林内閣弾劾演説中の尾崎行雄。 『尾崎行雄』 吉川弘文館より借用した)。
民族の祭典
私が三年生時代の弁論大会で、私は 「民族の祭典を見て」 という演題でこの弁論大会に出場した。 昭和11年(1936)8月、ドイツの首都ベルリンで第11回オリンピック大会が開催された。このとき、宣伝を重視したドイツ政府は聖火リレーとか大規模で厳粛な開会式とか、従来のしきたりを破った新機軸を打ち出して世界を瞠目させた。その一部始終を映画にしたものが、レニ・リーフェンシュタール監督の映画 『民族の祭典』 であった。1938年、この映画が公開されるや、その芸術性が高く評価されて各種の賞を獲得した。私たち中学生もこの映画を見ることを奨励された。当時の中学生は原則として映画館への出入りは禁止されていた。禁を破ったことがばれると謹慎や停学の処分を喰らった。ただ学校当局が推奨するものだけは見ることが許された。私の記憶では中学生活の4年半のうち、学校が許可したものは、この映画とこの映画の続編である 『美の祭典』 だけであった。因みに、映画 『民族の祭典』 は聖火リレーから陸上競技までを収めている。水泳などは続編の 『美の祭典』 がカバーしている。一昨年(平成16年)、故郷の家を解体したときに、納戸(なんど)の奥の柳行李(やなぎごうり)から、私の小学校、中学校時代の図画、手工(工作のこと)、綴り方などの作品が出てきた。そのなかにこのときの弁論大会の原稿があった。完成原稿ではなく、諸所に訂正の跡があり、しかも 話の途中までしかない尻切れトンボの原稿なのである。ともかく当時15才の私が、何を考え、何を書いたか以下に記録しておきたい。参考までに、この大会で日本選手の出した入賞記録も下に掲げる。
 民族の祭典を見て(昭和16年度弁論大会原稿)
民族の祭典を見て(昭和16年度弁論大会原稿)
世界映画史上に燦然と輝く、ドイツ映画、『民族の祭典』 を見て、私は、私の胸の底深く流れてゐる大和民族としての力強い血潮の高まりを感ずる事が出来たのであります。
作者レーニ・リーフェンシュタールが、四十四名の撮影技師を指揮して、科学ドイツの面目にかけて、あらゆる光学レンズの悪条件を征服して製作されたと言う、『民族の祭典』は最近、ヨーロッパの天地に雄飛する盟邦ドイツの姿を見るかのようでありました。
「我々の夢は二千六百年の昔にさかのぼる」 と言う字幕にはじまり、古代ギリシャの競技華やかなりし、オリンピアの遺跡を写し、聖火をオリンピア・クロースの丘から、七ヶ国の首都を経て三千七十五粁のベルリン競技場へリレーしたのであります。全世界五十一カ国の選手たちはその聖火の下に 「我等はオリンピア競技に於いて、光栄ある戦士として、武士道精神に則(ノット)り、祖国の光栄のために戦はん」 と誓ったのであります。民族の心と力は、聖火とともにここオリンピック競技場に燃え上がったのであります。
ここに世界各国を代表せる五千の選手達によって敢闘の幕が切って落とされました。スタンドを埋めた十幾万の紳士淑女をもって自他共に許す英米の観客でさへ、自国選手の出場に我を忘れて、熱狂的声援を送るのは、けだしその祖国愛の一端にほかならないのであります。
競技は回を重ねて三段跳びに移りました。わが選手も参加するので日本人の声援も熾烈でありました。田島選手の一躍十六メートルを飛んで世界記録を立てるや、日本人席では総立ちになって歓声之を惜しまなかったのであります。ハンカチを振り、帽子を振り、さては上着を打振る間に、日の丸の扇が人々の手にかざされた時、僕は涙ぐましい気持ちに打たれたのであります。外国で見る祖国選手の勝利が斯くまで嬉しいものかと・・・。君が代奏楽裡に国旗が掲揚された時、誰か胸中に大和魂の躍動を感ぜぬものがあったでありましょうか。翩翻(へんぽん)と翻る日章旗を仰いで、感激の涙を流したであろう当時の日本人の心のなかは、蓋し察するに餘りがああります。
女子四百メートルリレーに於いて常に先頭を走っていたドイツの一選手がバトンを落とすや、見物のドイツ人の顔こそ見ものでありました。一選手の不覚がドイツ観衆は勿論、全ドイツ人を切歯させたことは当然の事実であります。選手の行動は直ちにその国家の行動であります。選手の一挙手一投足はよく数多の同胞を歓喜せしめ、選手の一挙手一投足はよく祖国の名を世界各国の間に重からしめるのであります。之が故に選手の責務は大きいと言わざるをえません。一国の名誉はかかってその雙肩にあるのであります。かの棒高跳びに於いて、漸く夕闇迫らんとする競技場に我が大江、西田の両選手が顔に悲壮なる決心を浮かべて、棒をかかえて走る姿には思はず粛然として襟を正さしめるものがありました。
原稿はここまでである。しかし当時の新聞記事を参照すれば、私が演壇で、続いて何をしゃべり、如何なる結論によって演説を締めくくったかは容易に想像がつくのである。1万メートル競走に出場した村社(むらこそ)選手のエピソードは必ず語ったに違いない。大男揃いの欧米選手に混じって,彼らの三分の二ぐらいの背丈しかない村社選手は終始トップを走って満場の観客の喝采を浴びた。結局、最後の一周で体力に勝る外国選手に抜かれて4位に落ちたのであるが、欧米の観客はこぞってこの村社の健闘をたたえた。朝鮮人の孫選手は日本代表としてマラソンで優勝した。南選手も朝鮮人で3位に入賞した。これにも言及したはずだ。 結局、オリンピック・ベルリン大会が日本の国威を宣揚したことを強調して話を終えたのであろう。
弁論部主将
意外にも私は四年生、五年生の弁論部のベテランを抑えて優勝した。最後に講評した弁論部長の飛騨先生は、私が弁論部ずれのしない、平談俗語で演説したことを誉めた。それに、演壇上に拡げた原稿用紙を、話の切れ目ごとに一枚づつめくっていったことまで、慎重で用心深く、落着いた態度だと誉めた。この弁論大会の後、弁論部長の飛騨先生に弁論部に入るよう要請された。この飛騨先生はわが忠中の先輩であった。三高から京大文学部を出て、母校の国語の教師であった。知らないことは知らないといい、率直で飾らない人柄は生徒から敬愛されていた。私としては優勝させてもらった負い目もあり、断ることはできなかった。四年生になると私は弁論部の主将になったらしい。らしいと言うのはこのあたりの記憶が欠落しているからである。ただ、十数名の弁論部員と一緒に
海岸に出て海に向かって発声練習をしたことだけは覚えている。一昨年の家屋解体の際、見つかった作文の把(たば)のなかに、昭和17年度(1942)の弁論大会の開会の辞の原稿があったのである。開会の辞は弁論部主将の役目だから、多分私は主将であったのだろう。それは内容の空疎な決まり文句を羅列した拙い文章である。しかも私がもともと嫌悪していた弁論部臭ただよう文章である。しかし如何に拙い文章であろうと、それはそれでわが精神成長の一過程を証明するものである。以下記録にとどめておくことにする。
昭和17年度弁論大会開会の辞
大東亜戦争の開始によって、わが国の歴史的使命達成の巨歩が踏み出された。大東亜共栄圏の確立が我々日本人の全責任であることが明らかになったばかりでなく、さらにわが国は世界新秩序建設のために、重大なる役割を演ずることになったのである。皇紀二千六百一年(1941)十二月八日、恐れ多くも宣戦の大詔が渙発されるや、陸に海に空に、皇軍のあげた大戦果は我等をして感嘆之を久しゅうせしむるものがあります。しかしながら翻って思へ、かかる大戦果の蔭に土にい寝、草に伏し、占領地宣撫の為、日夜、寝食を忘れて奔走してゐる人々のあることを。凡そ占領地の宣撫たるや洋の東西を問はず、時の古今を論ぜず、戦争の重要なる一部門であります。しからばこの戦争の重要なる一部門、宣撫の任を果たすものは何であるか。銃でもない、剣でもない、百万の軍隊でもない、烈々たる愛国の至情を以って説き来たり説き去る弁舌の力、即ち之であります。
その昔、西洋史上に有名なアレクサンドル大王の東征よりさらに一代前、マケドニア国王フィリップの攻撃によりギリシャ諸国が滅亡の危機に瀕したとき、アテネの大雄弁家デモステネスは、強大なる軍兵を擁するフィリップに対し、自ら余はフィリップの敵なりと稱し、痛烈骨を刺し、言々肺腑より出づる大弁論をなしてギリシャ民族の危機を警告した。さればさすがのフィリップも其の雄弁に恐れをなして、「アテネの陸海軍如何に強大なりとも、予は一蹴して之を破るべきも、ただデモステネスの三寸の舌頭に至りては之に敵するの術なし」 と嘆じた。デモステネスをして「予はフィリップの敵なり」と豪語せしめたものは何であるか。フィリップをして 「デモステネスが三寸の舌頭に至っては敵する術を知らず」 と歎ぜしめたものは何であるか。それは彼、デモステネスの雄弁であります。而して其の雄弁たる、愛国の熱情燃ゆるがごとく、言々句々、人を動かすの真雄弁であったのであります。
人或いは 「雄弁は銀なり、沈黙は金なり」 と云ふ。併しながら其の金のごとき沈黙から迸りい出たる雄弁は金以上であります。プラチナであり、ダイアであります。否、否、かかる物質的なものではありません。人類の胸奥からい出たる生命の流れであり、活き活きとしたる心の聲であります。雄弁は、亦言語の技巧ではない。心を以って心に傅へ、誠を以て誠に傅へるものであります。されば我が占領地の宣撫よろしきを得て皇軍の大戦果をさらに輝かしきものにするを得、デモステネスの雄弁、よくフィリップの軍隊に抗するを得たのであります。
かく考えてくるとき、我々は国家の難局に際して、雄弁の有する意義たる真に大なるを知らねばなりません。而してここに雄弁大会の開かれる意義亦決して軽しとしないのであります。
昭和維新の歌
私が弁論部に入った頃には、すでに広島県下中等学校の弁論大会は開かれなくなっていた。支那事変は3年目に入っており、米英との関係は悪化しつつあった。時局は非常時なのだ。空論をもてあそんでいる時代ではないというのである。 五・一五事件の首謀者のひとり、三上卓海軍中尉の作詞と伝えられる
「昭和維新の歌」が、ひそかに青年の間に歌い継がれていた。その最終節は次のようなものである。
十、やめよ離騒
りそう
の一秘曲
悲歌
ひか
慷慨
こうがい
の日は去りぬ
我らが剣
つるぎ
今こそは
廓清
かくせい
の血に踊るかな
昭和7年(1932)5月15日未明、三上ら青年将校は首相官邸に拳銃を擬して乱入した。彼らは 「話せば分かる」 と制止する犬養毅首相を 「問答無用」 と叫んで射殺した。後の昭和11年(1936)の二・二六事件の前兆をなす一大凶事であった。それはまた、弁論が軍人の暴力によって封殺された象徴的な事件でもあった。この事件あたりから、悲歌慷慨の弁論は無用視され、明治以来のわが国の雄弁の伝統は次第に消滅に向かうのである。上の歌詞のなかの離騒とは、楚の人、屈原の憂国の詩である。今から二千四百年も前の支那の戦国時代末期、清廉の士、屈原は楚の宰相であったが、彼を煙たく思う仲間の讒言にあって、政府を追放される。乞食の境遇に身を落として国内を放浪する途中、汨羅(べきら)の淵に身を投じて自殺する。この歌の冒頭の句 ”汨羅(べきら)の淵に波騒ぎ” はこの史実を指す。廓清(かくせい)とは聞きなれない言葉である。悪いところを取り去って祓い清めることをいう。この歌の二番はこういっている。”権門上に奢れども 国を憂うる誠なし 財閥富を誇れども 社稷(しゃしょく)を思う心なし”。 廓清の対象は権門と財閥なのであった。この廓清という言葉は、一般には死語となっているが、医学用語として今に残っている。 大腸癌手術後、転移を防ぐため、近くのリンパ節を廓清するなどと使う。
成績
忠海中学校に入ったものの1学期の間は宿痾の盲腸炎手術とか右足首の関節炎の治療のため学校を休むことが多く、中間試験も受けることが出来なかった。期末試験は受けたが結果は惨めなもので、学期末の通信簿は乙と丙の並ぶ異様なものであった。このままでは2年に進級は覚束ないと受持教諭から告げられた父は驚き怒り、もし落第するようなことになったら退校させると宣言した。新しい友達も出来、漸く中学生活に慣れてきた私は、退校させられてはかなはないというのでその夏休みは水泳もやめて勉強に集中した。
猛勉の甲斐あって、1年生の総合成績は6番となり、退校しなくてもよくなった。当時わが学年の総人員は130数名でそれが3組に分かれていた。各組に級長、副級長(わが学校では幹事、副幹事と称した)がいて前年度の成績順に学校から任命された。私は1組の副級長になった。2年生の総合成績は2番になったので3年生では2組の級長になった。3年生の総合成績は1番で、4年生になると1組の級長となった。
成績の上昇と共に見違えるように健康になった。中学での激しい運動と汽車通学という規則正しい生活が、成長期の私の身体に好影響を与えたのだろう。小学校時代は四大節や朝礼で脳貧血のため何時も倒れていたが、中学入学以来一度もそういうことはなかった。毎日昼休みになるのが待ち遠しく、昼食の弁当を食べ終わるや校庭で友達と相撲を取ったり、器械体操に興じた。誰も教えてくれる者はいなかったが4年生になると大車輪ぐらいは出来るようになった。

写真説明
昭和17年(1942)4月、4年生に進級した直後、親友の古久保恭一(故人)と放課後、写真屋で撮影(向かって左側古久保)。私の制服の左襟にはローマ数字のⅣの徽章が付いている。これは4学年であることを示す。右襟の1は1組に所属することを示す。その隣の金メッキのスターマークは級長の印である。古久保は呉市の一流中学呉一中の入試に失敗してわが中学に入ってきた落武者であった。このような落武者がわが学年には十数名いた。彼らは一応標準語を話し、社会万般について豊富な知識を持っていた。成績もおおむねクラスの上位を占めていた。時には英語や数学で先生をやり込めるものも出てきた。田舎弁丸出しの私は彼らにからかわれながらも彼らから多くを学んだ。小学校では勉強しなくても級長になるのは当たり前であったが、中学では怠ければ落伍することも初めて知った。
呉市と忠海町の間は汽車で1時間半ほどかかった。彼らは冬など星を頂いて家を出、星を頂いて家に帰る毎日であった。5年間にわたって弁当を作り続けた母親の苦労も大変だったろう。
 私の中学4年生時代の写真を出したついでに、後に私の妻となる植木みよ子の女学校5年生時代、仲の良い友達と一緒に撮った写真を載せることにする。場所は東京渋谷区常磐松の実践高等女学校校庭、時は昭和18年3月、卒業直前。前列向かって右、生徒監の大田浄信先生、その左、植木みよ子。太田先生は海軍兵学校第30期、中佐で予備役に編入された後、女学校の教師になられた方である。因みに、当時聯合艦隊司令長官であった山本五十六大将は、海兵第32期であった。
私の中学4年生時代の写真を出したついでに、後に私の妻となる植木みよ子の女学校5年生時代、仲の良い友達と一緒に撮った写真を載せることにする。場所は東京渋谷区常磐松の実践高等女学校校庭、時は昭和18年3月、卒業直前。前列向かって右、生徒監の大田浄信先生、その左、植木みよ子。太田先生は海軍兵学校第30期、中佐で予備役に編入された後、女学校の教師になられた方である。因みに、当時聯合艦隊司令長官であった山本五十六大将は、海兵第32期であった。
受験勉強(1)
中学3年になって私は志望する上級学校を海軍兵学校に決めた。高等学校にも行きたかったが家の経済を考えると難しい。それでは金のかからない学校を選ぶほかはない。当時の軍国主義の風潮から、全国の優秀な中学生が陸軍士官学校、海軍兵学校の採用試験に殺到した。公表されてはいなかったが当時の採用人員は前者で約2千人、後者で約6百人であった。採用人員が限られているため競争率は高かった。私には泥臭い陸軍よりも、近代兵器を駆使して戦う海軍のほうが魅力的であった。短剣を吊ったスマートな海兵の制服も悪くない。受験界の評価は海兵のほうが陸士のワンランク上であった。より困難なほうに挑戦するということで私の気持ちも奮い立った。
わが中学は創立が明治中期にさかのぼる歴史と伝統のある県立中学であったが県下では二流であった。一流二流は生徒の上級学校入学率で計られること現在と変わらない。一流校は皆大都会にあった。一流校の教師の質は高くまた大都会には進学塾もあり、上級学校受験に備えた体制も完備していた。一流校の生徒に伍して難度の高い上級学校を受かるには並大抵の準備ではかなはないだろう。私はすぐれた受験参考書を精読することを受験準備の基本とすることにした。それに時々通信模擬試験に応募して実力の判定をする。事実田舎のこととてこれ以外の方法はなかった。
購入した受験参考書のうち今でも題名や著者名を覚えているのは次のようなものであった。
|
〇 |
受験英語単語熟語の総合的研究 |
赤尾好夫著 |
歐文社 |
|
〇 |
英文標準問題精講 |
原 仙作著 |
同上 |
|
〇 |
高等自由英作文 |
矢吹勝二 |
研究社 |
|
〇 |
受験代数学の総合的研究 |
高津 巌著 |
歐文社 |
|
〇 |
受験幾何学の総合的研究 |
同上 |
同上 |
|
〇 |
国文解釈の総合的研究 |
保坂弘司著 |
同上 |
|
〇 |
国文法の総合的研究 |
同上 |
同上 |
歐文社は現在の旺文社である。大東亜戦争の勃発によって、社名に歐の字を入れ
るのは欧米崇拝と見られるので旺文社と改名した。研究社と並んで受験産業の大手であった。同社は受験界のニュース,上級学校の難易度,入学試験の出題傾向などなどを満載した旬刊誌『受験旬報』を発行していた。これも後に『蛍雪時代』と改名され月刊誌となった。この雑誌は田舎の中学生が上級学校入試に関する知識を得る唯一のソースであった。私は毎月購読こそしなかったが友達と交換したりしながら一応目を通していた。余談であるがこの雑誌に小説欄があり読者の応募原稿を掲載した。「真帆高く」という題名の小説を今も覚えている。高等学校を目指して日夜勉強に励む貧家の中学生の、隣家の女学生との淡い交情を描いたものであった。私は他の受験記事と同様の熱心さでこれらの小説を読んだ。昨年亡くなった作家の山田風太郎は中学時代にこの小説欄の常連寄稿家であった由。他の応募作品とはレベルを異にするすぐれたものであったとは当時の同誌の編集者の述懐である。
受験勉強(2)
私だけでなくわが学年で成績上位に位する実力者の連中は皆3年生になるやそれぞれ志望する上級学校を決めて受験勉強に突入した。志望校が複数であったり、未決定の仮想目標であったりと内容はさまざまだが、ともかく何者かに突き動かされるような気持ちで走り出したといえば言えよう。一流校の生徒に比べ学力に差があることをみんな自覚していた。放課後、通学列車を待つ時間には友達同志校庭の芝生に寝そべって、上級学校の品定めや、やがて進学した場合の生活について語り合った。それは又受験界の情報を交換する貴重な時間でもあった。
そんなわが中学でも各学期半ばに行われる模擬試験という制度があった。これは上級学校入試問題を想定した自由な設問によって受験者の実力を調べるというもので、これを受けるのは4年生、5年生のうちの進学希望者に限られた。わが中学では4年生、5年生あわせて150名位が受験したであろうか。模擬試験の成績によって志望校を決めたり、変えたりするという進学希望者にとっては重要なものであった。これは現在進学塾でやられている模擬試験とあまり変わらないものだろう。試験は英語、数学、国語・漢文の3科目で行われ、各科目百点満点、合計300点、結果は成績順に一覧表とされ、通用門脇の掲示板に張り出された。
われわれは4年生になった年の6月に初めての模擬試験を受けた。その結果私は1番であった。正確に言えば合計点数の同じ1番が2人いた。1番のトップに掲出されたのは5年生の池田峰夫で、私の氏名と各科目の得点は2番目に出ていた。池田は数学で私を超え、英語と国漢では私が彼を抜いていた。池田は級長でも副級長でもなかったが過去の模擬試験成績で何時も5位以内に入るという実力者であった。彼の1番を誰も不思議なことと思わなかった。しかし私の場合4年生で初めて受験して1番というのは稀有のことであったので、全校がびっくりした。そもそも級長副級長というのは点取り虫のがり勉亡者である。教科書とサンモン(虎の巻のことをわが中学ではこう呼んだ)を丸暗記して,先生に贔屓してもらっているだけで、実力はたいしたことはないというのが大方の評価であった。事実、4年、5年合わせて12名の級長副級長のうち、毎学期の模擬試験で10位以内に入るのは2、3名であった。私は4年生のトップに立って4年1組の級長であるが、このような一般の評価に大いに不満であった。そうであっただけにこのときの1番は心底から嬉しかった。
私はその後海軍兵学校に合格し,戦後は東大に合格するなどおよそ上級学校入試に失敗したことはなかった。しかし、これら学校に合格した嬉しさもこのときの模擬試験の1番の嬉しさに勝るものではなかった。成績表の張り出された掲示板の前に群がっておしゃべりをしている下級生の前を通るときの晴れがましさ、面映さの混じった高ぶった気持ちは今に忘れ難い。余談であるがこのときの模擬試験で1番を分け合った5年生の池田は三高、京大を経て若くして同校地球物理学の教授となった。
私の昭和史・第二部、 私の昭和史・第一部、 ホーム




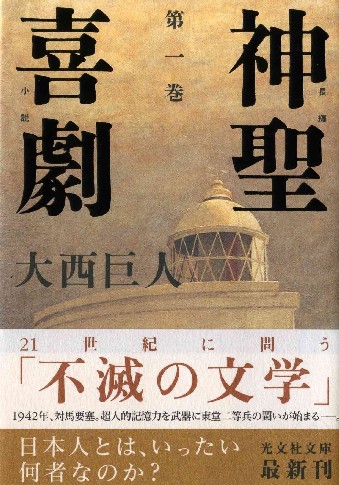 余談であるが、『神聖喜劇』 は著者大西巨人の、少年時代から軍隊時代にかけての自伝的小説である。彼は福岡の F 中学から旧制高校に入るのだが、中退をして就職する。召集されて對馬の砲兵連隊に入り最下級の二等兵からつとめる。陸軍には兵隊の実生活を細かく規制する内務法規がある。下士官や古参兵は、この法規の規定をたてにとって下級兵をいじめる。ところが大西は稀代の記憶力にものをいわして 『軍隊内務書』や『砲兵操典』 を丸暗記し、逆に上級者の揚げ足をとって、いじめに屈しない。古参兵はこの新兵の下克上に腹を立てるのだが、法規の引用と解釈には大西にかなわないので、どうすることもできない。五味川純平の 『人間の条件』(文春文庫 全6冊) の主人公、梶上等兵が体力と胆力で危機を脱するのを、大西二等兵は智力で切り抜けるのである。梶上等兵は終戦直後の満州で、壊滅した関東軍の中から奇跡的に生還する。両書はいずれも日本陸軍の下級兵を主人公にしている。しかし 『人間の条件』 の暗鬱(あんうつ)にたいし、『神聖喜劇』 は明朗である。からりとして明るいのだ。それに著者は小説中に内外古今の典籍を引用して該博な知識を披露する。私は文庫本の各巻が発行されるのを待ちかねて読んだ。戦後のわが国の文学のなかで最高傑作と激賞する批評家もいる。
余談であるが、『神聖喜劇』 は著者大西巨人の、少年時代から軍隊時代にかけての自伝的小説である。彼は福岡の F 中学から旧制高校に入るのだが、中退をして就職する。召集されて對馬の砲兵連隊に入り最下級の二等兵からつとめる。陸軍には兵隊の実生活を細かく規制する内務法規がある。下士官や古参兵は、この法規の規定をたてにとって下級兵をいじめる。ところが大西は稀代の記憶力にものをいわして 『軍隊内務書』や『砲兵操典』 を丸暗記し、逆に上級者の揚げ足をとって、いじめに屈しない。古参兵はこの新兵の下克上に腹を立てるのだが、法規の引用と解釈には大西にかなわないので、どうすることもできない。五味川純平の 『人間の条件』(文春文庫 全6冊) の主人公、梶上等兵が体力と胆力で危機を脱するのを、大西二等兵は智力で切り抜けるのである。梶上等兵は終戦直後の満州で、壊滅した関東軍の中から奇跡的に生還する。両書はいずれも日本陸軍の下級兵を主人公にしている。しかし 『人間の条件』 の暗鬱(あんうつ)にたいし、『神聖喜劇』 は明朗である。からりとして明るいのだ。それに著者は小説中に内外古今の典籍を引用して該博な知識を披露する。私は文庫本の各巻が発行されるのを待ちかねて読んだ。戦後のわが国の文学のなかで最高傑作と激賞する批評家もいる。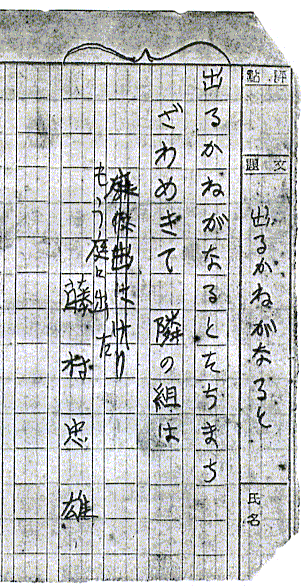


 民族の祭典を見て(昭和16年度弁論大会原稿)
民族の祭典を見て(昭和16年度弁論大会原稿)
 私の中学4年生時代の写真を出したついでに、後に私の妻となる植木みよ子の女学校5年生時代、仲の良い友達と一緒に撮った写真を載せることにする。場所は東京渋谷区常磐松の実践高等女学校校庭、時は昭和18年3月、卒業直前。前列向かって右、生徒監の大田浄信先生、その左、植木みよ子。太田先生は海軍兵学校第30期、中佐で予備役に編入された後、女学校の教師になられた方である。因みに、当時聯合艦隊司令長官であった山本五十六大将は、海兵第32期であった。
私の中学4年生時代の写真を出したついでに、後に私の妻となる植木みよ子の女学校5年生時代、仲の良い友達と一緒に撮った写真を載せることにする。場所は東京渋谷区常磐松の実践高等女学校校庭、時は昭和18年3月、卒業直前。前列向かって右、生徒監の大田浄信先生、その左、植木みよ子。太田先生は海軍兵学校第30期、中佐で予備役に編入された後、女学校の教師になられた方である。因みに、当時聯合艦隊司令長官であった山本五十六大将は、海兵第32期であった。