

|
| メゴチ |
| (木村義志著『魚と貝』主婦の友社より) |

|
| 新婚当時の父 |

|
| 徳富蘇峰 |

|
| 土肥周丸 |
| 治田栄一 |

|
| 琴平神社にて、昭和17年11月中旬 |

|
|
兵学校入校直後西生徒館中庭にて写す 昭和17年12月中旬 |

|
| 江田島の写真館にて 昭和18年6月 |

|
| 父と孫 田舎の家の縁側で 昭和36年2月28日 |
 昭和43年(1968)5月、私は川崎汽船の駐在員としてインド西海岸の港町、ボムベイに赴任した。日本/インド・パキスタン・ペルシャ湾航路の維持とペルシャ湾岸産油国への目配りが主な任務であった。ボムベイは現在では英人のつけた名前を廃してムンバイと称している。ムンバイとは数百年前、まだボムベイが漁村であった当時の地名という。ボムベイのみならずベンガル湾の最奥部に位置するカルカッタはコルカタに、南部のマドラスはチェンナイに改名された。インド人として自分の祖国の主要都市の名前がかつての征服者による命名のままでは面白くないのであろう。しかしわれわれ一時滞在者であった者としては、新しい名前は耳に馴染まず、懐かしさも半減する思いである。 右の地図は George Philip の Modern Home Atlas から借用した。
昭和43年(1968)5月、私は川崎汽船の駐在員としてインド西海岸の港町、ボムベイに赴任した。日本/インド・パキスタン・ペルシャ湾航路の維持とペルシャ湾岸産油国への目配りが主な任務であった。ボムベイは現在では英人のつけた名前を廃してムンバイと称している。ムンバイとは数百年前、まだボムベイが漁村であった当時の地名という。ボムベイのみならずベンガル湾の最奥部に位置するカルカッタはコルカタに、南部のマドラスはチェンナイに改名された。インド人として自分の祖国の主要都市の名前がかつての征服者による命名のままでは面白くないのであろう。しかしわれわれ一時滞在者であった者としては、新しい名前は耳に馴染まず、懐かしさも半減する思いである。 右の地図は George Philip の Modern Home Atlas から借用した。
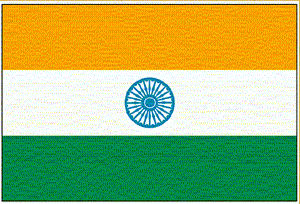
|
| インド国旗 |
|
|
| 購入したフラットの間取図 |

|
| 昭和45年(1970)新年会 於ボムベイ日本総領事館 |

|
| タジ・マハール |

|
| 練習艦隊司令官 |
| 海将補 本村哲郎 |

|
| 練習艦隊旗艦 てるづき 2350トン |

|
| わがフラットの入口にて |
| 向かって左から中山、小室、私、植田、高田 |